


ヒノキの間伐材を切り出す
茨城県石岡市にある小社保有林、ソローの山でヒノキの間伐材を伐採します。かかり木と言って、他の木によりかかって倒れない状態にならないように、伐倒方向を計算するなど、熟練の技が光ります。

製材して板状に加工する
切り出した間伐材の皮をむき、近隣の製材所に持ち込みます。出来高の割合を意味する歩留まりの良し悪しが決まるので、製材行程は大きな注意を払う必要があります。

レーザーでカットする
製材されたヒノキの板材をみね子さんの形状にレーザーでカットします。あらかじめ組まれたプログラムによって複雑な形状の切断や穴あけ加工ができます。

焼き印を押す
ホットスタンプ機でひとつずつ焼き印を押していきます。焼印加工での失敗の多くは長時間強く押しすぎて焦がしてしまうこと。綺麗に仕上げるために適切な温度で短時間押し当てます。

チャームを取り付けて完成!
1枚1枚ていねいにバリやささくれがないかを検品し、木くずの除去を行います。
その後、チェーンを取り付け、包装工程を経て完成です!


国土の約7割を占める森林は、日本の環境・防災・地域経済を支える基盤です。そのうち4割強は戦後に造成されたスギ・ヒノキ主体の人工林で、いま、本格的な高齢期を迎えています※。
しかし林業従事者の減少や木材価格の低迷などにより、適切な手入れが行き届かない“放置林”が各地で増加。これがさまざまな環境問題を引き起こしつつあります。
日本の森林が直面する課題と、解決の鍵となる「間伐」と「間伐材」の大切さを山めぐり猫・みね子さんが解説してくれます。
日本の森林が抱える
5つの環境課題
土砂災害のリスクが高まっている
密に植えられた人工林では土がやせ、根も浅くなるため、大雨のときに斜面が崩れやすくなります。国交省の統計では、森林が関係するとみられる崩落がこの10年で約1.4倍に増加しています。

CO₂吸収量の停滞
若い木ほど成長が早くCO₂もたくさん吸いますが、高齢期に入るとその勢いが鈍ります。手入れを怠ると、2030年代以降は日本の森林全体の吸収量が少しずつ減っていくと国立環境研究所は見込んでいます。
生物の減少
暗い人工林では地面まで光が届かず草木が育たないため、昆虫や鳥など多様な生きもののすみかが失われています。
外来・獣害問題
ニホンジカやイノシシが増え過ぎて森を食べつくしたり、アライグマなどの外来種が広がって生態系に影響を及ぼしています。
木を生かしきれず、地域経済も停滞
人工林の木は毎年約1億m³増えていますが、伐って使われるのは3割以下。林業の採算も苦しい状況です。
「間伐」ってどんな作業?
人工林では、成長に合わせて計画的に木を間引き、混み過ぎないように保つ作業を「間伐」と呼びます。光と風が入りやすくなり、残った木がすくすく育ちます。地面にも日が差すので下草や広葉樹が戻り、生きものの種類も増加。根がしっかり張ることで斜面が安定し、森全体のCO₂吸収力も若返ります。

「間伐」がもたらす効果
間伐を行うと、人工林はさまざまな面で元気を取り戻します。たとえばCO₂を吸う力がぐんとアップし、間伐してから約10年間は木1本あたりの年間吸収量が最大25%伸びると報告されています。また、根もしっかり張るようになるため、大雨のときの斜面崩れのリスクが最大40%減るという嬉しい効果も。さらに光が森の奥まで届くようになり、下草や広葉樹が戻ってくることで生きものの種類も豊かになります。実際、奈良県の試験地では、間伐後5年で植物の種類が2.4倍に増え、昆虫や鳥もいっそう多様になったそうです。こうした変化は、森の明るさが改善されたことが大きな理由と考えられています。
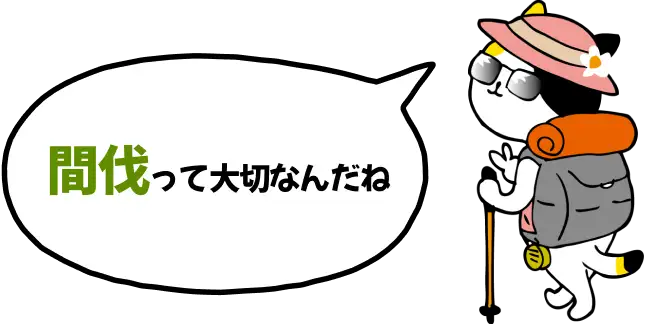
「間伐材」は“副産物”ではない
切った木はそのまま「炭素の缶詰」。燃やさない限りCO₂を閉じ込め続けます。細くて低品質な木でもチップやペレットにして発電・熱利用ができ、化石燃料の代わりに使えば年間1,500トンのCO₂を減らせた例も。さらに木質プラスチックや紙ストロー、セルロースナノファイバーなど新素材の原料にもなり、地域の新しい産業と雇用を生み出す力を持っています。
これからの課題と展望
間伐が必要な人工林は年間35万haありますが、実際に行われているのは半分ほど。コストを下げる工夫、人手の確保、木材需要の拡大を同時に進める体制づくりが急がれます。
とくに需要面では、公的建物だけでなく民間の建物にも木をもっと使うよう「木造化」を後押しし、補助金や税優遇、技術支援で木材の普及を加速させることが鍵になります。
おわりに
間伐は森を元気にしながら、気候変動対策・防災・生物多様性保全など多くのメリットをもたらします。伐った木を余さず活用すれば、その効果はさらに大きくなります。私たちが国産木材製品や再生エネルギーを選ぶことも、森を支える力になります。人と森がもう一度しっかりつながる循環をつくれるか――今、その正念場に立っています。
※林野庁『森林・林業白書令和4年度』(2023)

