エッセイスト 玉村豊男さんの
茹で牛肉のポテトサラダ添え



薬膳の世界には「薬食同源」、
つまり健康に良い食事の大切さを説く言葉があります。
体が喜ぶ食事にくわしい8人の方に、
おいしく食べて夏を元気に乗り切る、
とっておきのレシピを教えていただきました。



●牛肉(スネ肉またはランプ肉の塊、1人当り100〜120g)
●ソース(オリーブオイル、しょうゆ、ハラペーニョなど)…適量
●塩、黒コショウ…適量



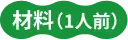
●豚スペアリブ…2本(200〜250g)
●冬瓜(ワタを除き、薄く皮をむき、ひと口大に切る)…ワタと皮つきで250g
●長ねぎ(斜め切り)…1/2本
●油…小さじ2
●合せ調味料 (混ぜ合わせる)
●青じそ(せん切り)…5枚



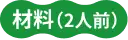
●なす…3本
●牛薄切り肉…80g
●わけぎの小口切り…1本分
●合せ調味料
●片栗粉…小さじ1(水大さじ1で溶く)
●太白ごま油…大さじ1
●花椒粉…小さじ1/3


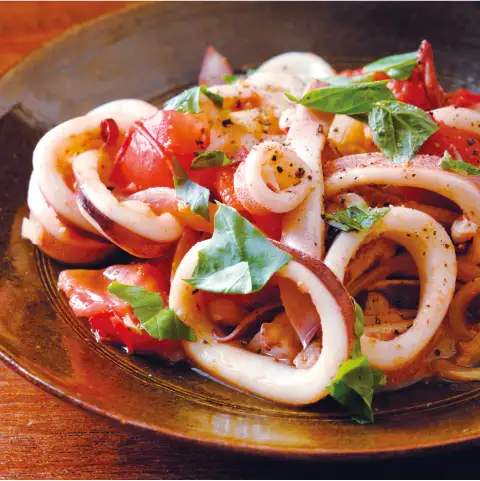
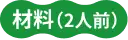
●生イカ…1杯
●トマト…1/2個
●玉ねぎ薄切り…1/4個分
●ニンニクみじん切り…1片分
●赤唐辛子輪切り…少々
●バジル…1枝
●オリーブオイル …大さじ2
●塩…小さじ1/3
●コショウ…少々



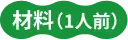
●マグロの刺身…6枚程度
●酒・しょうゆ・みりん…各大さじ1
●卵黄…1個
●温かいごはん…1杯分
●のり・長ねぎ・ごま…各適量
●おろしわさび…適量



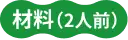
●なす…1個
●モロッコいんげん…2本
●木綿豆腐…1/3丁(100g)
●しょうゆ糀(※)…大さじ2
※米糀に同量のしょうゆを加えて3日~1週間室温で発酵させたもの。1日1~2回混ぜて発酵を促す。


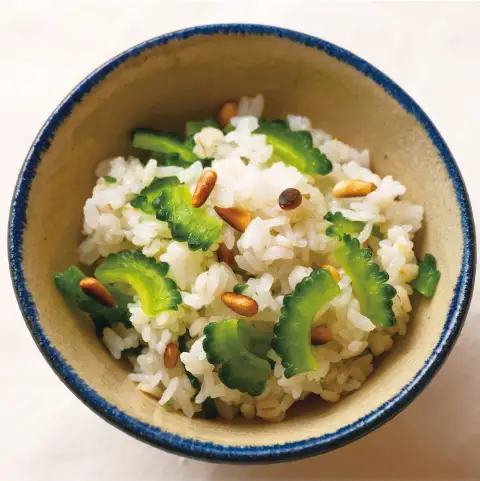
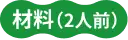
●温かいごはん…2人分
●ゴーヤ…1/3本
●松の実…大さじ2
●塩…小さじ1/2
●砂糖(甜菜糖等)…小さじ2/3



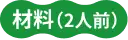
A
●長芋…100g
●味噌…大さじ1
●かつお節…1パック(4g)
●わさび…適量
