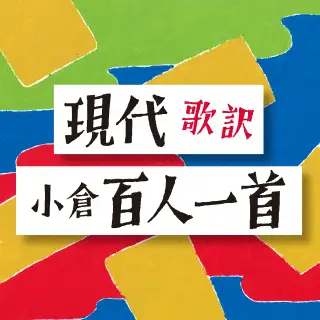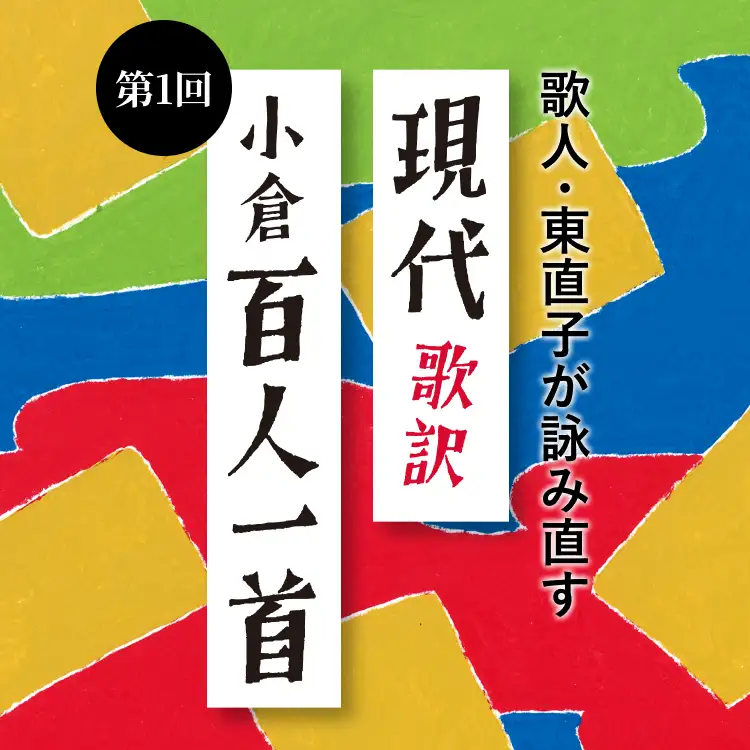
第1回
漫画や映画の影響で子どもたちにも人気の『小倉百人一首』を、歌人・作家の東直子さんに毎回5首ずつ、現代語で詠み直していただきます。第1回は、持統天皇・柿本人麿・安倍仲麿・喜撰法師・小野小町の5首。秋の夜長にしっとりとお楽しみください。

東直子さん
ひがし・なおこ/歌人、作家。1963年、広島県生まれ。96年歌壇賞受賞。2016年『いとの森の家』で第31回坪田謙治文学賞受賞。歌集に『春原さんのリコーダー』(ちくま文庫)、歌書に『短歌の時間』(春陽堂書店)ほか多数。
URL:http://www.ne.jp/asahi/tanka/naoq/
春過ぎて
夏来にけらし白妙への
衣干すてふ天の香具山
持統天皇
春は去り夏到来ね
純白の衣を干すよ天の香具山
初夏、山に吹く気持ちのよい風に、白い布がはためきながら乾いていく様子が見えて、とても気持ちがよい歌である。作者の持統天皇は、天智天皇の娘。高貴な人が詠む「白妙の衣」 はただの洗濯物ではなく、神聖な意味を帯びる。「天の香具山」は、奈良県橿原(かしはら)市にある大和三山の一つ。
あしびきの山鳥の尾の
しだり尾のながながし夜を
ひとりかも寝む
柿本人麿
山鳥のやたらと長い尾のように
長い夜だな一人で寝るのか
「あしびきの」は「山」にかかる枕詞。「あしびきの山鳥の尾のしだり尾の」が、「ながながし」を呼び出す序詞である。一人で寂しく過ごす夜の体感的な時間の長さを山鳥 (キジの一種) で表現するとは、とても斬新である。「~の」を繰り返す韻律が、ゆったりと流れる時間に音楽的な味わいを与えている。
天の原
ふりさけ見れば春日なる
三笠の山に出でし月かも
安倍仲麿
大空をふりあおいだらああ春日、
三笠の山に出ていた月が
作者の安倍仲麿は、遣唐留学生として唐に渡り、玄宗皇帝に長年仕えた後、 船の難破で帰国できず、日本に戻ることなく生涯をそこで終えた。おおらかな韻律の、のびやかな情景が印象的な歌だが、切実な望郷の念が込められてもいる。
わが庵は都のたつみ
しかぞ住む世をうぢ山と
人はいふなり
喜撰法師
マイホームは都心の東南いい感じ
憂鬱山と人は言うけど
「たつみ」は東南の方角のこと。「しか」は「このように」という意味。鹿と掛けているという説もある。「うぢ山」 は、都(京都)の東南に位置する宇治山のこと。「宇治」 の音から「憂し」の意味を引きだし、 諧謔的に表現したのだ。 ウィットに富んだ歌を詠んだ喜撰法師は仙人だったともいわれ、その生涯は謎である。
花の色はうつりにけりな
いたづらに我が身世にふる
ながめせしまに
小野小町
花々は色あせるのね
長い雨ながめて時は過ぎゆくばかり
絶世の美女と称された小野小町が、花がしだいに変化していくこと、経年によって自分自身の容色が衰えていくことを重ねた。「ながめ」は、「長雨」と「物思い」の二つの意味を重ねた掛詞となっている。老いをテーマに、歳月の残酷さを冷静に客観視し、技巧的でありながらやわらかな韻律の歌に仕上げ、確かな才を感じる一首である。
出典
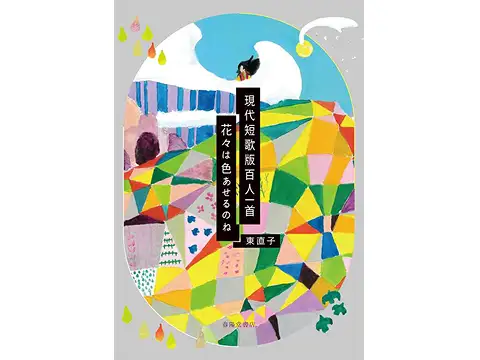
『現代短歌版百人一首 花々は色あせるのね』
東直子著 春陽堂書店