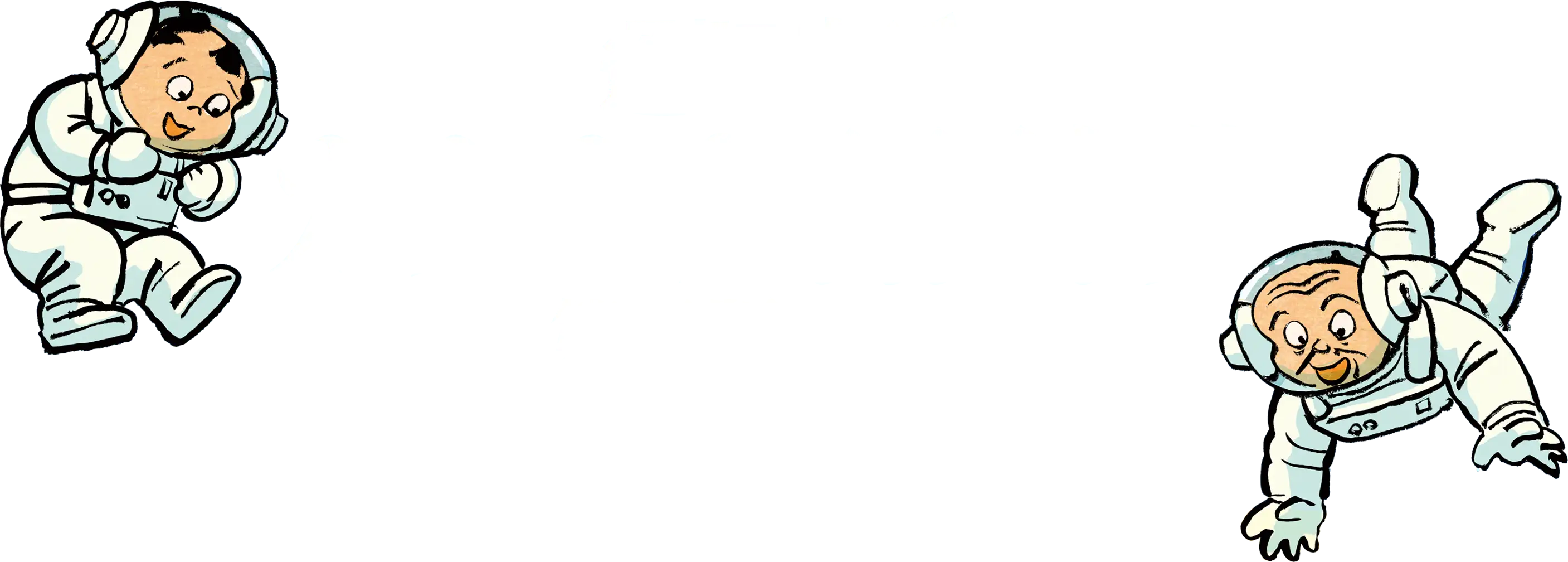ラ
-
ラーニング
-
学習、習得。
e―
コンピュータを利用した学習方法。
―ディスアビリティ(LD)
知能は正常でありながら、読み書きや計算など特定の学習が困難な障害。
-
ライトノベル
-
小説の分類の一つ。和製英語で、ラノベと略される。SFやホラー、ミステリー、恋愛などの要素を、読みやすい文体で書いた娯楽小説で、カバーと本文にイラストが使われる。主な読者層は10~30代。
-
ライフサイエンス
-
生命科学。生物学を中心に化学、物理学、医学、心理学、社会科学などから生物体と生命現象を総合的に研究する学問。
-
ライフライン
-
電気、ガス、水道、交通、通信など安全な生活を維持するために不可欠なもの。
-
ライブラリー
-
図書館、蔵書。コンピュータで、複数のデータなどをまとめて保存しておくところ。
-
ライン(LINE)
-
日本のライン社が2011年にサービスを開始した、文章や音声で会話できるスマホ向けの無料通話アプリ。SNSの一つ。
―ビデオ通話
お互いの顔を見ながら会話ができる通話機能。
―ペイ
スマホを利用して支払いをすませる決済サービス。
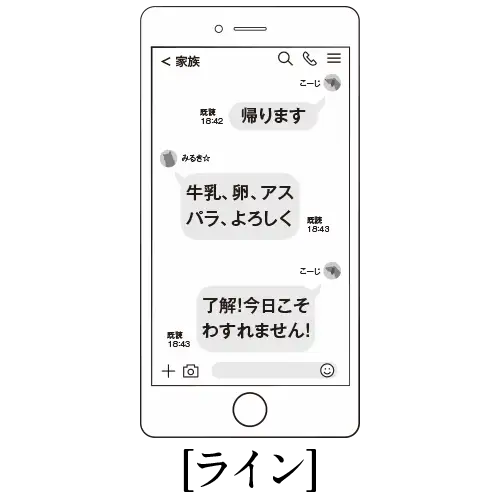
-
ラグジュアリー
-
贅沢品、高級品、贅沢なこと。
-
ラジコ【radiko】
-
民放ラジオ局と大手広告会社の電通の14社で設立した会社が運営するラジオ聴取サービス。現在、民放ラジオ全99局の番組をパソコンやスマホのアプリで聴くことができる。聴き逃した場合も、1週間以内の聴取が可能。
-
ラニーニャ現象
-
太平洋赤道域の日付変更線付近から南米ペルー沿岸にかけての海面水温が平年より低い状態が続く現象。逆に、同海域の海面水温が平年より高い状態が続くことがエルニーニョ(スペイン語で「男の子」)現象と呼ばれていたことから、その反対語として「女の子」を意味するこの名が付いた。ともに世界的な異常気象の原因とされる。
-
ラベルレス
-
ペットボトルに貼付するラベルをなくした飲料や食品のこと。箱やパッケージ単位で販売される場合、法律で義務付けられた製品情報や分別回収のための表示が個々のボトルには不要になったことから生まれた。ゴミが減り環境への負荷が下がるほか、見た目がすっきりしてデザイン的に好まれる傾向がある。
-
ランドマーク
-
歴史的な建造物や観光施設、町並み、山など、その地域の目印や象徴となるもの。
-
ランニングコスト
-
運転資金、維持費。企業が経営を続けるために必要な費用や、設備、機械などを維持するための費用を指す。
リ
-
リアクション
-
反応、反動、反響。例)菅首相の日本学術会議問題への発言に対して国民からの―が止まらない。
-
リアルタイム
-
即時に、同時に。
―視聴
放送中のテレビ番組などを放送時間中に試聴すること。
-
リーク
-
秘密や重要な情報を故意に漏らすこと。例)新聞社に―する。
-
リーズナブル
-
理にかなっている。(値段が)手頃なこと、妥当なこと。
-
リカバリー
-
回復、復旧、立ち直り。
グリーン―
新型コロナの流行で打撃を受けた経済を、環境問題への取り組みを通して立て直そうとする政策。
-
リカレント教育
-
リカレントは「繰り返す」「循環する」の意味。社会人になってから再度学校などの教育機関で学び、また社会へ出るのを繰り返すこと。社会人の学び直し。
-
リスク
-
危険、不確実性。
―ゼロ
危険がなく安全な状態。
―ヘッジ
金融取引で、損失の危険を回避する対策をとること。
-
リスケ
-
リスケジュールの略で、予定や計画の変更、組み直しのこと。例)先方の都合で会議が―になった。
-
リストラ
-
リストラクチュアリングの略で、再構築、再建のこと。不況のときに企業が、不採算部門の縮小や新規事業の展開などによって経営内容を改善すること。人員削減の意味で使われることが多い。
-
リテラシー
-
①ある分野に関する知識や情報を理解、活用する能力。②文字を読み書きする能力。
メディア―
テレビ、新聞、インターネットなどの情報を読み解き、活用する能力のこと。
-
リノベーション
-
修復、改善、改造。リノベと略すこともある。古い建物を大規模に改修したり、用途を変更したりして資産価値を高めること。例)―済みの賃貸物件。
-
リバースモーゲージ
-
高齢者が、自宅を担保にして金融機関から生活資金を借りる制度。生存中は毎月利息だけを支払い、死亡後、金融機関が住宅を売却して清算する。ただし利用できるのは資産価値の高い住宅に限定される。
-
リバウンド
-
①バスケットボールなどの球技で、シュートが成功せずボールが跳ね返ること。②薬剤の投与を中止した際、急激に症状が悪化すること。反跳現象。③ダイエットの中止や中断で一度減った体重が再び増えてしまうこと。
-
リブート
-
①コンピュータの電源を一度切り、起動し直すこと。リスタートともいう。②過去に製作された同名映画の主要な人物設定は変えずに、出演者を一新したり、新しい解釈を加えたりして製作すること。
-
リプライ
-
返事をする、答える。とくに電子メールで受信したメッセージなどに返信することを指す。リプと略すこともある。例)上司にメールで仕事の報告をしたのに、―がなくて不安だ。
-
リフレイン
-
①短歌や俳句などの韻文で、同じ句を繰り返すこと。畳句。②音楽で、前節の旋律を繰り返すことで強調する手法。フランス語でルフランという。例)人気曲の歌詞と旋律が頭のなかで―している。
-
リベンジポルノ
-
報復、仕返しを意味するリベンジとポルノグラフィーを合わせた造語。別れた配偶者や恋人に対する嫌がらせとして、相手の下着姿や裸などの私的な画像、動画をインターネット上に勝手に公開すること。また公開されたデータそのものも指す。
-
リマインダー
-
メモや助言。予定を忘れないように、設定しておいた時刻に電子メールなどで通知する機能やサービスのこと。
-
リモート
-
遠隔。他の語と組み合わせて使われることが多い。
―コントロール
遠隔操作。
―ワーク
遠隔勤務。インターネットを利用して、会社から離れた場所で仕事をする勤務形態のことで、2020年には、新型コロナの感染症対策として導入する企業が増えた。
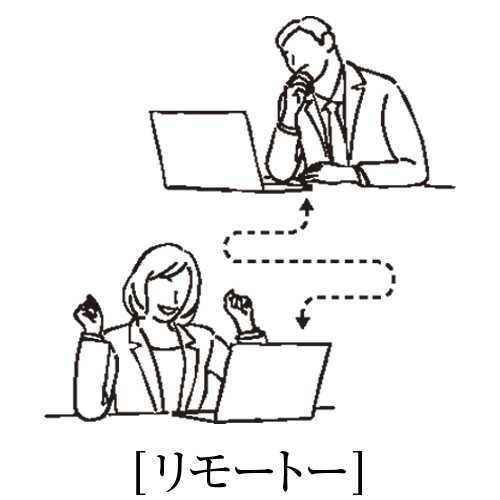
-
リユース
-
一度使用したものを捨てずに何度も再使用すること。古着や中古品を譲渡・売買したり、使用済みの製品や空き容器などを生産者が回収して再利用する。
ル
-
ルーティン
-
日課、慣例になっている手順や行動、習慣。例)毎朝の―で散歩をする。
-
ルッキズム
-
容姿の美醜。見た目で人を評価することで、「外見至上主義」とも訳される。
レ
-
レアアース
-
金属資源の一つ。サマリウム、ネオジムなど17種類の希土類元素の総称で、酸化物を多く含むのが特徴。スマホ、パソコン、電気自動車などの製造に欠かせない材料で、日本国内で使うレアアースは中国からの輸入が約6割に上る。
-
レーシック
-
角膜による屈折矯正手術の代表的なもの。角膜表層部を切開して角膜組織にレーザーを照射し、屈折率を調節、変化させることで近視や乱視、遠視を矯正し、視力を改善することができる。
-
レームダック(レイムダック)
-
任期中に影響力を失った政治家を指していう。死に体。直訳すると「足の不自由なアヒル」で、アメリカ発祥の語。債務不履行者、役に立たない人や組織のことも指す。
-
レガシー
-
遺産、語り継がれる業績。IT(情報技術)の分野では、「時代遅れな」の意味で使われることが多い。
-
レジュメ
-
①要約、概要。講演や講義、論文などの内容を簡潔にまとめたもの。②履歴書。
-
レジリエンス
-
英語で回復力、復元力を意味する言葉で、困難な状況にうまく適応すること、また回復する過程をいう。もとは物理学用語だが、精神医学や心理学、生態学などで使われるようになった。新型コロナ感染拡大が続くなかで用いられることも増えた。例)コロナ禍における不安軽減のために―を身に付けたい。
-
レビュー
-
物事を再調査・再検討すること。現在では、批評、評論の意味で使われる。特に、特定の商品や作品などについての評価や感想、意見などを指す。例)アマゾンの―で高評価の商品を選ぶ。
-
レンジ
-
変動、影響の範囲、分布幅。例)あの人は趣味の―が広い。
ロ
-
ローカルルール
-
特定の地域や場所、組織などに適用される規則。
-
ロースクール
-
法科大学院。裁判官、検察官、弁護士など法曹を養成する教育機関。司法制度改革の一環として2005年までに74校が開設。
-
ローリングストック
-
家庭における災害時のための備蓄食品。またはそれらを備蓄する方法。日常生活のなかで缶詰やレトルト食品などを消費しながら常に一定量を備蓄する。それによって災害時にも日常と同じ食品が食べられ、備蓄品の鮮度も保てる。循環備蓄、ローリング備蓄。
-
ロールモデル
-
ロールとは役や役割のことで、具体的な行動や考え方の模範になるような人、自分が手本にしたい人のこと。
-
ローンチ
-
新しい商品を発売したり、サービスを開始すること。例)新製品は4月に―されます。
-
ログイン
-
コンピュータに暗証番号など自分の身元を示す情報を入力して、利用可能な状態にしたり、インターネットに接続したりすること。接続を切ったり、終了したりすることを「ログアウト」という。
-
ロコモ
-
「ロコモティブシンドローム(運動器症候群)」の略。日本整形外科学会が2007年に提唱した言葉で、骨、関節、筋肉などの障害によって歩行が困難となり、介護が必要になる状態のことを指す。
-
ロジスティクス
-
経営資源を適切に配置して効率性を高めること。物流では、原材料の仕入れから消費者に届けるまでを効率的に統制すること。戦略的物流。もとは軍隊用語で兵站を意味し、兵器や兵員、補給物資などを確保して管理、輸送することを指す。転じてビジネス、マーケティングの分野で用いられるようになった。
-
ロジック
-
論理、議論の筋道。
―ツリー
物事を樹形状に分解していく図。問題の原因を解明し、解決策を見つけるために作成される。
-
ロスジェネ
-
①「ロストジェネレーション」の略。バブル経済崩壊後の1993年から2004年頃に高校・大学を卒業して社会人になった世代で、就職氷河期世代とも呼ばれる。非正規雇用労働者やフリーターが多いのが特徴。②アメリカでは、第一次世界大戦を体験した青年作家たちを指す。代表的作家にヘミングウェイがいる。
-
ロックダウン
-
都市封鎖。感染症の拡大防止などのために、人々の外出や移動を制限すること。2020年、新型コロナ対策として、東京都の小池百合子知事が、都市封鎖の可能性に言及したことから注目されるようになった。
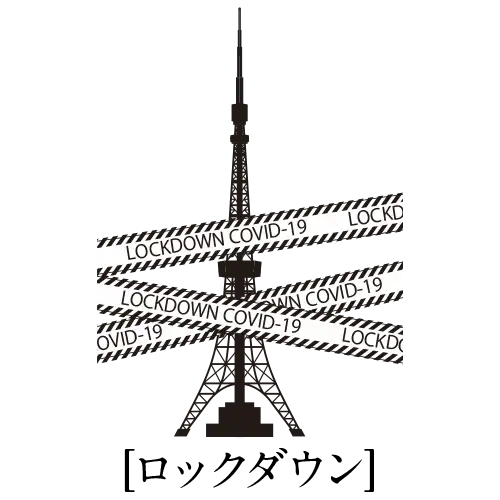
-
ロハス
-
健康的で、自然環境に配慮した生活様式。1990年代後半にアメリカで健康や環境への関心が高い人々によって提唱されたもので、日本では2000年代に入ってから浸透した。
-
ロビー活動
-
特定の団体や個人が、政治的影響を与えることを目的として行なう私的活動。政治家に対して行なわれる陳情や働きかけを指す。アメリカで、ホテルのロビーでくつろぐ大統領に陳述を行なったのがはじまり。ロビイング。ロビー活動を行なう人をロビイストという。