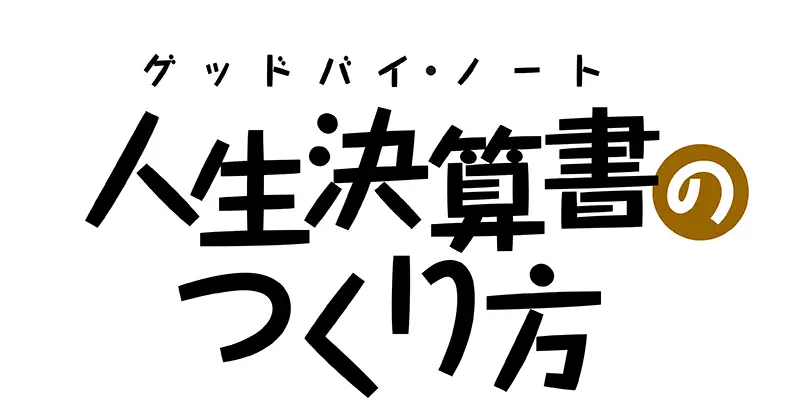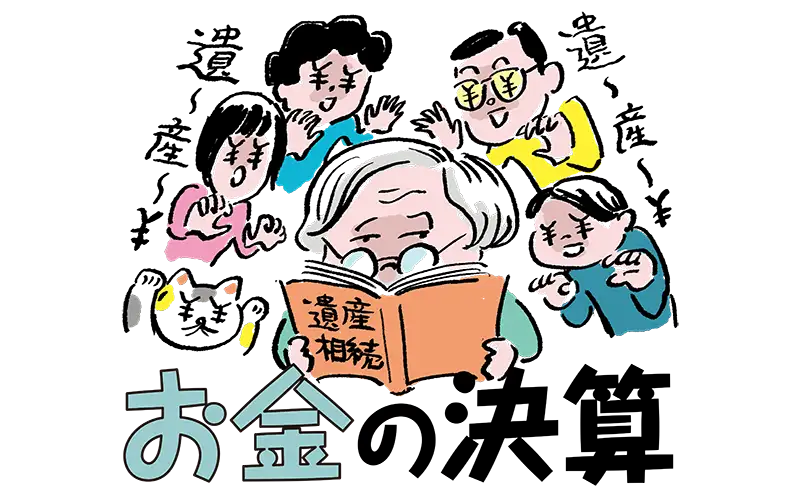「財産なんてわが家にはない」―― その油断が
あなたが亡くなったあと、家族が揉める原因になるかも…。
教えてくれる人
![]()
司法書士法人はやみず総合事務所代表
速水陶冶さん
主に成年後見や家族信託の分野で、高齢者の財産管理に携わっている。著書に『親が認知症になる前に読むお金の本』(サンエイ新書)。
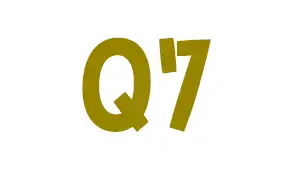
友人が「相続税の節税対策を始めた」と言います。どういった方法がありますか?(60歳・会社員)

代表的な方法は「生前贈与」です。早ければ早いほど効果的なので、元気なうちに始めましょう。
Q3で説明した通り、法定相続人が2人の場合、4200万円以上の財産があれば相続税は発生します。もし発生するとわかった時は、すぐに節税対策を始めることをおすすめします。1日でも早く始めることで、相続税による家族への負担を減らすことができるからです。
節税対策の方法は大きく分けて3つあります。
1つめは「生前贈与で財産そのものを減らす」方法です。
生前贈与の王道は「暦年贈与」です。暦年贈与とは、1年間に贈与する金額が110万円以下であれば、贈与税がかからない制度を利用すること。しかも法定相続人だけでなく、長男の妻や孫にも使うことができます。
その際、暦年贈与した証拠として「贈与契約書」を作成しておきましょう。契約書といっても、紙に贈与の意向と、贈与者と受贈者が署名捺印するだけで結構です。作成しておかないと、例えば娘の名義の口座をつくって、そこにお金を振り込んでも、税務署に「名義だけ娘が貸しただけ」とみなされ、その分に相続税が発生します。
毎年違う金額を贈与することも大切です。毎年きっちり110万円を贈与すると「一定額を贈与するつもりだった」と判断され、贈与した金額すべてに贈与税がかかる可能性があります。念のため、贈与時期も毎年変えましょう。
また、相続開始前3年以内の贈与は、相続税の対象になります。早く始めることの大切さがおわかりでしょう。高齢者や財産が多い人は暦年贈与にとらわれず、「住宅取得等資金の贈与」「教育資金の一括贈与」など(下部【その1】参照)も検討してください。
生命保険は節税対策にも有効
節税対策の2つめの方法は「相続財産の価値を下げる」ことです。
亡くなった人が居住用に使っていた土地の評価額を80%減額できる「小規模宅地等の特例」という制度があります。
この特例が使えるのは、以下のいずれかが土地を相続した場合に限ります。
- 配偶者
- 相続する前から同居していた親族(相続後も住み続ける必要がある)
- 過去3年間持ち家に住んだことがない親族
限度面積は330㎡です。例えば330㎡以内の土地で評価額が6000万円の場合、1200万円だけが課税対象となります。
限度面積や減額割合は異なりますが、会社やアパート経営など事業用の土地にも、この特例は適用されます。
3つめの節税対策は「非課税控除を活用する」方法です。
代表的な例が生命保険です。相続人が受け取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人の数」までは税金がかかりません。
仮に、夫がもしもの時のために生命保険に入っていたとします。法定相続人が、配偶者である妻と子ども2人の計3人であれば、1500万円まで相続税がかからないということになります。
同じ1500万円を現金で遺すよりも節税になりますから、相続税対策という観点で生命保険の見直しも考えてみましょう。
相続税の節税対策3つの方法

【その1】生前贈与で財産そのものを減らす
贈与のさまざまな非課税制度を活用しましょう。元気なうちに子どもや孫に贈与することで、相続の時に引き継ぐ財産を減らすことができます。
| 暦年贈与 | 1年間に110万円以下で贈与すれば、贈与税がかからない。ただし、贈与契約書を作成することを忘れずに。 |
|---|---|
| 住宅取得等資金の贈与 | 20歳以上の子どもや孫に対し、マイホームの購入・建築資金として、一定額(購入時期や住宅形態によって異なる)が非課税となる。 |
| 教育資金の一括贈与 | 30歳未満の子どもや孫に、教育資金として一括で贈与すると最大1500万円までが非課税となる。 |
※ほかにも「結婚・子育て資金の一括贈与」「特定障害者に対する贈与」などが非課税対象となる。
【その2】相続財産の価値を下げる
●小規模宅地等の特例
亡くなった人の自宅の土地の評価額を下げることができます。もし亡くなった人が老人ホームにいた場合でも「介護が必要なために入居したこと」「自宅を誰かに貸していなかったこと」がわかれば、特例の対象となります。
| 限度面積 | 330㎡ |
|---|---|
| 減額割合 | 80% |
| 特例を受けられる相続者 |
|
※会社やアパート経営など事業用の土地にも、この特例は適用される(限度面積や減額割合は異なる)。
【その3】非課税控除を活用する
●生命保険金の非課税枠
被相続人が所有していた財産として引き継がれたのではなく、亡くなったことがきっかけで相続人のものになった生命保険金などの財産は、税務上は「相続した」とみなされます。ただし、一定額まで非課税となります。
| 対象 | 亡くなった人にかかっていた生命保険金を受け取った相続人 |
|---|---|
| 内容 | 「500万円×法定相続人の数」までが非課税となる。相続税対策のための生命保険は、相続発生時に必ず支払われる「終身保険」が適している。 |
※「死亡退職金」も同様の金額が非課税となる。