戦後78回目の8月15日──
日本は再び戦争をする国になるのですか。
戦争と平和を考える18人の声
岸田政権は昨年12月、敵基地攻撃能力(反撃能力)を保有することを決めました。攻められないかぎり攻撃をしない「専守防衛」を国是としてきた日本の安全保障政策は、戦後78年のいま大きく変えられようとしています。「戦争と平和を考える」18人の声をお読みください。
私はこう考える

松尾貴史さん
俳優
「戦争が廊下の奥に立ってゐた」。いつの間にか戦争が身近に迫っていたという戦前のこの句の恐怖がいま、増大しています。
この7月、長崎県の黒田成彦・平戸市長がツイッターで「多数が勝つのが民主主義」と書いて、多くの人から様々な反論が寄せられていました。行政のトップが「多数がすべて」と言ってしまう。そうした民主主義に対する意識が、「今」の惨状を表しているんだと思います。
国レベルにおいても、国会審議を経ずに閣議決定でなんでも決めてしまうことが、安倍晋三内閣の時代から通例になってしまいました。もちろん、多数を占める与党の存在があるからできる振る舞いです。今はもう「またか」と慣れてしまっているところがあるけど、本当は「またか」で済ませてはいけないはずですよね。
マイナンバーカードも同じです。政府は最初、「強制ではない」と言っていたのに、いつの間にか健康保険証の機能を搭載し、現行の保険証を廃止すると打ち出した。実質的な強制です。そして、国会審議抜きの閣議決定やマイナンバーカードの強制などを進めている国会議員たちが、別の場面では憲法に緊急事態条項を設けようとしています。ナチス・ドイツが国家緊急権を蟻の一穴としてワイマール憲法を骨抜きにしたように、日本国憲法にそんな条項ができたら、将来、憲法と国会は停止させられてしまうかもしれない。「今は緊急事態だ」と権力者が言えば、何でも好き勝手にできるようになる。
また、日本では現在、殺傷能力のある兵器を輸出できるようにしようとしています。日本人が戦争で直接誰かを殺さなくても、その兵器が誰かを殺したら、殺された人の家族は「日本も敵だ」と思うでしょう。
ひとつひとつは無関係な出来事に思えるかもしれません。しかし、あちこちで起きている出来事が全部、戦争の側に向かって同時進行で繋がっているような気がしてなりません。決して飛躍した考えではないと思うんです。太平洋戦争が始まる直前に作られた、俳人・渡辺白泉の「戦争が廊下の奥に立ってゐた」という俳句があります。不気味な句だと思いませんか?
何の変哲もない日常だと思っていたのに、気が付いたら自分の家の一番奥に戦争がいた、というわけです。すごい恐怖感ですよね。戦争が起きた時、当時の人は本当にそう感じたのでしょう。そういう不安が今、僕の中で日々増大しているんです。
まつお・たかし●1960年、兵庫県生まれ。大阪芸術大学芸術学部卒業。テレビやラジオ、舞台、映画、エッセイ、イラスト、折り紙等、幅広い分野で活躍中。政治や社会問題も積極的に発信している。著書に『人は違和感が9割』(毎日新聞出版)など。
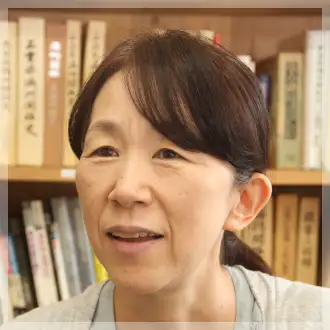
三沢亜紀さん
満蒙開拓平和記念館事務局長
満州国崩壊による逃避行や集団自決、難民生活、帰国後の苦難……館の扉を開けると、本当の戦争が見えます。
戦前、国策によって多くの日本人が旧満州(中国東北部)に渡り、入植しました。2013年に開館した「満蒙開拓平和記念館」はその資料を収集展示し、後世に伝える唯一の博物館です。長野県南部に立地したのは、長野県が全国最多の開拓民を送り出したからです。入植時のプロパガンダ、満州国崩壊による逃避行や集団自決、難民生活、シベリアへの連行と抑留、帰国後の苦難……。日本に戻れず、中国残留孤児になった人たちもいます。館では、そうした国策の負の歴史を目の当たりにできます。
開館前、地元では「開拓団を出すと決めた村長たちを責めるようなことをするな」という声がありました。開拓団員だったという体験を隠し続け、恐る恐る電話をしてきた方もいる。子どものとき満州での集団自決を生き残った兵庫県の人も来ました。その方は「中国の難民収容所にいるときに励ましてもらった」という長野県の元開拓団員とここで再会しました。館は満蒙開拓の歴史を学ぶだけでなく、当事者が思いを吐き出したり、人間らしく死ぬことができなかった身内や知人を弔ったりする場にもなっているのです。
館の運営は、主張ではなく歴史から真摯に学ぶというスタンスです。「アベ政治を許さない」という言葉がありましたが、安倍さんの政治を「許す」人にも来てほしい。だから「日本の悪いところばかり見せている」と怒って帰る人もいれば、「もっと国の責任を追及すべきだ」という人もいます。
「日本人がひどい目に遭った」という扉を開けると、土地を収奪された中国人の痛み、送り出した側の日本人が背負ってきた痛み、さらに残留孤児・残留婦人の問題などが見える。「日本がアジアでどういう戦争をしたのか」に目が向くきっかけにもなる。その視点があるかないかで、今の中国や韓国との関係も変わってくるでしょう。
来館する子どもたちには「『なぜ』を持ってきて」とお願いしています。すると「満蒙開拓を進めていなかったら、日本はどうなっていたと思いますか?」「戦後、国は開拓団の人たちに謝罪や補償をしたんですか?」と鋭い質問が出てきます。単に「戦争はダメだ」ではなく、いろんな立場から国や社会、政治のあり方を考える。それが平和を守ることにつながると思います。
みさわ・あき●1967年、広島県生まれ。93年、長野県飯田市へ移り、地元ケーブルテレビ局で番組制作に携わる。2009年12月に満蒙開拓平和記念館事業準備会の事務局員、その後、事務局長。13年4月の開館後は、同館の事務局長。

一ノ瀬俊也さん
埼玉大学教授
日本の平和主義は社会の地下に深く根を張っています。そう簡単に「新しい戦前」にはならないでしょう。
1945年生まれのタレントのタモリさんが昨年末、テレビ番組で2023年はどのような年になりそうかと質問され、「新しい戦前になるんじゃないでしょうか」と答えて以降、「新しい戦前」が取り沙汰されてきました。では、今の社会は「新しい戦前」なのでしょうか?
「かつての戦前」は不景気や生活苦、漠然とした将来不安などに覆われていました。そして外敵をつくって煽ったり、それを叩いて溜飲を下げたり。例えば、1930年代には、大陸での日中の軍事的緊張を背景として、「暴支膺懲」(ぼうしようちょう)、すなわち「暴戻」(乱暴)な中国を懲らしめろという意味のスローガンが瞬く間に世間に溢れました。メディアが煽り、民衆が熱狂したのです。小学生が「兵隊さん、悪い支那人をやっつけてください」といった作文を普通に書くようになっていました。
いま、SNSなどのネット空間では「中国といかに戦うか」「北朝鮮に先制攻撃を」といった書き込みが溢れています。思慮深くもなく、軽々しく外国や外国人を叩いていく様子は当時と似ているように見えるかもしれません。しかし、よく言われるようにSNSなどのネット空間では自分に近い意見が自動的に表示されるアルゴリズムが機能しており、自分の見ているものは必ずしも社会を広く俯瞰したものではありません。
社会風潮という観点から言えば、戦前と現代は相当に違うというのが私の見解です。例えば、1980年代から続く「世界価値観調査」には定番の「あなたは国のために戦いますか」という設問がありますが、最新調査では日本の「戦う」は13.2%です。調査対象79ヵ国中、ダントツの最下位。憲法9条についても改正を急ぎたい政治家や論者はいますが、国民の議論は全く盛り上がっていません(ただし、そのことが沖縄の基地問題に対する本土の無関心につながっているのも事実です)。
岸田政権が進める防衛力増強も実現には大増税が必要ですし、簡単に国民の理解が得られるかどうか。自衛隊員が常に定員割れという問題もあります。徴兵制導入の可能性も指摘されていますが、経済的に困窮した若者に軍務を事実上強制する「経済的徴兵制」の問題はあるにせよ、深刻な少子化で実現は困難でしょう。つまり、日本はそう簡単に戦争できる国になっていないわけです。
憲法によって根付いた日本の平和主義は、社会の地下に深く根を張っています。いま必要なのは「新しい戦前」という言葉に過剰に反応して「それにどう備えるか」といった議論に進むことではなく、当時と現代の違いを史実に基づいて見極め、歴史に学ぶことだと思います。
いちのせ・としや●1971年、福岡県生まれ。国立民族博物館助教などを経て、2016年から埼玉大学教養学部教授。専門は日本近現代史、とくに軍事史・社会史。『銃後の社会史』(吉川弘文館)、『特攻隊員の現実(リアル)』(講談社現代新書)、『軍隊マニュアルで読む日本近現代史 日本人はこうして戦場へ行った』(朝日文庫)など著書多数。
