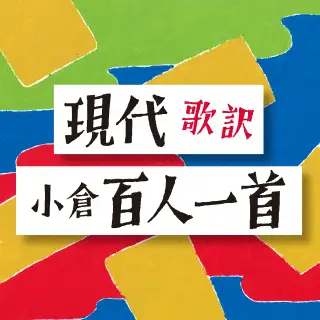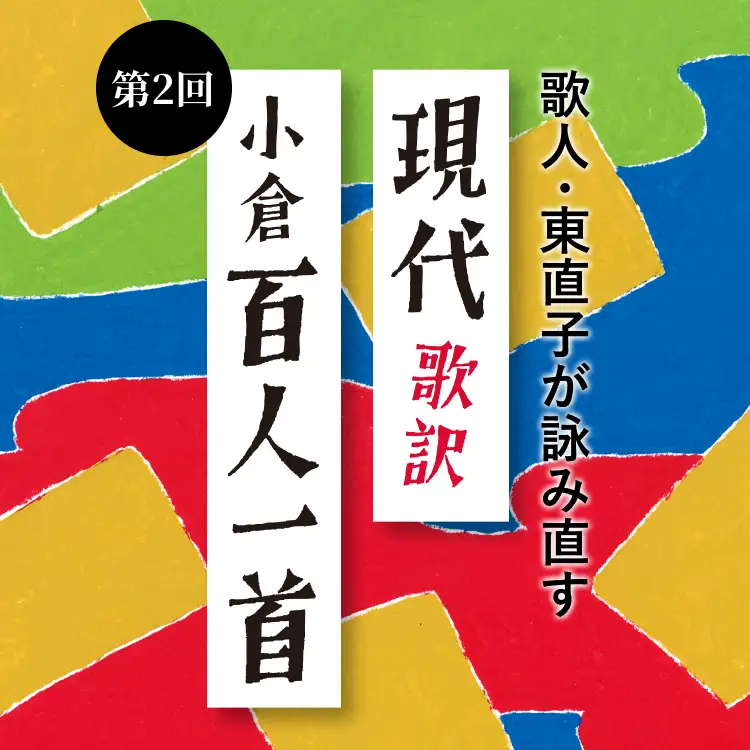
第2回
漫画や映画の影響で子どもたちにも人気の『小倉百人一首』を、歌人・作家の東直子さんに毎回5首ずつ、現代語で詠み直していただきます。第2回は、中納言兼輔・壬生忠岑・紀友則・紀貫之・右近の5首。深まる秋の夜長にお楽しみください。

東直子さん
ひがし・なおこ/歌人、作家。1963年、広島県生まれ。96年歌壇賞受賞。2016年『いとの森の家』で第31回坪田謙治文学賞受賞。歌集に『春原さんのリコーダー』(ちくま文庫)、歌書に『短歌の時間』(春陽堂書店)ほか多数。
URL:http://www.ne.jp/asahi/tanka/naoq/
みかの原わきて流るる
いづみ川いつ見きとてか
恋しかるらむ
中納言兼輔
みかの原わけて流れる泉川
いつからこんなに恋しいのだろう
「わきて」は「湧きて」と「分きて」の掛詞。「湧き」「流るる」「川」は縁語。上の句が「いつ見」を導くための序詞となっている。隅々まで技巧を凝らした歌なのだ。作者は賀茂川堤の邸宅に住み、堤中納言と呼ばれた。「みかの原」は、「三日原」「瓶原」などと書き、京都府の木津川が流れる地域にあたる。
有明のつれなく見えし
別れより暁ばかり
憂きものはなし
壬生忠岑
有明の月のつれない別れから
夜明けがずっと悲しいのです
夜が明けても空に月が残っている。夜と朝の間の時間は、一緒に夜を過ごした人と別れなければいけないときである。つれないなあ(無情だなあ)と月を恨んでしまうのは、相手への未練のあらわれなのである。辛い想いをしたときの風景が胸に残り、同じような風景を見た時にその辛さが蘇る。普遍的な心境である。
ひさかたの光のどけき
春の日にしづ心なく
花の散るらむ
紀友則
天の光のどかにそそぐ春の日に
そぞろごころに花は散りゆく
「ひさかたの」は「光」に掛かる枕詞。「空」や「日」「雲」などにも掛かり、自ずとのびやかな空のイメージを連れてくる。春の光があふれるしずかな世界に、はらはらと散っていく桜の花を惜しんでいる。「ひさかた」「光」「春」「花」と、四句目以外はハ行音で始まり、それらを「の」の音が結びつけ、愛唱性のある韻律が生まれている。
人はいさ
心も知らずふるさとは
花ぞ昔の香ににほひける
紀貫之
人の心はわからないけど懐かしい
ここに変わらぬ梅の香におう
「ふるさと」は「古いなじみの家」という意味。人の心は変わるけれど、花は毎年不変の香りを放つ。アイロニカルな視点も入っているこの歌の作者は紀貫之。『古今和歌集』の中心的撰者で『土佐日記』の作者でもある。詞書に「梅の花を折りて詠める」という文言があるので、この歌での「花」は、梅なのである。
忘らるる
身をば思はず誓ひてし
人の命の惜しくもあるかな
右近
忘れられても愛を誓った君だもの
そのお命を案じています
自分のことをあなたが忘れてしまっても、あなたの命はなによりも惜しい。切ない片思いとも、執念深い未練ともとれる奥深い歌である。一方的な熱い感情は、今もこの世に遍在するリアルな思いでもある。この歌の「身」は、自分自身のことを指し、「人」は恋しい相手のこと。
出典
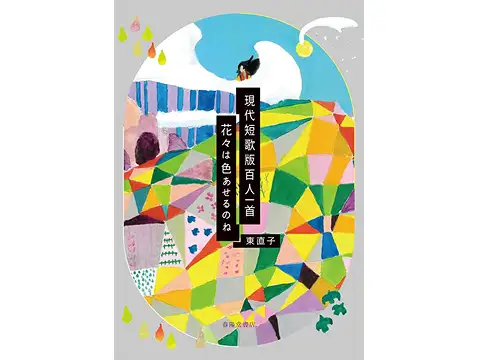
『現代短歌版百人一首 花々は色あせるのね』
東直子著 春陽堂書店