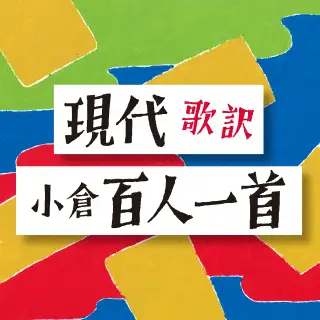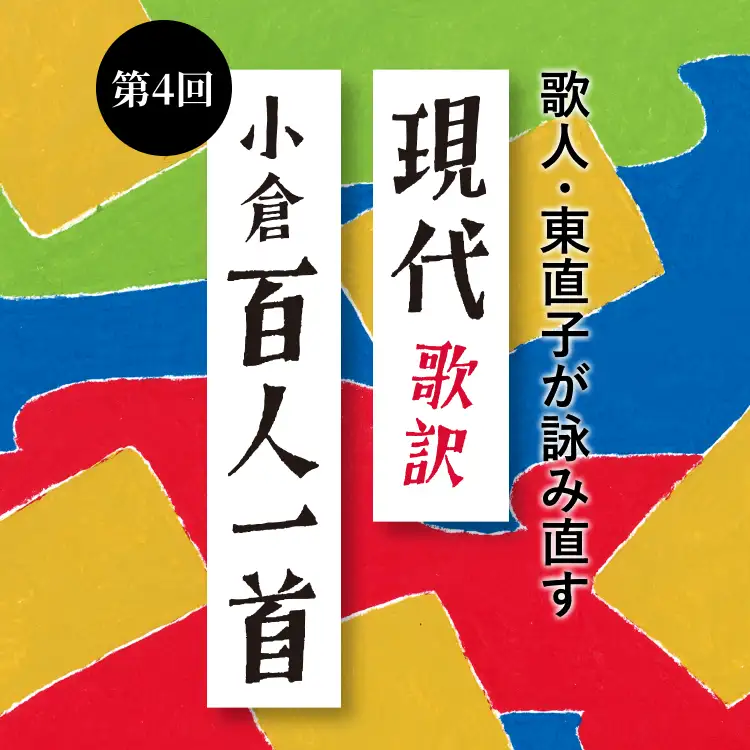
第4回
歌人・作家の東直子さんに毎回5首ずつ、現代語で詠み直していただいてきた『小倉百人一首』は今回で最終回。第4回は、法性寺入道前関白太政大臣、崇徳院・西行法師・鎌倉右大臣・入道前太政大臣の5首。東さんの感性で紡ぎ出された現代語訳の数々は、東さんの著書『現代短歌版百人一首 花々は色あせるのね』(春陽堂書店)でも詳しくお読みいただけます。ぜひご一読ください。

東直子さん
ひがし・なおこ/歌人、作家。1963年、広島県生まれ。96年歌壇賞受賞。2016年『いとの森の家』で第31回坪田謙治文学賞受賞。歌集に『春原さんのリコーダー』(ちくま文庫)、歌書に『短歌の時間』(春陽堂書店)ほか多数。
URL:http://www.ne.jp/asahi/tanka/naoq/
わたの原
漕ぎ出でて見ればひさかたの
雲居にまがふ沖つ白波
法性寺入道前関白太政大臣
海原に漕ぎ出て見れば
はるかなる雲かと思う沖の白波
作者は藤原忠通。藤原基俊に恨まれている相手である。保元の乱で藤原氏の頂点に立った。この歌は、保元の乱の前の崇徳院在位中の歌会で「海上遠望」の題で詠まれたもの。空の雲と白波が一体化する雄大なイメージが清々しい。
瀬をはやみ
岩にせかるる滝川の
われても末に逢はむとぞ思ふ
崇徳院
滝川の岩に砕けてわかれても
いつかはきっとまた逢いましょう
川の流れにこと寄せて、今は別れてもいつか一緒になろうという、情熱的で一途な恋を思わせる。しかし、出生から流刑地(讃岐)での死まで、悲劇的な作者の人生に鑑みると再起を切望する怨念がこもっているようでもある。讃岐に流されたあとのおどろおどろしい伝説が残されている。
嘆けとて
月やはものを思はする
かこち顔なるわが涙かな
西行法師
悲しめと月が言うのか(そうじゃない)
月にかこつけ流れる涙
「やは」は反語なので、否定の意味になる。月を擬人化し、自己を客観化した。作者は、佐藤義清(さとうのりきよ)という名前の北面の武士だったが、妻子を捨てて二十三歳で出家し、諸国を遍歴、月を愛し、花を愛し、命を思い、様々な心もようを率直に詠み、多くの名歌を残した。
世の中は
つねにもがもな渚漕ぐ
あまの小舟の綱手かなしも
鎌倉右大臣
世の中は変わらなければいいのにな
漁師の小舟が引かれていくよ
「かなし」は「愛しい」という意味。作者は源頼朝と北条政子の子で、鎌倉幕府三代将軍源実朝である。甥の公暁の手にかかり、二十八歳で亡くなった。将軍の息子として政治に従事する一方で、定家に歌を学んだ。不条理な殺され方をした実朝の人生や源氏の末路を思うと、変わらぬ世を素朴に望むこの歌が切ない。
花さそふ嵐の庭の
雪ならでふりゆくものは
わが身なりけり
入道前太政大臣
花の降る嵐の庭の花の雪
ふるびゆくのは私のからだ
桜の花が散って庭に雪が降っているようだ、という雅な風景を詠みつつ、自分の老いと結びつけている。作者の藤原公経は太政大臣にまでのぼりつめたが、永遠に権勢をふるうことも、生き続けることもできないと自覚していた。「ふり」は、「花」と「雪」の縁語である「降り」「古り」を掛けている。
出典
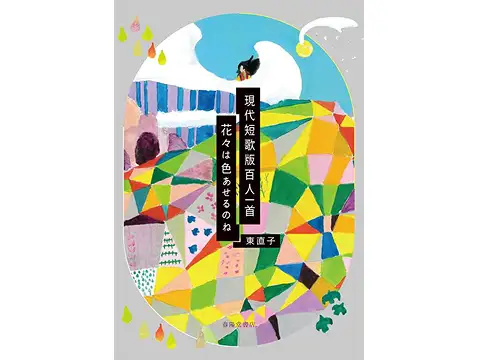
『現代短歌版百人一首 花々は色あせるのね』
東直子著 春陽堂書店