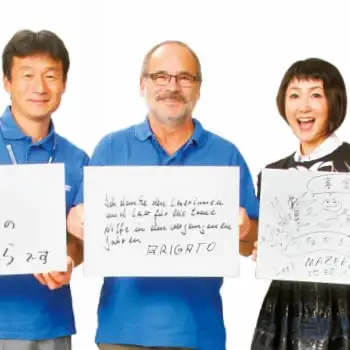紛争地からドイツ平和村へやって来る子どもたちに1口2,000円のお年玉を。
「ドイツ国際平和村」は、自国で十分な治療を受けられない子どもたちをドイツに連れてきて治療し、
治ったら母国へ帰す「援助飛行」という活動を半世紀にわたり続けています。
平和村の活動内容とこれまでの読者カンパについては、下記の通販生活2025年新春号の記事をご覧ください。

骨髄炎の治療のため、2024年11月の援助飛行でドイツに向かうツバイダちゃん(2歳)。
同じく治療のため渡独する女の子に抱かれてチャーター機に向かう。(写真/André Hirtz)
「ドイツ国際平和村」は、自国で十分な治療を受けられない子どもたちをドイツに連れてきて治療し、治ったら母国へ帰す「援助飛行」という活動を半世紀にわたり続けています。
米軍が撤退し3年以上が経つアフガニスタン。タリバン政権下、国際社会からの支援がなくなり、食糧危機はさらに悪化。栄養不足によって未熟児や発育不全の子どもが増えています。
こうした状況を受けて、平和村では新しい取組みが始まっています。その様子を、アフガニスタン在住のジャーナリスト・安井浩美さんが取材しました。
「通販生活」編集部
困窮するアフガニスタンの現在

アフガニスタンで、一人でも多くの子どもが生き延びるためには平和村の支援が不可欠です。
写真・文 安井浩美(ジャーナリスト)
安井浩美さん
やすい・ひろみ/1963年、大阪府生まれ。2001年にアフガニスタンに移住。共同通信社カブール通信員として働くかたわら、現地の女性や子どもの支援活動に取り組む。
2024年11月、首都カブールにあるアタトゥルク病院。栄養失調患者のための30床ほどの病棟があり、生後間もない乳児から5歳未満の子どもが入院している。ほとんどが地方からの患者で、病院到着時にはすでに重篤で入院後1~2日で死亡する子も多く、そのほとんどが1歳未満の乳児だ。
タリバン政権以降、100万人以上のアフガン人が国外退避し、国際社会の支援も激減した。そのため失職する国民も多く、普通に3度の食事がとれていた中間層の人々が貧困層(1人が1日1ドル以下で生活する層)へと転落するケースも少なくない。

カブール市中では、戦争や病気などで夫を亡くし、物売りに出る女性が増えている。
栄養不足で先天異常の乳児が増加。
未熟児で生まれ、現在入院中のハシナちゃん(7ヵ月)。体重は平均の半分強の約5キロ。数日前から下痢と嘔吐を繰り返し、入院後は昏睡状態に陥った。母親のナシマさん(20歳)は「夫の実家は農家で現金収入が少なく、妊娠中も十分な栄養がとれなかった」と話した。一緒にいた義父のバイジャンさん(72歳)は、「1ヵ月に1度も肉を食べる機会がない」と半ば開き直って自身の不甲斐なさを嘆く。ほとんどの貧困層の人々は、ナンと甘いお茶で空腹を満たしているのが実情だ。

入院したハシナちゃんと寄り添う母親のナシマさん。
アタトゥルク病院には、24年3月から9月の半年間で377人に及ぶ1歳未満の栄養失調患者が訪れ、うち2割が死亡。1ヵ月未満の患者12人が死亡した月もあった。
「タリバン政権以降の経済破綻で人々は職に就けず、みな現金がない。そのため妊娠中の母親もお腹の子も栄養不足に陥る。食事の重要性を知らない母親も少なくない。さらには、働き手もいないのに子どもを産み続ける。未熟児で産まれると心疾患など先天異常をもつ確率も高くなる」とマリアム・ジャボール医師は乳児死亡の多さの原因を解く。
この国では、約7%の子どもが先天的疾患をもって産まれてくる。なかでも先天性心疾患は手術が必要だが、同医師によると1000人以上の子どもたちが手術を待っているという。地方では無医村も多く、先天性心疾患と気づかずに死亡する子どもも少なくない。

カブール郊外のゴスパンダラ地区。元はクリケット場だったが、子どもの墓でいっぱいになった。
子どもたちを蝕む骨髄炎は“貧困の病”。
次に、カブール西部にあるキュアホスピタルを訪ねた。この病院では2023年11月から、平和村による「現地治療プロジェクト」が行なわれている。子どもたちが家族の元で治療を受けられるようにしたいという平和村の支援のもと、同院の設備は十分手術が可能な状況になった。援助飛行によるドイツでの患者受け入れが厳しくなっていることに加え、費用面でも、現地で手術を実施できればさらに多くの子どもが治療を受けられることになる。
その日、手術に立ち会った。不安な表情で手術台に横たわるバスミナちゃん(7歳)。手術台の横には、医療用のトンカチや電動ドリルなどまるで大工道具のような器具が並ぶ。カブール近郊のロガール州出身で貧困家庭に生まれ、骨に細菌が侵入して炎症を起こす骨髄炎を患っている。
バスミナちゃんの体重15キロは日本の3歳児の体重である。痩せすぎていて血管を探すのも一苦労な様子。今回で4度目となる手術では、細菌の侵入で壊死した左脚の大腿骨のおよそ3分の1(約20センチ)を切除する。炎症が進行し手術を受けなければ手遅れになる重篤な状態である。

バスミナちゃんの手術は、現地の医療スタッフとドイツ人医師が行なった。
手術に立ち会ったドイツ人のラルフ医師は、「再び細菌が蝕めば左脚を切断することになる。そうしなければ細菌は血管を通って心臓に達し、命を奪うおそれがある」という。だが、彼女の将来を考えると切断は難しい判断だと心情を打ち明けた。
骨髄炎が〝貧困の病〞といわれるゆえんは、栄養不良が原因となるからである。口腔や尿路、擦過傷の傷口などを介して細菌が骨髄に到達し繁殖、骨が壊死したり破壊されたりする。先進国では、初期であれば抗生物質の服用で細菌を除去できる。
国連によるとアフガニスタンでは5歳未満の約45%に栄養不足からの発育阻害が見られる。そのため子どもたちは細菌と闘うだけの抵抗力を持ち得ない。バスミナちゃんの手術でも、最後の段階まで傷口に抗生剤を投入し入念に消毒がされていた。
貧困が解消されない状況下、一人でも多くの子どもが手術で生き延びられるよう、平和村の支援が不可欠となっている。
平和村の新しい挑戦

ドイツで治療する「援助飛行」とアフガニスタンで手術をする「現地治療」の両輪で、救える子どもを増やします。
ビルギット・シュティフター(ドイツ国際平和村代表)
平和村が活動を行なっているアフガニスタンは、生きるための環境が本当に劣悪で、それは面会する子どもたちの様子からもわかります。タリバン政権になったことや経済的な理由もありますが、地震や洪水、干ばつなど自然災害も大きく影響しています。
「現地治療」は家族と離れずに治療できるのが利点。
こうした状況を受けて平和村では、援助飛行に加えて2つの活動に力を入れるようになりました。まず、これまでもやってきた「物資援助」です。緊急支援要請が来たらすぐに、食料や医療物資などを送り出せる準備をドイツで常に整えています。もう一つは、新しく2023年11月から始めた「現地手術プロジェクト」です。
アフガニスタンで子どもと面会し、ドイツに連れてくるほど複雑な治療が必要でない場合は、現地の病院で手術を行なえるシステムを構築しました。何よりも、渡独によって子どもたちが家族と離れてしまうことがなくなるのが利点です。
具体的にはフランスとアメリカがそれぞれ支援する2つの病院と、平和村の現地パートナーである赤新月社、それから平和村の4者で、何人くらいの子どもの受け入れが可能かを話し合っています。当初はドイツからボランティアの医師が加わって手術をしましたが、現地の医師の技術に問題はなく、いまは現地の医師やスタッフだけで子どもたちの治療に当たっています。
これまでに各病院で約20人、合計約40人の手術を行ないました。手術内容は骨髄炎が非常に多く、ほかに形成外科手術、そして今後は泌尿器系の治療も進める予定です。現在、平和村からの支援は、圧倒的に不足している医療用具や抗生物質などの医薬品、資金援助が中心です。
「現地治療」か、あるいは援助飛行による「渡独治療」かを判断する面談には250~300家族ぐらいが来ます。現地治療だけでは不十分で渡独治療が必要と判断されるケースは、骨髄炎などに加えて泌尿器系の疾患や火傷、先天的な病気など複合的な症状が認められる子どもです。こうした渡独が必要な子どもの人数は1回の援助飛行でおよそ80~100人。そして、今後は同じくらいの人数の子どもが現地で手術を受けられるようにしたいと思っています。
手術には1回およそ1000ドル(約15万円)かかります。病気の度合いにより一人の子どもに対して手術が複数回に及ぶこともあります。援助飛行のチャーター機の費用は往復1機につき25万ユーロ(約4000万円)。治療を待つ子どもはとても多く、現地治療と援助飛行(渡独治療)の両輪でやっていきたいと考えています。
寄附が減っているなか、長年の支援の力を実感します。
一方、援助飛行で迎えた子どもの治療については、以前のように無償で受け入れてくれる病院がかなり減っています。ドイツで最近進んだ病院制度の合理化の影響が大きく、コロナやその後の戦争の影響による経済状況の悪化もあって、平和村には大きな打撃となっています。
こうしたドイツの受け入れ態勢の変化の点からも、現地治療は今後も力を入れたいプロジェクトです。また、読者の皆さんからの支援で平和村内に21年に完成したメディカル・リハビリセンター(平和村手術室)も、平和村独自で行なえる治療体制としてまさに力を発揮しています。23年は70人、24年は85人の手術を行ないました。
平和村も世界情勢を受けて寄附が少しずつ減っていますが、その反面、長年支援してくださっている方、「通販生活」の読者のように定期的な支援の力を強く感じています。日本の支援者の皆さんは直接に子どもたちを見ているわけではないのに、遠く離れたところから応援してくださって、ドイツ人よりも子どもたちのことをよく知ってくださっている。本当に感謝しています。
アフガニスタンでの活動

新たに始まった「現地手術プロジェクト」で骨髄炎の手術を受けるアーマード君(8歳)と医師たち。

援助飛行のための面談にはアフガニスタン全土から多くの家族が集まってくる。

平和村では、現地での取り組みとして他に「養鶏プロジェクト」も開始。写真は、昨年5月に暴風雨と洪水の被害を受けたアフガニスタン北部にあるバグラン州オグレ村。鶏卵による栄養確保を目的に、一家族につき9羽の雌鶏と1羽の雄鶏に加え、餌、水分供給器やケージをこれまでに500世帯に提供している。
平和村の子どもたち

24年11月、帰国直前の51名の子どもたち。短くて1年、長い場合には2年半の治療滞在ののち、家族の元へ帰る。
平和村ではたくさんの日本人スタッフが活躍しています
平和村での集団生活が円滑になるよう
日々、悩みながら答え合わせをしています。
佐藤恵美さん(作業療法士、37歳、京都府出身)
4歳から10歳までの子どもたちが生活する宿舎で働いています。着替え・食事の準備など日常生活のサポートのほか、自由時間に少人数のグループ活動を行なっています。
運動が苦手、落ち着きがない、友達関係が苦手など、子どもたちの性格はさまざま。平和村での集団生活が円滑になるよう日々、平等に接することや物事の善悪の判断など、国や文化・個々人の違いを考慮し、子どもたちと悩みながら答え合わせをしています。自分の中にある正しさを疑うこと、それが他者を理解する上で必要なことだと子どもたちから教わりました。

子どもたちの施設で遊びを見守る。
残念ながら、すべての子どもたちが帰国後、就学できるわけではありません。しかし、もしコミュニティで良好な人間関係を築くことができれば、虐げられたり争ったりすることなく優しい世界をつくれる。そう信じてこれからも一人ひとりと大切に向き合っていきたいと思っています。

担当するビビアイーシャちゃん(5歳)、タティアナちゃん(4歳)たちと、粘土を使って集中力や手先の器用さを高めるグループ活動の様子。
広島で生まれ育った人間として、私にできる
平和貢献のかたちを模索していきます。
三戸彩萌さん(24年11月からボランティア、21歳、広島県出身)
平和村と私をつないでくれたのは、中学3年生の時に手にとった一冊の本です。紛争、地雷、医療援助……。当時の私には馴染みのない言葉が並ぶ文章の先に、目を背けたくなるような世界の現実を、そして平和村の存在を知りました。
その後、私は平和村につながるたくさんの学びや素敵な方々と出会う機会をいただきました。なかでも昨年6月、代表のシュティフターさんの広島訪問は深く心に刻まれた出来事です。私がインターンとして所属する広島の特定非営利活動法人ANT-Hiroshimaの代表との対談にご一緒したのです。その時初めて、平和村に関わる方々の人柄や平和に対する想い、生き方に直接触れました。

渡独のための荷物をスーツケースに詰め込む。
広島で生まれ育った人間として、被爆4世として、私には何ができるだろうか。大学生になり模索し続けてきた答えが、平和村での活動にあることを確信しました。
いま私が知っているのは、書物や映像、写真に納められた平和村です。これから始まる活動の中で、たくさんの方々が届け、つないでくださった平和村を自分の目で見て、感じて、私にできる平和貢献のかたちを模索していきます。
※編集部注記:三戸さんには渡独前に寄稿していただきました。

平和村に到着、新しい仲間たちと。