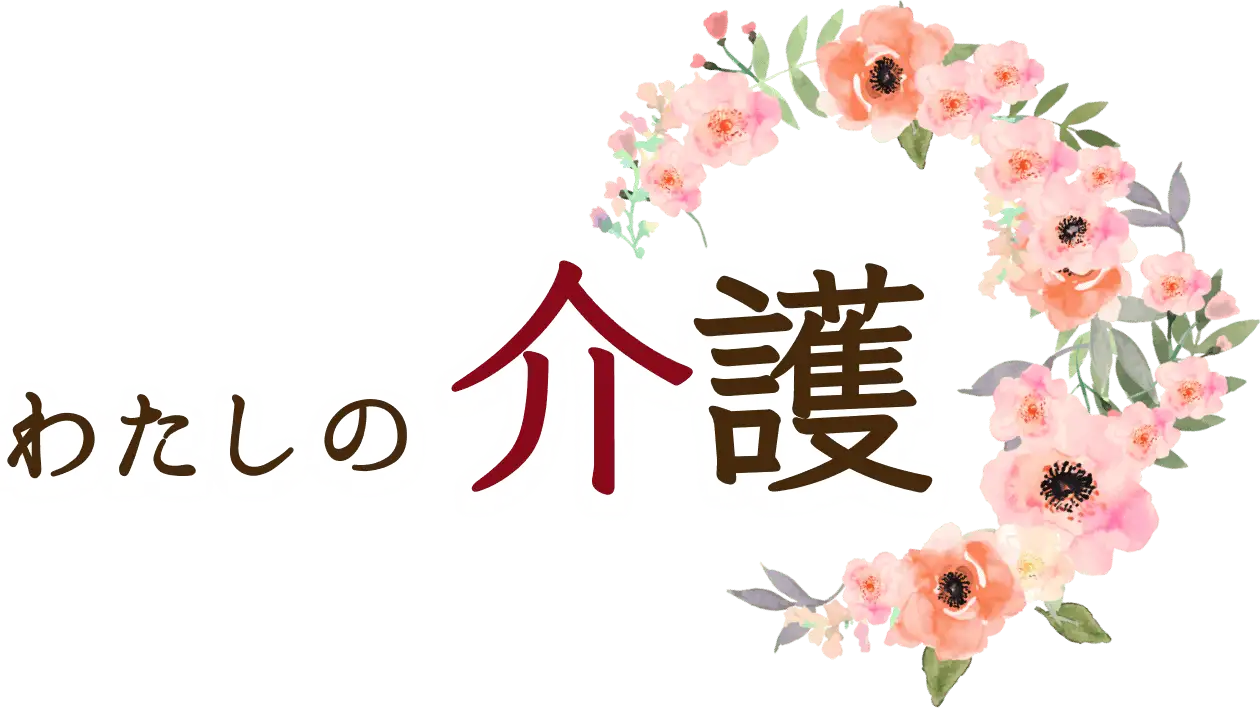元気いっぱいのトークでテレビやラジオで活躍するハリーさんは、仕事もこれから、という27歳の時に最愛の父親がパーキンソン病と認知症を併発。孤独な在宅介護を経て父に寄り添った10年の日々を振り返ります。
わたしの介護年表
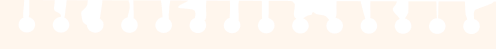
2012年
父73歳
首が傾き姿勢が悪くなり、歩きづらくなる。パーキンソン病を発症。
2013年
父74歳
ガスの消し忘れやトイレに閉じ込められたり、深夜に仕事に出かけようとする。レビー小体型認知症の診断。在宅での生活サポートが始まる。
2014年
父75歳
東京都・区立の「特養」(特別養護老人施設)でデイケアやショートステイを利用する。
2016年
父77歳
そのまま特養に入所。ケアを受けながら、共著やインタビューによる書籍を出版。
2020年
父81歳
コロナ禍による面会制限によって、家族でのケアができなくなる。
2022年
父83歳
誤嚥性肺炎により救急搬送。3週間入院したのち特養に戻り静養。4月17日、家族に見守られ永眠。
尊敬するヒーローであり親友でもあった
父の異変。
世界で一番尊敬する人であり、何でも話せる大親友でもあった父、ヘンリー・スコット・ストークスは、2022年4月に83歳で亡くなりました。
その6月には非公式で「日本外国特派員協会」が父を偲ぶお別れの会を開いてくれました。父の古くからの同僚のみなさんや後輩の外国人ジャーナリストの方々と、父の思い出を語り合いながら、いい時間を過ごしました。亡くなって半年、父を思い出さない日はありません。寂しさはいつも感じていますが、ただ悲しむだけではなく、父の人生を祝福する気持ちも大切だなと思うようになりました。
父は、1964年の東京オリンピックの年、イギリスの経済誌『フィナンシャル・タイムズ』初代東京支局長として来日しました。
1967年にはイギリスの日刊紙『タイムズ』東京支局長、1977年にはアメリカの日刊紙『ニューヨーク・タイムズ』東京・ソウル支局長から、その後はアジア総支局長も務めました。
この間に作家の三島由紀夫さん、実業家の服部一郎さん(セイコーエプソン初代社長)とも親しくしていたようです。韓国の金大中元大統領や北朝鮮の金日成主席にも取材したことがあり、まさに激動の昭和と当時の国際情勢をつぶさに見てきた人でした。
父は、僕にとっては第一線で活躍するジャーナリストであり、無敵のヒーローであり、一家の大黒柱。お互いを「ヘンリー」「ハリー」と呼び合うような、親子の絆を超えた特別な関係でした。

ニューヨーク・タイムズ東京支局長として取材に奔走していた当時、若き日のヘンリーさん。(写真はハリーさん提供)
父の様子が少しおかしいと、最初に気づいたのは母でした。2012年、73歳の頃はまだ、父は元気で仕事をしていましたが、母から「最近、姿勢が悪くなって首が硬直しているみたい。歩き方もぎこちない」と相談されたのです。「Head up! Don't slouch!(頭を上げて! 猫背になるな!)」と、子供の頃からいつも言われてきたのに、どうしたんだろうと心配になり病院で診てもらったところ、パーキンソン病と診断されました。神経系の難病です。
当時、僕は27歳、事務所を移籍したばかりで、朝の情報番組のレギュラー出演やラジオの帯番組もスタートしたところ、仕事をがんばらないといけない時期でした。一人暮らしをやめて実家に戻り家族3人の生活になると、父は一人で立ち上がることにも苦労し、体を思うように動かせないようでした。これらはたしかに、パーキンソン病の特徴的な症状である「振戦(ふるえ)」「固縮(筋肉の緊張)」「寡動・無動(動作の遅さ、表情の硬さ)」「姿勢反射障害(転びやすい)」に当てはまっていました。
そのうち、トイレの鍵を開けることができず中に閉じ込められてしまったり、外出時にガスを消し忘れたり、父らしくない行動を頻繁に起こすようになりました。レビー小体型認知症という診断も受けましたが、実際のところはよくわかりません。家族は、現実を受け止めることができませんでした。「歳なんだし仕方ない、怠けているだけ、ちょっと調子が悪いだけ。大丈夫、なんとかなるでしょう」。
僕自身、「信じたくない」という思いが強くて、根拠もなく楽観的に考えてしまいました。介護施設のお世話になるなんて父から自由を奪い見捨ててしまうようで、父の病気は母と僕だけの秘密にして、家庭内で徹底的にケアしようと決めました。でもそれは家族を追い詰めてしまうことになりました。


歳だから仕方ない、と楽観的に
考えようとしたことが、
家族を追い詰めてしまいました
僕も母も介護の知識はゼロ。認知症の人に対して、否定したり怒ってはダメだと今ならわかりますが、僕は父に何度も「なぜできないの?」「なぜ忘れるの?」「めんどくさがっているの?」と言ってしまいました。あれは言葉による拷問だったと思います。父も混乱したでしょう。症状を悪化させてしまっていたのかもしれません。
着替えをサポートしようと手を貸すと、父は自分のパーソナルスペースを侵されると思って、殴りかかってくることもありました。「手伝っているのになぜ?」と母も僕も怒りました。時には、父に手をあげそうになったことも……。
仕事が大好きだった父は、真夜中にスーツに着替えて出かけようとしたり、徘徊して近所の方に知らせてもらったこともありました。
こうなると目が離せなくなり、日常生活のほとんどでサポートが必要になりました。将来への不安や心配、自分自身の無力さから僕も母もイライラしてしまうし、父は怒られることに過剰に反応しビクビクしてしまうし……。
介護者も時には癒しの時間を持たないとストレスを相手にも自分にもぶつけてしまい、悪循環に陥ってしまうものです。家にいると自分がどうにかなりそうで、友達と夜遊びに出かけたこともありました。でも、彼らはみんな介護とは無縁の生活。相談したり愚痴をこぼすこともできません。現実逃避している自分を責めたりもして、辛く孤独な日々でした。

次回(3月18日公開)に続く
取材・文・編集協力/小泉まみ イラスト/タムラフキコ 撮影/藤田政明 編集協力/株式会社Miyanse
『月刊益軒さん 2022年12月号』(カタログハウス刊)の掲載記事を転載。
-
第1回
介護者も自分の健康を気にかける時間が必要です
篠田節子さん【前編】1月29日公開
-
第2回
介護者も自分の健康を気にかける時間が必要です
篠田節子さん【後編】2月5日公開
-
第3回
精神論では無理。介護が始まる前に家族で話し合っておきたい
ハリー杉山さん【前編】3月11日公開
-
第4回
精神論では無理。介護が始まる前に家族で話し合っておきたい
ハリー杉山さん【後編】3月18日公開
-
第5回
後ろめたさを感じずに介護はプロを頼っていい
安藤優子さん【前編】3月25日公開
-
第6回
後ろめたさを感じずに介護はプロを頼っていい
安藤優子さん【後編】4月1日公開
-
第7回
無理のない役割分担で『きょうだいチーム介護』を実践
岸本葉子さん【前編】4月15日公開
-
第8回
無理のない役割分担で『きょうだいチーム介護』を実践
岸本葉子さん【後編】4月22日公開
-
第9回
元気なうちに延命治療について希望を聞いておくべきです
盛田隆二さん【前編】5月21日公開
-
第10回
元気なうちに延命治療について希望を聞いておくべきです
盛田隆二さん【後編】5月29日公開
-
第11回
「介護はプロとシェアして」という言葉で、罪悪感から解放された
信友直子さん【前編】6月21日公開
-
第12回
「介護はプロとシェアして」という言葉で、罪悪感から解放された
信友直子さん【後編】6月28日公開
-
第13回
一人で抱え込まないようにして介護うつ、介護後うつの予防を
安藤和津さん【前編】7月19日公開
-
第14回
一人で抱え込まないようにして介護うつ、介護後うつの予防を
安藤和津さん【後編】7月26日公開
-
第15回
親子の関係が逆転する「交差地点」をうまく乗り越えるのが大切
綾戸智恵さん【前編】8月23日公開
-
第16回
親子の関係が逆転する「交差地点」をうまく乗り越えるのが大切
綾戸智恵さん【後編】8月29日公開
-
第17回
絶対に一人で抱え込まず専門家の輪の中で介護を
山口恵以子さん【前編】9月26日公開
-
第18回
絶対に一人で抱え込まず専門家の輪の中で介護を
山口恵以子さん【後編】10月2日公開
-
第19回
介護の日々を文章にすることで、辛い気持ちも救われました
伊藤比呂美さん【前編】11月5日公開
-
第20回
介護の日々を文章にすることで、辛い気持ちも救われました
伊藤比呂美さん【後編】11月11日公開
-
第21回
母に手を上げてしまったとき、自宅介護を諦める決心がついた
松浦晋也さん【前編】12月3日公開
-
第22回
母に手を上げてしまったとき、自宅介護を諦める決心がついた
松浦晋也さん【後編】12月12日公開
-
第23回
介護に振り回された7年間は自分の老後を考えるきっかけに
秋川リサさん【前編】1月15日公開
-
第24回
介護に振り回された7年間は自分の老後を考えるきっかけに
秋川リサさん【後編】1月23日公開
-
第25回
本人が納得してくれることを大切に。父と母のダブル介護を乗り越えて
荻野アンナさん【前編】2月10日公開
-
第26回
本人が納得してくれることを大切に。父と母のダブル介護を乗り越えて
荻野アンナさん【後編】2月17日公開
-
第27回
この先を考えれば不安も。まず「今日、明日」で考えています
にしおかすみこさん【前編】3月13日公開
-
第28回
この先を考えれば不安も。まず「今日、明日」で考えています
にしおかすみこさん【後編】3月20日公開
-
第29回
介護のストレスは外に吐き出して解消。「言いふらし介護」をおすすめします
新田恵利さん【前編】4月11日公開
-
第30回
介護のストレスは外に吐き出して解消。「言いふらし介護」をおすすめします
新田恵利さん【後編】4月17日公開
-
第31回
介護には客観的な視点が重要。いいケアマネさんに出会えました
入江喜和さん【前編】5月15日公開
-
第32回
介護には客観的な視点が重要。いいケアマネさんに出会えました
入江喜和さん【後編】5月22日公開
-
第33回
認知症の父と向き合うために哲学が役に立ちました
髙橋秀実さん【前編】6月12日公開
-
第34回
認知症の父と向き合うために哲学が役に立ちました
髙橋秀実さん【後編】6月19日公開