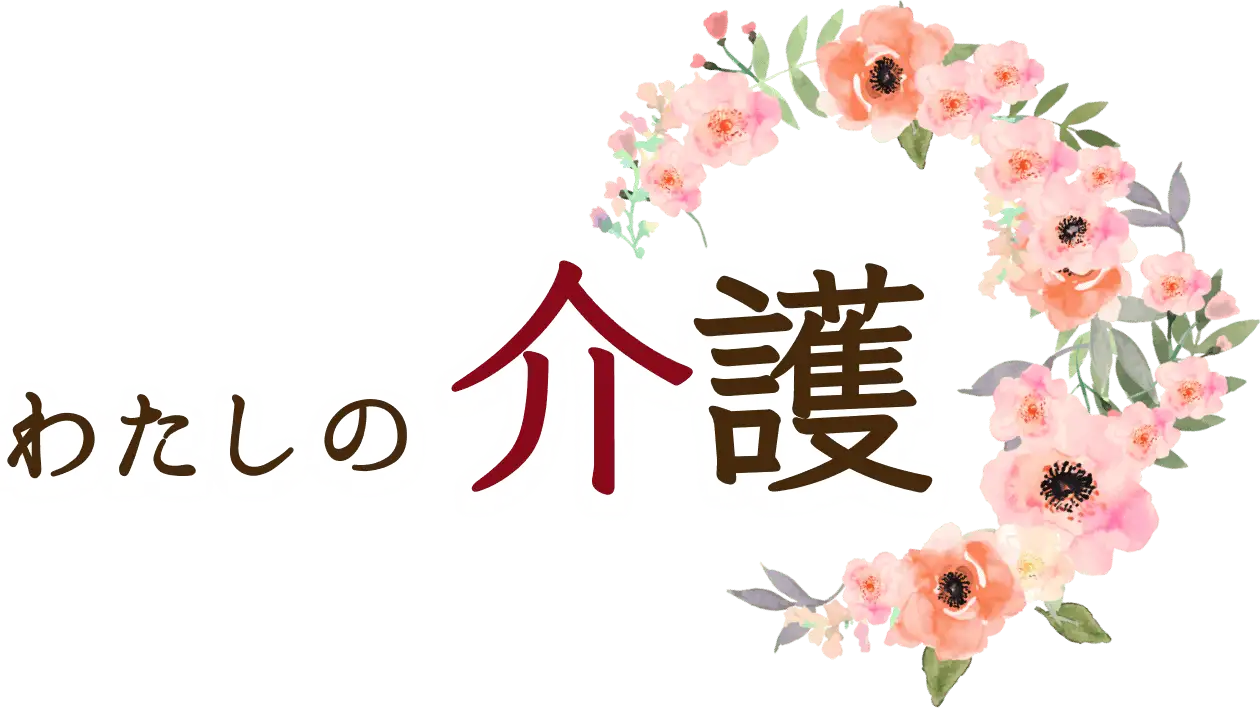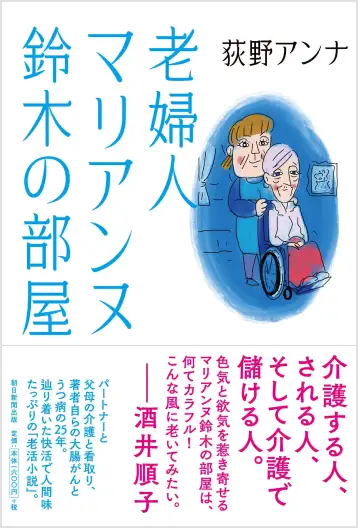作家の荻野アンナさんは、約15年間、父と母を介護しました。その間に自身の大腸がんも発覚し、手術と治療をすることに。できないことが増えてわがままになる両親と、時にはぶつかりながらも、相手の気持ちに寄り添った介護を心がけたと言います。
わたしの介護年表
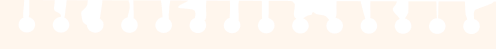
父の介護
2000年
父85歳
悪性リンパ腫で手術入院。続けて、翌年腸閉塞になり手術入院をする。その後5年ほど元気に。
2006年
父91歳
心不全で入院し、リハビリ病院を経て、自宅介護。その後、有料老人ホームへ入居する。
2010年
父95歳
入退院を繰り返すが、老人ホームで4年間過ごす。医師の見立てより半年も長生きし、天寿を全う。
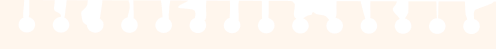
母の介護
2000年
母77歳
バスのドアにぶつけて右腕を骨折。腰椎滑り症で腰が曲がっていて、夫の介護はできない。
2006年
母83歳
ヘルペスで入院。徐々に体調を崩していく。自宅のトイレで動けなくなり、救急車を呼ぶ。
2012年
母89歳
アンナさんが大腸がんになる。要介護4の母と一緒に入院。のちに、母は肺の扁平上皮がんで入院。
2013年
母90歳
退院して家で24時間介護に。家が施設になる。絵の制作は続け、秋に展覧会に出品する。
2015年
母91歳
前年にペースメーカーを入れて、命をつなぐ。1月12日に亡くなる。
※年号・歳の一部は目安です。
2010年に父が亡くなりました。ほぼ老衰です。老人ホームに入ってからも入退院を繰り返しましたが、常にプロに見守ってもらっていたので、寿命は長くなったと思います。在宅介護をしていたら、体調の変化に気が付かなかったでしょう。
2012年に、今度は私が大腸がんになってしまいました。それまで両親のことで病院通いをしていましたが、「自分の病気で病院に行けるなんて、すごく贅沢」という気分です。要介護4になっていた母を自宅に1人置いておけないので、手術をする病院に頼んで母の部屋をとってもらって一緒に入院。病室で仕事をしていると、母が「アンナ、アンナ」と電話をかけてくるので、母の部屋でご飯を食べたり、タバコがやめられない母のために喫える場所まで散歩に付き合ったりと、忙しい入院ライフでした。
この年の年末に母は自宅で転んで病院に行くと、肺の扁平上皮がんが見つかりました。私は抗がん剤治療の真っ最中で、吐き気とめまい、手の痺れなど体調が悪かったのですが、母の治療に付き添いました。体調が限界のときは、待合室のベンチで、目にハンカチをかけて横になることも。母の病室でも、母に体を斜めに寝てもらって、ベッドの足元の空いたスペースで寝るなど、寸暇を惜しんで休みました。その光景を見た看護師さんからは「仲がおよろしいですね」なんて言われました(笑)。

父や母に納得してもらう
しゃべりが上手くなる
母は退院しますが、父とは違い、施設に入るという選択肢はありません。心血を注いで整えてきた自宅は母の作品で、離れたくなかったからです。そうなると、家を施設のようにするしかない。訪問介護、入浴介助など、介護保険で利用できるものは全部使って、家での本格的な24時間介護が始まりました。ヘルパーさんには入院中に病室に来てもらい、母に慣れてもらっていたので、もう嫌だと言いませんでした。
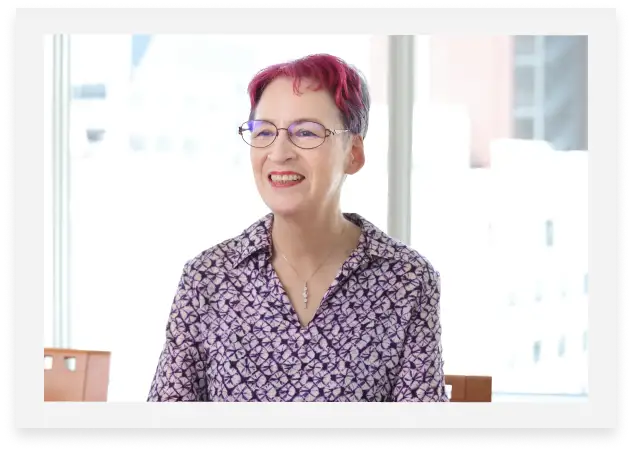

私が大腸がんを発症。
要介護4の母と一緒に病院へ
入院して、手術をしました
母は呼吸を補助するために在宅酸素の装置を使っていました。ただ、酸素を吸入する器具、カニューレをつけるのを嫌がり、「酸素なんて出ていない、無駄だ」と言い張る。そこで、在宅酸素の装置を製造している会社に電話をして、「水の入ったコップにカニューレを入れるとブクブク泡が立つ」と教えてもらいました。それを母にやって見せたら、ようやく納得してくれたのです。
体が弱ってできないことが増え、わがままになる両親を、納得させるしゃべりは、とても上手くなりましたね。父が車椅子に乗るのを嫌がったときも、熱心なキリスト教徒だった父に、当時の教皇様が車椅子だったので「教皇様も車椅子だよ」と説得。さらに「昔は車椅子に乗るほど長生きできなかったよね。車椅子に乗って長生きするのと、乗らずに早く亡くなるのとどっちがいい?」と続け、父に納得してもらいました。
最初からこんな穏やかだったわけではなく、ぶつかることもたくさんありました。でも、介護の色々な経験をし、相手の思いを大切にしようと学習していきました。
今、振り返って一番大変だったなと思うのは、命の決断をしなければいけなかったことでしょうか。母は亡くなる前年に、ペースメーカーを入れる手術をしました。入れないと命が先細りだと医者から言われました。でも母のように認知症の症状がある人は、手術中に動いてしまって失敗もあるとも。迷って決断をし、手術が上手くいって母に言葉が戻ってきました。「今日、生きていて良かったと思った」とつぶやいたときは、ほっとしました。でも、また肺炎になったりして「生きているのが辛い」と言うことも。さらに落ち着くと「死ぬのが怖い」とも嘆きました。限界まで頑張ってもらって良かったのか、逆に辛い思いをさせてしまったのではないか。これは、今でも答えが出ていません。
母は2013年まで絵の制作をし、2015年に亡くなりました。最後の2年ほどは、肺、心臓、肝臓が弱り、入退院を繰り返しながら過ごしました。

両親の介護が始まる少し前、自宅でお客様に撮ってもらいました。2人ともまだ元気でした。
時々、わがままを通して
気持ちを立て直す
介護をする者にとって、介護が生活の100%になると、息が続きません。私の介護は85%くらいだと自分で思いますが、それでも時々爆発します。介護中に、ボクシングを始めました。両親に理不尽なことを言われたりして、もう介護を続けていけないと思ったとき、サンドバッグに気持ちをぶつけてすっきり。自分でも可笑しかったのは、当時のメモを見返すと、「もう限界」と走り書きした横に「高橋別館予約」と書いてあります。あまり遠くない温泉宿を予約していました(笑)。でも、それが大事でした。温泉で気分を変えると、翌日晴れやかに両親の病院に行けます。自分のわがままを通していると思えると、理不尽な状況にも耐えられました。
今、介護中の方にも、道端の花1輪を見るでもいい、ほんの少しでも自分の時間を持ち、擦り切れないようにして欲しいと思います。
取材・文/大橋史子(ペンギン企画室) イラスト/タムラフキコ 撮影/島崎信一 協力/株式会社Miyanse
『月刊益軒さん 2023年10月号』(カタログハウス刊)の掲載記事を転載。
-
第1回
介護者も自分の健康を気にかける時間が必要です
篠田節子さん【前編】1月29日公開
-
第2回
介護者も自分の健康を気にかける時間が必要です
篠田節子さん【後編】2月5日公開
-
第3回
精神論では無理。介護が始まる前に家族で話し合っておきたい
ハリー杉山さん【前編】3月11日公開
-
第4回
精神論では無理。介護が始まる前に家族で話し合っておきたい
ハリー杉山さん【後編】3月18日公開
-
第5回
後ろめたさを感じずに介護はプロを頼っていい
安藤優子さん【前編】3月25日公開
-
第6回
後ろめたさを感じずに介護はプロを頼っていい
安藤優子さん【後編】4月1日公開
-
第7回
無理のない役割分担で『きょうだいチーム介護』を実践
岸本葉子さん【前編】4月15日公開
-
第8回
無理のない役割分担で『きょうだいチーム介護』を実践
岸本葉子さん【後編】4月22日公開
-
第9回
元気なうちに延命治療について希望を聞いておくべきです
盛田隆二さん【前編】5月21日公開
-
第10回
元気なうちに延命治療について希望を聞いておくべきです
盛田隆二さん【後編】5月29日公開
-
第11回
「介護はプロとシェアして」という言葉で、罪悪感から解放された
信友直子さん【前編】6月21日公開
-
第12回
「介護はプロとシェアして」という言葉で、罪悪感から解放された
信友直子さん【後編】6月28日公開
-
第13回
一人で抱え込まないようにして介護うつ、介護後うつの予防を
安藤和津さん【前編】7月19日公開
-
第14回
一人で抱え込まないようにして介護うつ、介護後うつの予防を
安藤和津さん【後編】7月26日公開
-
第15回
親子の関係が逆転する「交差地点」をうまく乗り越えるのが大切
綾戸智恵さん【前編】8月23日公開
-
第16回
親子の関係が逆転する「交差地点」をうまく乗り越えるのが大切
綾戸智恵さん【後編】8月29日公開
-
第17回
絶対に一人で抱え込まず専門家の輪の中で介護を
山口恵以子さん【前編】9月26日公開
-
第18回
絶対に一人で抱え込まず専門家の輪の中で介護を
山口恵以子さん【後編】10月2日公開
-
第19回
介護の日々を文章にすることで、辛い気持ちも救われました
伊藤比呂美さん【前編】11月5日公開
-
第20回
介護の日々を文章にすることで、辛い気持ちも救われました
伊藤比呂美さん【後編】11月11日公開
-
第21回
母に手を上げてしまったとき、自宅介護を諦める決心がついた
松浦晋也さん【前編】12月3日公開
-
第22回
母に手を上げてしまったとき、自宅介護を諦める決心がついた
松浦晋也さん【後編】12月12日公開
-
第23回
介護に振り回された7年間は自分の老後を考えるきっかけに
秋川リサさん【前編】1月15日公開
-
第24回
介護に振り回された7年間は自分の老後を考えるきっかけに
秋川リサさん【後編】1月23日公開
-
第25回
本人が納得してくれることを大切に。父と母のダブル介護を乗り越えて
荻野アンナさん【前編】2月10日公開
-
第26回
本人が納得してくれることを大切に。父と母のダブル介護を乗り越えて
荻野アンナさん【後編】2月17日公開
-
第27回
この先を考えれば不安も。まず「今日、明日」で考えています
にしおかすみこさん【前編】3月13日公開
-
第28回
この先を考えれば不安も。まず「今日、明日」で考えています
にしおかすみこさん【後編】3月20日公開
-
第29回
介護のストレスは外に吐き出して解消。「言いふらし介護」をおすすめします
新田恵利さん【前編】4月11日公開
-
第30回
介護のストレスは外に吐き出して解消。「言いふらし介護」をおすすめします
新田恵利さん【後編】4月17日公開
-
第31回
介護には客観的な視点が重要。いいケアマネさんに出会えました
入江喜和さん【前編】5月15日公開
-
第32回
介護には客観的な視点が重要。いいケアマネさんに出会えました
入江喜和さん【後編】5月22日公開
-
第33回
認知症の父と向き合うために哲学が役に立ちました
髙橋秀実さん【前編】6月12日公開
-
第34回
認知症の父と向き合うために哲学が役に立ちました
髙橋秀実さん【後編】6月19日公開
-
第35回
謎が多すぎる両親を遠距離でお世話と見送りを
姫野カオルコさん【前編】7月17日公開
-
第36回
謎が多すぎる両親を遠距離でお世話と見送りを
姫野カオルコさん【後編】7月24日公開