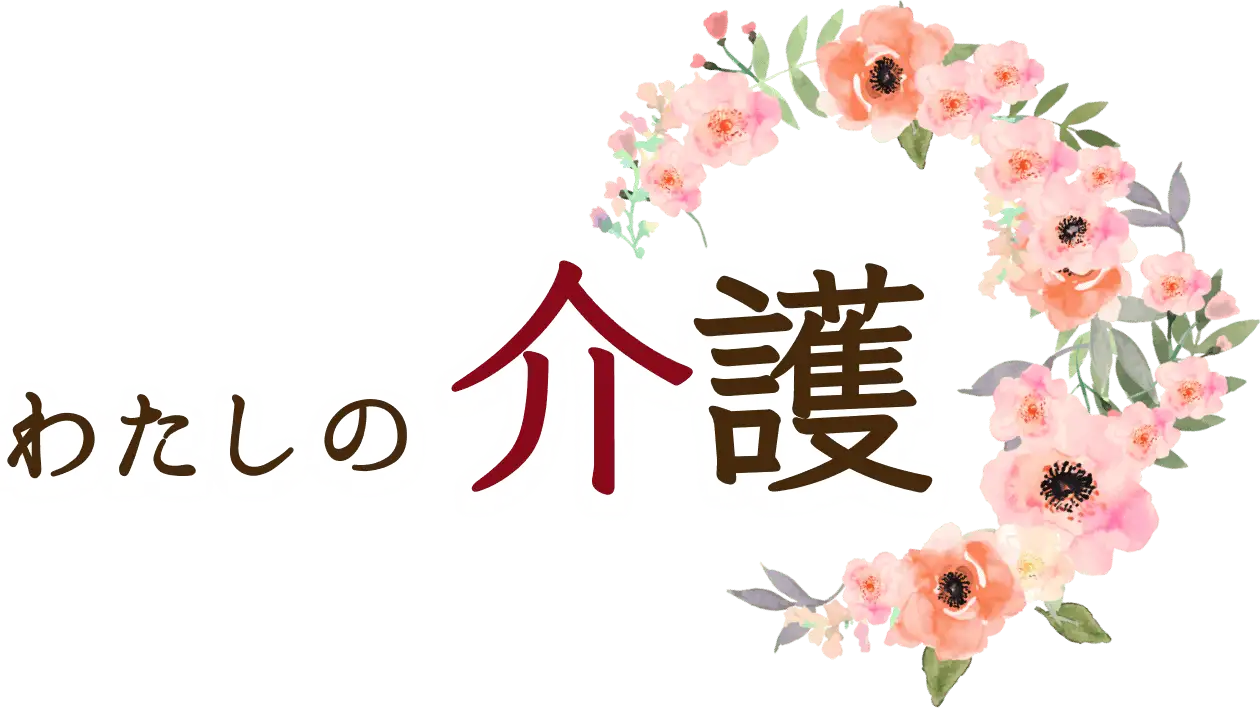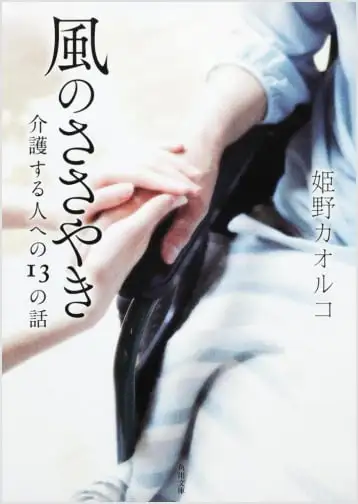作家の姫野さんは20代の頃から、両親と親族のお世話を担ってきました。両親は子どもの頃から理解に苦しむ行動が多く、ずっと分かり合えないままだったそう。大学入学時に家を飛び出し、その後、一緒に暮らすことはなく、東京と滋賀を行き来して見送りました。楽しい思い出が少ない両親のお世話をどのように乗り切ったのか、お話しを聞きました。
わたしの介護年表
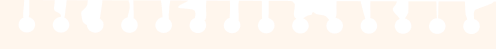
1980年頃~
父60歳頃
父が糖尿病を発症した後、脳梗塞に。母やヘルパーさんで在宅介護。姫野さんは東京から頻繁に帰省して手伝う。78歳で、亡くなる。
1998年頃~
母70代半ば
一人暮らしをしていた母に認知症の症状が出始める。姫野さんは東京から週1回ほど帰省して様子を見る。悪徳セールスで高額な商品を買わされるようになる。
2000年頃~
母70代後半
一人暮らしは難しくなり、母はグループホームに入居。生活になじみ、楽しく過ごす。元気な時はネガティブだったのに、ポジティブで明るい性格に。
2005年頃~
母80代半ば
パーキンソン病が悪化し、施設を転居。窓から琵琶湖の見える特養に入居する。話すこともできなかったが、穏やかに3年ほど過ごして亡くなる。
※年号・歳の一部は目安です。
「もう一人暮らしは無理かな」と思い始めた頃、市役所の福祉課に勤めている友人が「グループホームっていうのがあるよ。その人の残ってる能力を使って、みんなで暮らしている施設だよ」と教えてくれました。当時は今みたいに、要支援でデイサービスを使ってとか、老健があってなど介護情報が知られていないし、制度も整っていない時代です。私もグループホームというものがあることを初めて知りました。
母が訪問販売の人を家に中に入れてしまうのは、「一人で寂しいからなのでは。話す相手がいるグループホームはいいかもしれない」と思い、まずは私だけで見学に行きました。
グループホームは、実家から自転車で5分くらいの場所にある古い日本家屋でした。みんなが集まれる茶の間があって、その他の部屋は改装して3畳ほどの個室になっていました。家庭菜園をしている庭もあって、サザエさんの家みたいで。家庭的な雰囲気が気に入り、次は母を連れて行きました。
父と結婚する前の幸せだった女学校時代に住んでいた家に似ていたようで、「大津で住んでいた家やね」と母も気に入った様子。生活の場が急に変わるのは抵抗があるかなと思い、最初は昼間は家にいて、夜は暖かいグループホームで夕食と就寝という、通いのスタイルに。少しずつ慣らしてから、完全にグループホームに引っ越しました。
母が「(家にある)ピアノを持っていきたい」と言うので、施設にお願いして、置かせてもらうことに。小学生唱歌など同年代の人が好きそうな曲を弾いていたら、入居者や職員さんの間で「〇〇さんまた弾いて~」とあちこちから声のかかる人気者になったのです。

絵を描くのは昔からすごく下手で、下手なのに画家の絵を酷評する人でしたが(笑)、カレンダーの裏か何かに描いたのを職員さんがすごく褒めてくれて。気を良くしたようでやる気になり、どんどん上手く描けるようになりました。
何よりも驚いたのは、もともとはネガティブだった性格が、全く逆の明るくポジティブに変わったこと。人の悪口しか言わなくて、私にも嫌なことしか言わなかったのに、人のいいところを見つけるんです(笑)。みんなからちょっと煙たがられてるおばあさんがいたんですけど「〇〇さんは色が白くて器量よし。きっと昔は綺麗だったんだろう」とノートに書きとめていたのを後から見つけました。
さらに、母が旅行で父と撮った写真を急に、部屋に飾り出したんです。昔の男の人って妻に秘書みたいに荷物を持たせて、自分はステッキだけ持って歩いてるみたいな。そんな旅行だっただろうに、母が「この写真、この葉っぱが綺麗やろう?」とか言って眺めているんですよ。初めて知る母の一面を見たようで驚きました。
職員さんから「認知症になると性格が反対になることが多い」というお話を聞きました。母とは逆に、上品だった人が、「ぶっ殺してやる」なんて残酷な言葉を使うこともあるとか。「介護されるとき優しい人になるように、今は性格を悪くしておこう」と、職員さんと笑いました。
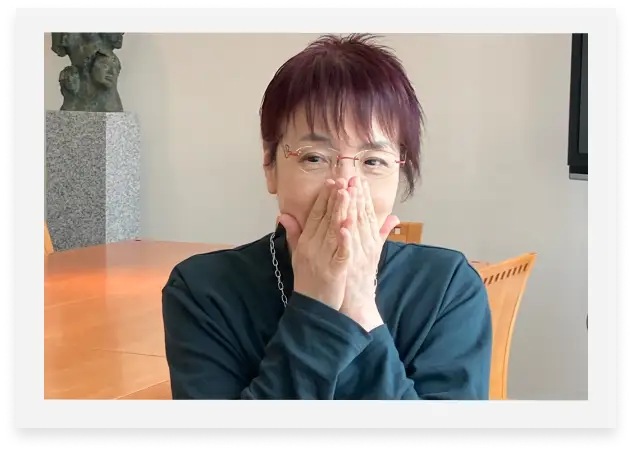

認知症ではあったけれど
家庭的なグループホームで
母は楽しく過ごせました
介護のプロの言葉に
ハッとして
だんだん母のパーキソン病が悪化して、胃ろうが必要になり、もうグループホームでは看られないとなってしまって。まずはいったん、滋賀県の老健に移り、その間に滋賀県と、私が暮らす東京の両方で、特養を同時に探しました。
私が行きやすいところにあるか、何分で行けるか、掃除は行き届いているか、入ったときの臭いはどうかなど、気になる部分をチェック項目にして、見学したところを全部リストにしていきました。滋賀と東京を行き来しながら探し回り、やっと「ここならいいな」と、チェック項目が合格する施設を、東京で見つけました。
特養はなかなか空きがなく民間の施設になりましたが、以前から色々相談していた東京の福祉課の職員さんにさっそく報告に行くと「お母さんを東京に呼ぶということですよね。それは、あなた本当に自己満足ですから」ときつく怒られました。
「お母さんはもうしっかりしてるわけではなくて、夢の中にいるような状態です。ずっと関西の人なのに、毎朝起きると関西弁じゃない言葉が聞こえてきたら、私どこにいるのってどれだけ不安になるか、考えたことありますか?」と。
母が「くつろげるところで横になっているんやな」と思うところでないといけない。やはり住みなれた滋賀がいい。候補の一つになっていた特養で、窓から琵琶湖が見えて、周りに畑が多く、肥やしのにおいが時々する、母が幸せだった子どものころに住んでいた場所にあるような施設がありました。明るく掃除も行き届いていたので、そこに決めました。
そうして滋賀に決めた特養でしたが、入る頃の母は、認知症も進んで衰弱もして、もう話もできませんでした。毎週お見舞いに行くと、ニコニコと笑っているだけ。好きだった歌を一緒に歌ったりして過ごし、入居して3年ほどして、穏やかに亡くなりました。
ジャズダンスが
ストレス解消になった
20代から30年くらい、親戚や両親を遠距離で看てきましたが、同居しようと思ったことはありません。距離があってこそ、仲良くなかった両親の世話ができた。私にとって距離の移動はたとえ頻繁であっても、大変というよりも気分転換です。早起きして乗る始発の新幹線、周りはみんなスーツを着ていて、まるで会社。電話もかかってこない集中できる空間で、仕事もはかどりました。
20代で始めたジャズダンスもストレス解消になりました。ふだんの私は自分で操作する仕事内容で、生活も自分でマネージメントしないといけないので、ダンスレッスンの先生から、指示されたことをそのままやるのが逆に新鮮。振りやステップを覚えて、できるようになると嬉しいし、賑やかな音楽で身体を動かしていると頭がスッキリします。
だんだん振りの覚えが悪くなってきて、若い方の迷惑になってきました(笑)。でも、趣味としてできるだけ続けていきたいです。
取材・文・/大橋史子(ペンギン企画室) イラスト/松元まり子 協力/株式会社Miyanse
『月刊益軒さん 2024年3月号』(カタログハウス刊)の掲載記事を転載。
-
第1回
介護者も自分の健康を気にかける時間が必要です
篠田節子さん【前編】1月29日公開
-
第2回
介護者も自分の健康を気にかける時間が必要です
篠田節子さん【後編】2月5日公開
-
第3回
精神論では無理。介護が始まる前に家族で話し合っておきたい
ハリー杉山さん【前編】3月11日公開
-
第4回
精神論では無理。介護が始まる前に家族で話し合っておきたい
ハリー杉山さん【後編】3月18日公開
-
第5回
後ろめたさを感じずに介護はプロを頼っていい
安藤優子さん【前編】3月25日公開
-
第6回
後ろめたさを感じずに介護はプロを頼っていい
安藤優子さん【後編】4月1日公開
-
第7回
無理のない役割分担で『きょうだいチーム介護』を実践
岸本葉子さん【前編】4月15日公開
-
第8回
無理のない役割分担で『きょうだいチーム介護』を実践
岸本葉子さん【後編】4月22日公開
-
第9回
元気なうちに延命治療について希望を聞いておくべきです
盛田隆二さん【前編】5月21日公開
-
第10回
元気なうちに延命治療について希望を聞いておくべきです
盛田隆二さん【後編】5月29日公開
-
第11回
「介護はプロとシェアして」という言葉で、罪悪感から解放された
信友直子さん【前編】6月21日公開
-
第12回
「介護はプロとシェアして」という言葉で、罪悪感から解放された
信友直子さん【後編】6月28日公開
-
第13回
一人で抱え込まないようにして介護うつ、介護後うつの予防を
安藤和津さん【前編】7月19日公開
-
第14回
一人で抱え込まないようにして介護うつ、介護後うつの予防を
安藤和津さん【後編】7月26日公開
-
第15回
親子の関係が逆転する「交差地点」をうまく乗り越えるのが大切
綾戸智恵さん【前編】8月23日公開
-
第16回
親子の関係が逆転する「交差地点」をうまく乗り越えるのが大切
綾戸智恵さん【後編】8月29日公開
-
第17回
絶対に一人で抱え込まず専門家の輪の中で介護を
山口恵以子さん【前編】9月26日公開
-
第18回
絶対に一人で抱え込まず専門家の輪の中で介護を
山口恵以子さん【後編】10月2日公開
-
第19回
介護の日々を文章にすることで、辛い気持ちも救われました
伊藤比呂美さん【前編】11月5日公開
-
第20回
介護の日々を文章にすることで、辛い気持ちも救われました
伊藤比呂美さん【後編】11月11日公開
-
第21回
母に手を上げてしまったとき、自宅介護を諦める決心がついた
松浦晋也さん【前編】12月3日公開
-
第22回
母に手を上げてしまったとき、自宅介護を諦める決心がついた
松浦晋也さん【後編】12月12日公開
-
第23回
介護に振り回された7年間は自分の老後を考えるきっかけに
秋川リサさん【前編】1月15日公開
-
第24回
介護に振り回された7年間は自分の老後を考えるきっかけに
秋川リサさん【後編】1月23日公開
-
第25回
本人が納得してくれることを大切に。父と母のダブル介護を乗り越えて
荻野アンナさん【前編】2月10日公開
-
第26回
本人が納得してくれることを大切に。父と母のダブル介護を乗り越えて
荻野アンナさん【後編】2月17日公開
-
第27回
この先を考えれば不安も。まず「今日、明日」で考えています
にしおかすみこさん【前編】3月13日公開
-
第28回
この先を考えれば不安も。まず「今日、明日」で考えています
にしおかすみこさん【後編】3月20日公開
-
第29回
介護のストレスは外に吐き出して解消。「言いふらし介護」をおすすめします
新田恵利さん【前編】4月11日公開
-
第30回
介護のストレスは外に吐き出して解消。「言いふらし介護」をおすすめします
新田恵利さん【後編】4月17日公開
-
第31回
介護には客観的な視点が重要。いいケアマネさんに出会えました
入江喜和さん【前編】5月15日公開
-
第32回
介護には客観的な視点が重要。いいケアマネさんに出会えました
入江喜和さん【後編】5月22日公開
-
第33回
認知症の父と向き合うために哲学が役に立ちました
髙橋秀実さん【前編】6月12日公開
-
第34回
認知症の父と向き合うために哲学が役に立ちました
髙橋秀実さん【後編】6月19日公開
-
第35回
謎が多すぎる両親を遠距離でお世話と見送りを
姫野カオルコさん【前編】7月17日公開
-
第36回
謎が多すぎる両親を遠距離でお世話と見送りを
姫野カオルコさん【後編】7月24日公開