映画評論の大家である山田宏一さんに、毎月、とっておきの映画を「2本立て」で紹介していただくコーナーです。今回は、昨年末に惜しくも亡くなったブリジッド・バルドー(B.B.)の追悼です。彼女の全盛期を同時代的に見つめて来られた山田さんに、数ある出演作の中から『気分を出してもう一度』と『軽蔑』の2本を選んでいただきました。あらためてこのフランスを代表する大スターの魅力にひたってみたいと思います。
紹介作品
気分を出してもう一度
製作年度:1956年/上映時間:96分/監督・脚本:ミシェル・ボワロン/原作:ケリー・ルーズ/共同脚本:アネット・ヴァドマン/撮影:ロベール・ルフェーブル/音楽:アンリ・クロラ、アンドレ・オデール/出演:ブリジッド・バルドー、アンリ・ヴィダル、ノエル・ロクヴェール、ダリオ・モレノ、ポール・フランクール、フランソワ・ショメット、フィリップ・ニコ、ドーン・アダムス、マリア・パコム、セルジュ・ゲンズブールほか
軽蔑
製作年度:1963年/上映時間:102分/監督・脚本:ジャン=リュック・ゴダール/原作:アルベルト・モラヴィア/撮影:ラウル・クタール/音楽:ジョルジュ・ドルリュー/出演:ブリジッド・バルドー、ミシェル・ピコリ、ジャック・パランス、ジョルジア・モル、フリッツ・ラングほか
セクシーなB.B.旋風吹きまくるとばかりに1950年代から60年代に超人気スターとして多くのファンを悩殺したフランス女優、ブリジッド・バルドーが昨年末(2025年12月28日)、91歳で亡くなった。1973年にすでに女優業からは引退していたが、生誕90周年記念映画祭が2024年から25年にかけて催されたあと11作品がDVD化され、オールカラーによる300点以上の映画ポスターを掲載した「ブリジッド・バルドー映画ポスター・コレクション——世界がB.B.に恋した時代——」(井上由一編、Du Books発行、ディスクユニオン発売)が刊行されたばかりだった。
姓名のイニシャルだけの愛称、MM(マリリン・モンロー)、CC(クラウディア・カルディナーレ)とともに、BB(ブリジッド・バルドー)をセクシーな人気スター3人揃い踏みのように対抗させたり持ち上げたりするけれども、BBはフランス語で赤ちゃん(bébé)と同じベベと発音するので、肉感的な魅力、グラマーという以上に、とても愛くるしいイメージが先立つところが、MM、CCとは異質のセックスシンボルだったような気がする。あどけないベベ(赤ちゃん)だがMMのようにおバカさんあつかいされたこともなかったと思う——挑発的で生意気なわがまま娘とみなされたことはあったとしても。
女優を引退したあと、財団を立ち上げ、動物愛護運動に尽力した功績(死亡記事では大きく取り上げられている)などはともかく、単純に映画女優として忘れがたいブリジッド・バルドー、B.B.の魅力を、DVD(あるいはブルーレイ)で見られる代表作のなかから『気分を出してもう一度』(ミシェル・ポワロン監督、1959年)と『軽蔑』(ジャン=リュック・ゴダール監督、1963年)を追悼の意もこめて久しぶりにあらためて見ながら、再検討してみたいと思う。
●健康的なお色気にあふれたB.B.の天衣無縫さ
『気分を出してもう一度』は、題名からして肩の凝らない(というか、気軽に見られる)コメディーで、ブリジッド・バルドーがちょっと太めの——太めながら軽快に踊りまくる——ダンス教師(トルコ人とイタリア人の混血で歌手としても活躍していたダリオ・モレノ)とマンボを踊る愉快なシーンが何よりもまず思い出されて、どうしてもまた見たくなった。ブリジッド・バルドーも愛くるしく、まさにB.B.という愛称で呼びたくなるような可愛らしさで、踊りっぷりもすごく素敵で、たのしい。〽わたしといっしょに踊りませんか/気分を出してもう一度…/あなたはほんとに美しい/ほんとに まったく美しい/誰より一番美しい…と映画の冒頭から歌っている男の声が聞こえてくるのだが(歌っているのはダリオ・モレノか?)、まったく、ベベをくどいて誘って、いっしょに踊りたくなるだろう。ベベも大はしゃぎで、いっしょにテンポよく調子を合わせて、スカートが舞い上がるような勢いでめくれ上がるほど踊りまくってくれるだろう。ダンスもとても上手だ(と思う)。ミシェル・ポワロン監督の前作『殿方ご免遊ばせ』(1957年)でも、ベベは——フランスの首相の一人娘という役で——フランス訪問中の某国の殿下(シャルル・ボワイエ)と親密にダンスを踊るのだが、そのはつらつとした健康的でエロチックな踊りっぷりの見事さといったらなかった。
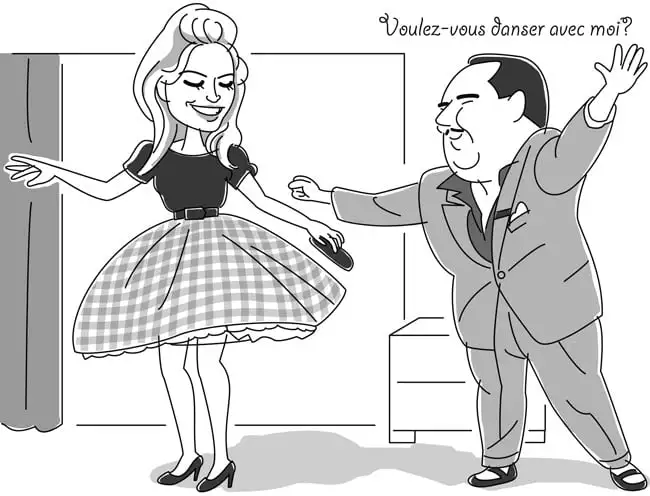
イラスト/池田英樹
パリの裕福な実業家を父として少女時代はバレリーナを夢みつつコンセルヴァトワール(パリ国立音楽院)に学び、フランス上流家庭の雰囲気に包まれて育ったということだから、ダンスを優雅に踊るのはお手のものだったのだろう。いいうちのお嬢さんとして何不自由なくわがまま放題にすくすくと育ったのかもしれない。
そんな育ちのよさが女優になったB.B.に災いしたのは手のつけられないそのわがままぶりだったにちがいないが(スターにつきもののスキャンダラスな噂はやむを得なかったのだろうけども)、それ以上に幸いしたのはその天衣無縫(何をやってもわざとらしくない自然で微笑ましく有終完美、裸にならなくても何も着ていない感じのおおらかな官能的魅力)、天真爛漫(飾り気のない無邪気さ、平然として泰然自若の露出ぶり)、技巧的にちらちらと見せるせこいストリップまがいの芸当とはまったく無縁のぬぎっぷりの気軽さ朗らかさだ。かがやくようなブロンドの髪も豊かな若く可愛いパリのお転婆娘の当世風の行状記が、ミシェル・ポワロン監督のたわいないけれども実にたのしいセクシー・コメデイーなのである。『気分を出してもう一度』はそんな奔放なパリのわがまま娘の結婚篇である。それもアメリカの犯罪小説、ケリー・ルースの「ブロンド娘は踊りながら死んだ」を原作にしたミステリータッチのコメディーだ。可愛いブロンド娘(ブリジッド・バルドー)が実業家の——といっても、そうは見えない、すっとぼけた感じの——父親(ノエル・ロクヴェール)を連れて若い独身の歯医者(ハンサムだがタフでいかつい感じのアンリ・ヴィダルがけっこうコミカルに元気いっぱいに演じる)に、パパが虫歯で苦しんでるからすぐ診てほしいと急にやってきて、診察室でお互いに一目惚れ。ベベには婚約者が決まっていたのに、どうしてもこの男前の歯医者さんと結婚したいとわがままを言う。こんな「牛飼いみたいな男」のどこがいいんだと父親は反対するが、次のシーンはもう結婚式というすばやく快調な展開である。
スピード結婚のあと、早くも夫婦喧嘩。診察室で歯医者とその助手の看護師として夫婦共同の仕事がうまくいかず、「この役立たず!」「ヤブ医者!」とどなりあって、ベベは家を飛び出してしまう。家に取り残されたアンリ・ヴィダルは気を紛らそうとナイトクラブに行って時間をつぶしていると妖艶な美女(ドーン・アダムス)に声をかけられ、ダンスに誘われる。「ダンスはへたでしょう」と男が言うと、美女は「わたしはダンス教室を経営しているのよ。ぜひいらっしゃい。ダンスも教えてあげる」。
ナイトクラブを出て、美女の部屋に連れ込まれ、あでやかな美女に誘われるまま、長椅子の上であらわな美女の胸にキスしてしまったりするが、「妻を愛してるから浮気をするわけにはいかない」とあやうく我に返って美女のもとを辞去。しかし、ナイトクラブから美女の部屋までひそかにあとをつけて美女の部屋の長椅子であられもなく抱き合うふたりの姿態を写真に撮っていた怪しげな男(まだ若くて耳が大きくて蒼ざめた顔のセルジュ・ゲンズブール)には気がつかなかった。怪しい男は美女の仲間で、すべては彼女の企んだ罠だったのである。
その夜遅くそっと家へ帰ってきたB.B.は夫のアンリ・ヴィダルとベッドで愛し合って仲直り。翌朝からまた診察室で歯医者と助手の看護師として仲よく共同の仕事を再開するが、そこへ昨夜の美女、ドーン・アダムスがやってきたのである。もちろん診察のためではない。怪しげな男の撮った“証拠写真”をネタに恐喝に来たのである。歯医者のアンリ・ヴィダルの義理の父、つまりB.B.の父親が実業家で金があると見てのゆすりだった。アンリ・ヴィダルはとりあわなかったが、次は電話で呼び出され、ダンス教室を訪れたアンリ・ヴィダルはドーン・アダムスと談判を重ね、ゆすりの金の支払いを拒否しつづける。ドーン・アダムスからの電話をたまたま父親のノエル・ロクヴェールとともに傍受したB.B.は、「ほら、やっぱり、あの牛飼いみたいな歯医者には女がいたんだ」と諭す父親をなだめて、ダンス教室まで夫のあとをつけて監視する。アンリ・ヴィダルはアンリ・ヴィダルで自分の清廉潔白を主張し、脅迫には負けんぞとがんばるのだが、ダンス教室のオフィスに経営者の美女、ドーン・アダムスにきっぱりと結着をつけるつもりで会いに行くと、彼女は何者かに撃たれて死んでいた…という、とんでもない殺人事件が起こる。犯人の嫌疑をかけられた夫を救うべく、素人探偵ベベの活躍がはじまるのだが、ダンス教室で踊ったり、女装の変態男たちが出てきて歌ったり、あれやこれやいろいろあって、最後はやっぱり気分を出してもう一度ということになるのだが!
●B.B.の美しい金髪と肉体が輝く前衛的メロドラマ
『軽蔑』は、1952年に全作品が露骨な性描写やその反社会性ゆえにローマ教皇庁の禁書リストに載せられたというイタリアのスキャンダラスな(と言ってもいいような)作家、アルベルト・モラヴィアの「映画人とその妻の愛憎模様」を描いた同名の小説(「侮蔑」の題で邦訳されている)の映画化。ヌーヴェル・ヴァーグの旗手、ジャン=リュック・ゴダール監督と新時代のセックスシンボル、B.B.との世紀の組み合わせが大きな話題になった。日本公開時のポスターにも「B・B=ゴダールが放つ強烈な愛の断層!」とうたわれた。フランスのシナリオライター(ミシェル・ピコリ)がハリウッドのプロデューサー(ジャック・パランス)からイタリアのチネチッタ撮影所と地中海のカプリ島ロケで撮影されるドイツの大監督(フリッツ・ラング本人が出演)の新作の書き直しを依頼されて、妻のブリジッド・バルドーとともにローマにやってくる。金のために雇われて横暴なプロデューサーの言いなりになるシナリオライターの夫の卑屈な態度を軽蔑して妻は同じベッドで夫と寝ることも避けるようになり、アメリカ人のプロデューサーに誘われるまま親しくなって、プロデューサーとともに自動車事故で惨死してしまうというシニカルなタッチの、なんとも救いのない愛憎のドラマとともに、世界的に斜陽の風が吹きまくっていた時代の映画界の裏側(広大なチネチッタ撮影所も閑散として映画製作に賑わっている光景など見られない)がわびしく描かれる。

イラスト/池田英樹
ロケ地のカプリ島では地中海をのぞむ崖っぷちの真っ白な屋上建築(マラパルテ邸)を中心に、燃えるような太陽の下で、全裸のベベの美しい金髪と肉体がかがやく。わがままで気分屋のスター女優にゴダール監督はてこずり、得意の逆立ちを曲芸まがいにやってみせてはご機嫌を取って裸になってもらったのこと。映画のなかでは助監督の役で出演もしながら、映画とは何かを問いつつ、「映画人とその妻の愛憎模様」を特異なゴダール・スタイルで描いた格調高い最高の前衛的メロドラマだ。
余談ながら、ブリジッド・バルドーはのちにわがままいっぱいに言いたい放題の回想録「ブリジッド・バルドー自伝 イニシャルはBB」(渡辺隆司訳、早川書房)で、ゴダールを「薄汚いインテリ」とののしり、軽蔑する夫の役のミシェル・ピコリも助監督役のゴダールも同じような不細工な黒い帽子をかぶっていることをあげつらっているのだが!

イラスト/野上照代
山田宏一
やまだこういち●映画評論家、翻訳家。ジャカルタ生まれ。東京外国語大学フランス語学科卒業。1964~1967年にパリ在住。その間「カイエ・デュ・シネマ」の同人となり、ジャン=リュック・ゴダール、フランソワ・トリュフォーらと交友する。

