映画評論の大家である山田宏一さんに、毎月、とっておきの映画を「2本立て」で紹介していただくコーナーです。前回に引き続き、若尾文子の出演作とイギリスのイーリング・コメディーの名残りのような珍品の2本立てです。前者は若き日の若尾文子が演技開眼するきっかけとなった『祇園囃子』。そして後者は皮肉の効いたコミカルなスリラー『紳士同盟』です。
紹介作品
祇園囃子
製作年度:1953年/上映時間:116分/監督:溝口健二/原作:川口松太郎/脚本:依田義賢/音楽:斎藤一郎/撮影:宮川一夫/出演:木暮実千代、若尾文子、進藤英太郎、河津清三郎、菅井一郎、田中春男、小柴幹治、浪花千栄子など
紳士同盟
製作年度:1960年/上映時間:99分/監督:ベイジル・ディアデン/原作:ジョン・ボーランド/脚本:ブライアン・フォーブス/音楽:フィリップ・グリーン/撮影:アーサー・イベットソン/出演:ジャック・ホーキンス、ナイジェル・パトリック、ロジャー・リヴシー、リチャード・アッテンボロー、ブライアン・フォーブス、キーロン・ムーアなど
●若尾文子はいかに人気があったか
「若尾文子映画祭Side.A/Side.B」の開催にあたって映画女優・若尾文子についてのいろいろな文献を私なりに調べていたところ、「キネマ旬報」の古い号(1956年3月下旬号/No.141)に「ファンレターの研究 若尾文子の場合」というおどろくべき特集記事が見つかった。おどろくべきというのは、8ページにわたる大特集であるばかりか、映画評論家や編集部による特集記事ではなく、社会心理研究所(南博/大井しな子/柳真沙子)による学術的な、社会心理の分析なのである。いわく、「現代の人気スターの第一人者である若尾文子のところへ来た1ヶ月間のファンレター2,955通の内容を分析して、マス・コミの立場から映画の魅力、人気の構造、ファン心理の内容等を研究してみた。これは若尾さんの協力を得て、社会心理研究所に委嘱したものである」という次第。
ファンレターの内容分析(サインを求める平凡なタイプからスター志願のタイプ、女中志願のタイプ、弟子入り志願のタイプ、結婚の世話をたのむタイプ、求愛のタイプ、金の無心のタイプ、映画無料パスの無心のタイプ、脅迫のタイプ、等々に至るいくつかの典型についての、スクリーンの若尾文子ばかり夢中になって追いかけてきただけの私などには考えも及ばない、数々の分析)以上に私にとって興味深かったのはもちろん「若尾文子出演作の分析」で、「彼女の出演作品の中からファンが“最も若尾文子らしい”といって好んでいる」映画の1本に『祇園囃子』が取り上げられていることがうれしかった。若尾文子のスクリーン・デビュー2年目に巨匠・溝口健二監督に目を付けられ(当然その才能を見込まれて)、主演の木暮実千代と同格の、というか、互角の共演に抜擢された——若尾文子のキャリアの転機になる——記念すべき作品だった。戦前、『祇園の姉妹』(梅村蓉子と山田五十鈴の共演)という名作を撮っている溝口健二監督が再び祇園の芸妓の世界を描いた風俗映画で(オリジナルストーリーだが、映画化に先立ち、川口松太郎が原作を小説の形で書いて雑誌「オール讀物」に発表し、『祇園の姉妹』と同じ、依田義賢が脚本を書いた)、姉芸者を木暮実千代、妹芸者を若尾文子が演じ、特に若尾文子は将来の大女優の片鱗を見せた作品として評価された。
というわけで、今回の日本映画はまたも若尾文子、それも若き日の若尾文子の忘れがたい『祇園囃子』である。
DVDで見直した『祇園囃子』は、古めかしい白黒の画面ながら、いかにも田舎から出てきたような(などと言っては失礼ながら)、特に華やいだ感じもない、ごくふつうの女の子に見える若尾文子が京都の花街に出てきて、芸妓修行をへて、みるみる一人前の祇園芸者に成長していくまでの物語。細い露地、物売りの声など、当時の京都特有の風物描写もさりげなくリアルで、舞妓を志してくる娘、茶屋の女将、出入りする男たち、金銭や色恋沙汰をめぐるかけひきなどの風俗描写もあざやか、風俗映画の傑作とみなされる所以でもあるだろう。
「若尾文子映画祭」のプログラムにも引用されているが、こんな若尾文子の回想も興味深い。

イラスト/池田英樹
「映画のトップシーンは、私が演じた栄子という少女が京都の舞妓になりたくて、生まれ故郷から単身出てくるところ。だから、映画のその場面で着ることが決まっている木綿の衣裳を着て、ほんとの祇園の置屋さんに修行に行ったんです、住み込みで。雑巾がけから、何もかも、普通の住込みの舞妓さんがやることと同じ事をやりました。その間に、舞妓さんが芸事を練習する女紅場という場所へ通って、三味線とか踊りとか、鼓みとか太鼓とか、ほんの入口ですけど、一通り習わされて、それからクランクインです。置屋さんには2週間くらい住み込んだと思いますね」。
置屋とは「芸娼妓を抱えておく家」で、「自分の家では客を遊興させず、揚屋・茶屋から注文に応じて芸娼妓をさしむける」と辞書(「広辞苑」)にもある。「キネマ旬報」の特集「ファンレターの研究 若尾文子の場合」には、『祇園囃子』は若尾文子中心にこんなふうに具体的に紹介される。
「若尾文子の最初の舞妓もので、これで評判になって、『舞妓物語』『荒城の月』などの企画が生まれた。ブロマイドでも、若尾文子の舞妓姿は最もファンに好まれている。
芸者の子に生まれた栄子は、母親に死に別れ、たよる人もなく、親の友だちの祇園芸者・美代春をたよって舞妓になる。どんな苦労も辛抱する芸熱心な子であった。はじめてお座敷に出たとき、客「さ、祝いに一杯いこう」と、なみなみと酌する。栄子はすまして一口に飲み干してケロリとしている。
客「ほう、駈けつけ三杯か。こりゃ偉い」
栄子、またすまして、ぐっと飲んでしまう。栄子、ぐでんぐでんに酔いつぶれる。美代春は怒って、「あきれた子、店出しの夜からガブガブのんで酔ってしまう子があるかしら」
栄子「すみません姉ちゃん、それよりうち、お酒ってこんなに凄いもんかということ知らなんだのよ…お客さんが飲まさせるんやもん、飲まなんだらお座敷がつとまらんと思うて、営業に忠実に従うたまでよ…」という。向こう見ずで可愛らしい。
因襲と矛盾にみちた花柳の世界にいながら、「義理てなあに、わからないわ、あたし、人情てどんなもん」と大声でいって、皆をおどろかす。銀座のバーにお客が連れて行こうとすると、あでやかな舞妓の正装で出て来て、「これ、うちの制服よ。当り前の着物着て歩いたら、唯の女でしょう。この格好をしてこそ、祇園の舞妓やとみんなが騒いでくれはるわ、当り前のことでは人の心を惹く事出来へん世の中やもん…」。また皆は呆れて口もきけない。
客が無理に接吻すると、唇にかみついて全治1ヶ月の傷を負わせる。
ともかく不幸な環境にたえしのびながら、一本気で明るく、姉さん思いで因襲や権力に反抗する強い意志と正しさをもっている。こうした性格が、若尾文子のおっとりとした外貌、あまったれた声とほどよくまざって、庶民の心に入りこんだのである」。
このファンレターの分析による若尾文子の魅力のイメージは、ファンたちが「若尾文子のなかに、単に可愛らしいだけでなく、意志の強い面があることを強調している」が、「この意志の強さは内面的な、じっと耐えしのぶという形で表わされており、行動的な創造性を生み出す意志の強さではない」ことを南博の社会心理研究所は結びの言葉としている。「明るくはっきりしたアプレとも言われる性格も、内気で従順ないわゆる従来の女らしさの上にぬられたメッキにすぎない」のだ、と。因みに、アプレとはアプレゲール(フランス語で「戦後」の意で、今ではすたれてしまった呼称だが、当時、「第2次大戦後の若者の放恣で退廃的な傾向。また、その傾向の人。戦後派。」(広辞苑による)」の略称である。
そして…「若尾文子は、今『赤線地帯』で、ガラリと役柄の変わった[汚れ役]娼婦を演じているが、こうした役をファンたちは、不安気に見守っている。この作品の出来如何によっては、彼女とファンのむすびつきかたに変化がおこるであろう。彼女の役柄の中に、ファンの期待しないジャンルのものが増えてきたとき、ファンの心理がどう動くか、こうした問題は、俳優が次の段階へ進むとき、常におこるむずかしい問題である」。
●溝口健二から増村保造へ
『赤線地帯』(1956年)は売春防止法(1956年制定、翌年施行)成立直前の売春宿を舞台に娼婦たちの生態を生々しく描く溝口健二監督作品で、『祇園囃子』に次いで再び溝口監督から若尾文子に声がかかり、汚職で獄中にあった父親の保釈金稼ぎに身を売って小銭を貯める(ちゃっかりもので札束を数えてばかりいる)汚れ役の娼婦を演じた。『祇園囃子』で共演した木暮実千代も子持ちの娼婦役で出演していた。
『祇園囃子』では若尾文子を「子ども」と呼んでやさしかった溝口健二監督も『赤線地帯』では「キャメラを回してくれるまでに10日間もかける」というきびしさだったということだから、「大人になった」この女優にかける監督の期待も相当のものだったことが察せられよう。
「俳優が——女優・若尾文子が——次の段階へ進むとき」だったのだろう。溝口健二監督はこの最後の傑作と言うべき『赤線地帯』を遺作にこの世を去るのだが、「増村(保造)さんが、この『赤線地帯』のとき、イタリア留学から帰国して溝口組の助監督でした。溝口さんの意向や注意みたいなことを、増村さんが伝えに来てたんです。溝口さんに『増村、お前教育しろ』って言われてたみたいですね」と若尾文子はのちに述懐しているが(立花珠樹「若尾文子〝宿命の女〟なればこそ」 ワイズ出版)、やがて、増村保造監督は、かつての清純派女優から大人の女優へ完全に脱皮した若尾文子のキャリアの頂点を築く最も重要な役割を担うことになることは周知のとおりだ(若尾文子が大映のトップスターになる1950年代末から60年代にかけて増村保造監督は長短篇合わせて20本ものコンビ作品を撮っている)。
『祇園囃子』は美しい映画だ。木暮実千代と若尾文子の親子のような、姉妹のような芸妓同士の愛と友情と意地には心打たれずにはいられない。祇園祭の夜、笛や太鼓の囃子に誘われるように花街に生きる覚悟を胸に紋付長袖のふたりが歩き去るぽっくりの音がせつなく心に残る。
●イギリス的ユーモアの快作
今回の外国映画は、またも戦後のイギリス映画の一時代を築いたバルコン・タッチのイーリング・コメディーのつづき、それも遅れて来たイーリング・コメディーというか、もはやイーリング・コメディーの時代は終わったはずなのにその名残りを色濃くとどめていた忘れがたいイギリス的ユーモアの快作、『紳士同盟』(1960年)である。
とはいうものの、実はこんな映画までDVD化されていたのかと快哉を叫んだのも束の間、私のDVDプレイヤーとは相性が悪いらしく(どうしても機械音痴であることを認めざるを得ない私の手に負えず)、ついに日本語字幕が出てこなくて、映画の公開時に映画館で見ただけの覚束ない記憶だけをたよりに、以下、短く紹介させていただくことにする。
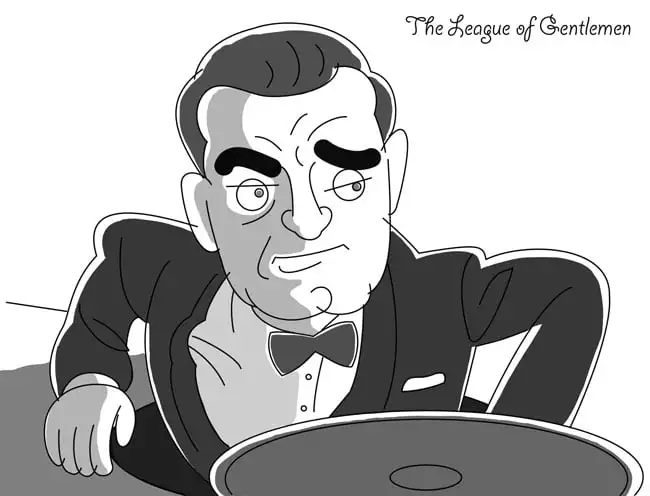
イラスト/池田英樹
バルコン・タッチのイーリング・コメディーというのは名プロデューサーのマイケル・バルコンの指揮のもとにイーリング撮影所でつくられた喜劇の総称で、すでに紹介したアレクサンダー・マッケンドリック監督の『白衣の男』(1951年)、『マダムと泥棒』(1955年)などがその代表作として知られる。東京国立近代美術館フィルムセンターで開催された「エリザベス女王来日記念——英国映画の史的展望」のパンフレットに映画史家・飯島正が書いている解説によれば「バルコン・タッチからみちびきだされたイーリング映画の喜劇」とは「一口でいえばドキュメンタリズムに裏打ちされたイギリス人独特の突飛なアイディアの喜劇だとでもいおうか」ということになる。ブラック・ユーモアをまじえてイギリス人独特の諷刺や皮肉や機知にあふれたギャグを伝統的なドキュメンタリー・タッチで描くコミカルなスリラーである。イーリング撮影所が閉鎖される1950年代後半までこの傾向はつづいたが、ハリウッド資本の攻勢などもあって、1956年、マイケル・バルコンはイーリング撮影所をBBCテレビに売却せざるを得ず、イギリス人気質の誇り高き牙城イーリング撮影所の時代は終わった——しかし、マイケル・バルコン傘下のイーリング撮影所から育った若手の監督たちがその後も活躍。その中の一人、ベイジル・ディアデンが戦後の犯罪都市ロンドンの警官たちの生活をドキュメンタリー・タッチで描いた小気味のいいスリラー映画『凶弾』(1959年)に次いで撮った珍品(とも言うべきか)が『紳士同盟』(1960年)なのである。
撒水車が走る夜明け前の道路のマンホールから、ひとりの紳士(ジャック・ホーキンス)が顔を出す。何者か? 軍備縮小で退官させられた中佐であることがわかってくるのだが、何かを企んでいるらしい。映画の題名どおり、7人の紳士たち、それも全員、免官された元将校たちを集めたプロフェッショナルの軍隊式同盟を結成し、大金強奪を実行するための特攻大作戦である。水ももらさぬ綿密な計画、用意万端、裏切りもなく、脱落者も出ず、万事好調、勝利の祝杯をあげ、大金を分け合って解散、というところまでとんとん拍子でいくのだが……最後は、なんと警察の護送車に全員集合、7人そろって隊長を迎え、最敬礼し、隊長も敬礼を返して「よろしい」(だったか、「休め」だったか、きっぱりとした軍隊用語の字幕で愉快に笑わされた記憶があるのだが!)。

イラスト/野上照代
山田宏一
やまだこういち●映画評論家、翻訳家。ジャカルタ生まれ。東京外国語大学フランス語学科卒業。1964~1967年にパリ在住。その間「カイエ・デュ・シネマ」の同人となり、ジャン=リュック・ゴダール、フランソワ・トリュフォーらと交友する。

