映画評論の大家である山田宏一さんに、毎月、その時期に合わせた映画を「2本立て」(日本映画、外国映画)で紹介していただくコーナーです。今回はアメリカ映画ならではの底抜けに明るいロマンチック・コメディ『九月になれば』と、木下惠介監督の最高傑作とも言える『野菊の如き君なりき』(1955年)です。
紹介作品
九月になれば
製作年度:1961年/上映時間:112分/監督:ロバート・マリガン/撮影:ウィリアム・H・ダニエルズ/音楽:ラッセル・F・シェーンガース/主題曲:ボビー・ダーリン/出演:ロック・ハドソン、ジーナ・ロロブリジーダ、サンドラ・ディー、ボビー・ダーリン、ウォルター・スレザック、ブレンダ・デ・バンジー
野菊の如き君なりき
製作年度:1955年/上映時間:92分/監督:木下惠介/撮影:楠田浩之/音楽:木下忠司・黛敏郎/出演:田中晋二、有田紀子、杉村春子、田村高広、笠智衆、松本克平
9月になればと思っているうちに、もう10月になってしまった。季節に合わせて(という口実で)邦洋2本立ての映画を見るという構想で、今回は木下惠介監督の最高傑作と言いたいくらいのしみじみとした味わいのある悲恋もの『野菊の如き君なりき』(1955年)とアメリカ映画ならではの、とちょっとノスタルジックに思い出す(というのも今はもう失われてしまったアメリカン・スタイルかもしれない)底抜けに明るいロマンチック・コメディ『九月になれば』(ロバート・マリガン監督、1961年)の2本立てであるというつもりが……。
リゾート感覚が満喫できる楽しさいっぱいのロマンチック・コメディ
9月になってもぐずぐずした猛暑で、あちこち天候異変がつづき、うかうかしているうちに9月も半ばすぎになってしまって、なんと思いがけずDVDでこれが見られることがわかって、遅ればせながらどうしてもこの忘れがたい『九月になれば』を見たいと思った次第なのだ。当時、『美女の中の美女』(ロバート・Z・レナード監督、1955年)といった映画のヒロインも演じたうっとりするくらい官能的なイタリア美人、ジーナ・ロロブリジーダに惑わされた作品でもあった。
9月になればイタリアのミラノ近郊のリゾート地の別荘に骨休みに出かけるというアメリカ人の大富豪の実業家が主人公で、演じるのは絵に描いたような二枚目、ロック・ハドソン。まだ40前の男盛りで、ローマに住む恋人、ジーナ・ロロブリジーダと甘い愛の9月を別荘でいっしょにすごすことをたのしみにしているのだが、ジーナ・ロロブリジーダのほうは9月だけの愛の生活にそろそろ終止符を打って、地道でも正式な結婚をするために、ロック・ハドソンのように大富豪でハンサムな相手ではないけれども結婚を申し込まれて花嫁衣裳も準備中である。まだ9月になる前、7月の出来事である。そもそも『九月になれば』という題名(原題も『Come September』)からして季節はずれの感じだ。そこへ、自家用飛行機でミラノ空港に到着したロック・ハドソンから電話がかかってくる。「これから別荘へ向かう、すぐ来てくれ、心から愛してるよ」というロック・ハドソンの甘い言葉に、ジーナ・ロロブリジーダはたちまち他の男との結婚の約束などどこへやら、別荘に向かうことになる。
一方、別荘のほうも、9月にしかやってこないはずのロック・ハドソンが7月なのに突然、商用とやらで現れることになって大騒ぎになる。というのも、執事のような管理人のウォルター・スレザックが9月まで内緒で別荘をリゾート・ホテルにして営業していたからである。ラ・ドルチェ・ヴィスタ(甘美な眺め)などというホテル名の看板やマッチまでつくり、テラスもちょっとしたカフェのようにしつらえた手ぎわのよさが笑わせる。いざとなると看板を取り外したり、絨毯を裏返したり、あれこれ裏表にひっくりかえしたりすればいいといった衣替えのように自然なすばやさだ。しかし、おおらかな大富豪のロック・ハドソンもさすがにどこか変だと気がつきはじめる。自分の別荘にピクニックから帰ってきた若い女学生たちがずかずかと入りこんできて、ロック・ハドソンをまるで余所者のように眺め、かわいい女学生のひとり、サンドラ・ディーは心理学を専攻していて、ロック・ハドソンをこの別荘の持ち主と思いこんでいるあわれな妄想狂患者のようにやさしくあつかって精神分析のテストを試みたりする始末だ。

イラスト/池田英樹
ロック・ハドソンはミラノ空港から最新の自家用車で別荘に向かう途中、アメリカから遊びに来ていた4人組の若者(その先頭に立つのが大ヒットした映画の軽快な主題曲も作曲している人気歌手のボビー・ダーリンである)の乗るボロ車とよくある意地の張り合いでバカバカしい競争をしたりするのだが、この若者たちがロック・ハドソンの別荘の前にテントを張って、別荘に泊まっている女学生とのデートを目論むことになって事態はいっそう面倒になる。ロック・ハドソンはもちろん女学生たちをすぐ追い出すように管理人のウォルター・スレザックに命じたのだが、別荘にやって来た恋人のジーナ・ロロブリジーダとやっと会えた祝賀の乾杯に抜いたシャンペンの栓がテラスから飛んで、それを踏んで転んでしまった女学生たちの引率係の先生(ブレンダ・デ・バンジー)が骨折して足腰が動かなくなってしまい、知恵袋のような管理人のウォルター・スレザックからのたのみもあって、ロック・ハドソンが女学生たちの看視役をひきうけることになってしまう。若者たちは女学生たちを助け出して遊びたいので、ロック・ハドソンとジーナ・ロロブリジーダを誘ってオートバイの遠乗りでくたくたにしてやろうと企んだりするが、タフなロック・ハドソンにはかなわず、自分たちのほうが逆にのびてしまう。
ナイトクラブでもロック・ハドソンは、夜じゅう踊りまくり、女学生を次々にパートナーに踊りながら、「若い男には気をつけろ、結婚前に気軽にからだを許したりしてはいけない」などとプレイボーイらしくない古風な道徳的なお説教をしたりする。それを知って9月だけの愛人あつかいされているジーナ・ロロブリジーダが「じゃあ、わたしは何なのよ」とロック・ハドソンに迫って、形勢逆転、ということになったりしていよいよドタバタがエスカレートする。
別荘のバーで若者たちとの強い酒の飲み合戦をやらかすというバカバカしくも愉快なシーンもあり、若者たちが次々にダウン、最後にボビー・ダーリンもぐったりとして寝込んでしまったのをたしかめてから、ロック・ハドソンはひとり悠然として、最後にもう1杯、ぐっと飲み干してから、階段をゆっくりと昇って、ジーナ・ロロブリジーダの待つ寝室に戻り、ドアを閉めたとたんに、若い者には負けんぞと命がけで虚勢を張っていた緊張感がいっきょに途切れてぶっ倒れるというおかしさ。
最後はロック・ハドソンとジーナ・ロロブリジーダの追いつ追われつのドタバタ恋愛合戦がジーナ・ロロブリジーダの忘れがたい誘惑の微笑みの勝利に終わるという、なんともたわいないロマンチック・コメディだ。毎日がピクニック日和といった感じの晴れ渡ったリゾート地を明るい色彩で撮影したたのしさいっぱいの作品。DVDが日本語吹き替え版か字幕版かの選択をしなければならず、操作がちょっと面倒ではあるのだが…。
素朴で純真な愛を静かな気品と風格のある演出で描く名作
『野菊の如き君なりき』は幼馴染の少年少女の純愛物語を日本的な(あまりに日本的な、と言いたいくらいの)美しい農村風景のなかに詩的に描いた木下惠介監督の名篇。映画そのものが抒情的な1篇の映像詩と称賛された。「風物的抒情に関しては天才的な映像感覚の持ち主である木下恵介監督の作品の中でも風物の詩情でひときわぬきんでているのがこの作品である。信州の山と河、野と雲、百姓家と小道、その美しさをさながら墨絵のような、絶妙なカメラ(名コンビの楠田浩之)で撮し出し、そのわびしさとなつかしさは、ほとんど溜息が出るほどであった」と佐藤忠男氏も書いている(「日本映画300」、朝日文庫)。白黒の映像がなつかしく美しい。原作は明治・大正の歌人としてよりよく知られる伊藤左千夫の中篇小説『野菊の墓』(しかし生前には歌集すら刊行されず、この純真可憐な悲恋物語小説だけが刊行されて多くの読者の共感を得たという)。
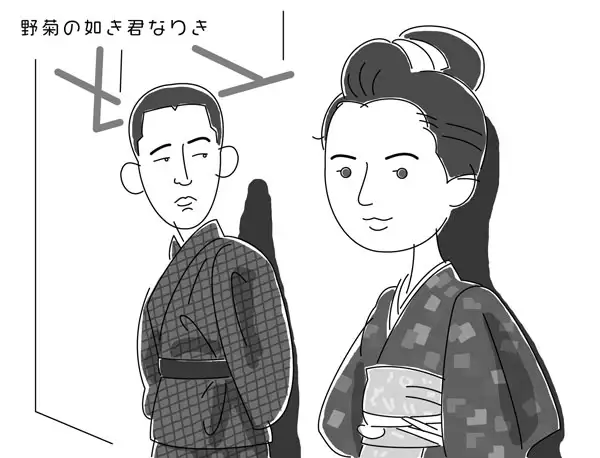
イラスト/池田英樹
静かな気品と風格のある映画的脚色のうまさもあって、文芸映画の香り高い名作に仕上がっているとと言っていいだろう。
75歳の老人(笠智衆)がなつかしい故郷の風景に囲まれた川を櫓(ろ)でさかのぼる渡しの小舟のなかで船頭と話をしながら60年も前の初恋——それも生涯ただ1度の恋——を思い出す。
まつひとも/待たるゝ人も/かぎりなき/思ひ忍ばむ/北の秋風に、という伊藤左千夫の歌集からの1句が画面に出たあと、楕円形の白いボカシで画面が縁取られて回想に入るという形式である。古いアルバムをめくるような感じでもあり夢のようなイメージの連続のようでもある。「死ぬ前にもう1度訪ねたいと思って」故郷に帰ってきたのだと老人はつぶやく。身寄りもなく、住んでいた昔の家もない。「はかないもんですなあ」と嘆きながらも、「もう60年も前のすぎ去ったことが忘れることができなくて……」というのである。
15歳の政夫と2歳年上の従姉(いとこ)の民子はいつもいっしょに山の畑で仕事をしながら、「民ちゃんは野菊のような女(ひと)だ」「政夫さんはりんどうの花のよう」とお互いに仲よく言い合っていた。あまりに仲がよすぎて村中の噂になっていたが、ふたりは何も悪いことをしていないのだから、周囲がどう言おうと、これからもずっと仲よくしようと誓い合う。それほど素朴で純粋な愛なのである。ふたりが並んで夕日を拝むうしろ姿の美しさとても印象的で心に残る光景だ。
やがて政夫が町の中学校に入るために村を去って行かなければならない日がやってくる。小舟に乗って去って行く政夫と涙とともに民子が別れを惜しみつつ見送る渡し場のシーンも美しく、せつなく忘れがたい。小雨が降りつづいて霧が立ちこめた川を小舟が遠く消えていく——運命がふたりの愛を永遠に引き裂くかのように。
政夫が冬休みで帰省する直前に、民子は実家の親の取り決めた縁談で他の家に嫁入りさせられる。中天に遠く満月が小さく淋しく輝く夜の野の道を花嫁姿の民子が馬に揺られて進む遠景もあまりにも悲しく幻想的で忘れられない。
意に反して結婚させられた民子は不幸のきわみに涙も涸れ果て、そして病死してしまう——政夫からの手紙とりんどうの花を胸にしっかりと抱いたまま。
映画のラストは野菊に囲まれた墓の前にひとりたたずむ老人のわびしい孤影である。今朝の朝の/霧ひやびやと秋草や/すべて幽(かそ)けき/寂滅(ほろび)の光、と自らの死を間近に感じながら老人は心に詠じているかのようである。

イラスト/野上照代
山田宏一
やまだこういち●映画評論家、翻訳家。ジャカルタ生まれ。東京外国語大学フランス語学科卒業。1964~1967年にパリ在住。その間「カイエ・デュ・シネマ」の同人となり、ジャン=リュック・ゴダール、フランソワ・トリュフォーらと交友する。

