映画評論の大家である山田宏一さんに、毎月、その時期に合わせた映画を「2本立て」(日本映画、外国映画)で紹介していただくコーナーです。2023年もまもなく終わります。クリスマスと正月を控え、慌ただしい日々を送っているみなさんに、心がほっこり暖かくなる、とっておきの2本立てを考えていただきました。共に大晦日がクライマックスとなる、木下惠介監督『今年の恋』とビリー・ワイルダー監督の『アパートの鍵貸します』の名作2本です。
紹介作品
今年の恋
製作年度:1962年/上映時間:82分/監督・脚本:木下惠介/撮影:楠田浩之、成島東一郎/音楽:木下忠司/出演:岡田茉莉子、吉田輝雄、田村正和、石川竜二、東山千栄子、三木のり平、三遊亭円遊、浪花千栄子
アパートの鍵貸します
製作年度:1960年/上映時間:120分/監督:ビリー・ワイルダー/脚本:ビリー・ワイルダー、I・A・L・ダイヤモンド/撮影:ジョセフ・ラシェル/音楽:アドルフ・ドイッチュ/出演:ジャック・レモン、シャーリー・マクレーン、フレッド・マクマレイ、レイ・ウォルストン、ジャック・クルーシェン、エディ・アダムス、ホープ・ホリデイ
急に寒くなったと思ったら、もう12月である。1年のしめくくり、大晦日が印象的なラストシーンになる邦洋2本立て映画を考えた。木下惠介監督(今年は生誕110周年、特集というほどではないにしても私なりに忘れがたい作品を何本かつづけて取り上げてきたけれども、今回がいちおう最後の1本になる)『今年の恋』(1962年)とアメリカ映画、ビリー・ワイルダー監督の『アパートの鍵貸します』(1960年)である。
心地良く爽やかなロマンチック・コメディーの傑作
『今年の恋』は1962年のお正月映画だった。日本映画にもこんなに軽快で素敵なロマンチック・コメディーがあるのだと快哉を叫びながら見た覚えがある。和服姿の岡田茉莉子がヒロインで、日本的な情緒たっぷりの映画なのに、ハリウッドの荒唐無稽なロマンチック・コメディーに負けず劣らず楽しく見られる作品だ。岡田茉莉子は美しく、喜劇的な役をやっても品があって、同じころ見た小津安二郎監督の『秋刀魚の味』(1962)でもチョイ役だったが、とても印象的で、何をやってもすばらしく、私はすっかり魅了され、彼女の出る映画なら何でも見たいと思うファンになってしまった。
自伝『女優 岡田茉莉子』(文藝春秋)にはこんなふうに回想されている。
「1961年11月下旬、木下惠介監督の『今年の恋』の撮影が始まった。2年前の『春の夢』と同じく、木下さんご自身が脚本を書かれた、(1962年の)お正月用の喜劇だった。前作は社会諷刺的なものだったが、今回は下町を背景にした、松竹調とでもいうべき喜劇だった。
銀座にある日本料理屋の娘である私は、結婚適齢期でありながら、数ある縁談に耳もかさず、店の看板娘として楽しく働いている。その私の唯ひとつの心配は、高校生の弟が不良であることだった。その原因が、弟の友達に誘惑されているからだと私は思い、その友達の兄と会い、きびしく非難する。その兄を演じる吉田輝雄さんも、自分の弟が不良になったのは私の弟のせいだと思いこんでおり、私を怒らせてしまう。やがてその兄は私を好きになり、求婚するのを、私は断ってしまう。そして最後には、私自身も愛していることに気づき、そのあとを追って京都に行き、大晦日の夜、知恩院境内で除夜の鐘をふたりで聴くというストーリーだった。
こうした松竹調のドタバタ喜劇も、木下さんが撮るとお仕着せがましくなく、心地よく爽やかに笑えるのはさすがに巨匠だからだろうか。」
映画は、不良の弟たち、といっても勉強よりもボクシングに熱中し、ボクシング部に入って励んでいるが、先輩の不良学生たちにいじめられ、喧嘩には弱いという話からはじまる。デビューしたばかりの田村正和と石川竜二が演じていて、いつもふたりでつるんでいる仲良し二人組で、学校の成績不良というだけで、むしろ気の弱い良家のお坊ちゃんたちといった感じだ。
勉強なんかできなくたっていいんだと無学文盲で自ら包丁を握って料亭を繁盛させている能天気な父親(落語家の三遊亭円遊がのんびりといい感じで好演)は、「ラブレターも書けなかったくせに」と女房(浪花千栄子)に毒づかれながらも、「昔はよかったなあ、勉強しなくて済んで…」と成績不良の息子を放任。
というわけで、気丈な娘の岡田茉莉子が親代わりになって弟の田村正和を不良の(と彼女は思いこんでいる)友だちの石川竜二との付き合いをやめさせようとするのだが、石川竜二のほうの家でも、男やもめの父(野々村潔)が鷹揚で物わかりのいい人だが愛人(高森和子)に夢中で息子をほったらかしなので、口うるさい婆や(東山千栄子が木下惠介の映画ではいつもながら痛快なお婆ちゃんぶりで笑わせる)と秀才でハンサムな大学院生の兄(吉田輝雄)が真剣になって弟の田村正和を不良仲間(と兄も婆やも思いこんでいる)から救い出そうとする。

イラスト/池田英樹
松竹の美人スター、岡田茉莉子と新東宝から松竹に移籍、入社第1回主演の吉田輝雄の顔合わせによる1962年の正月映画で、「木下惠介監督の新年度第1作! 大船調喜劇の決定版!」といううたい文句で公開された。木下惠介監督によれば、「都会的な喜劇というより下町もの、即ち大船調喜劇というべきもので、僕にとっては珍しく作中人物が涙を流すシーンは1ヶ所もないし、ほんとに屈託なく笑ってもらおうと、明るくからっと仕上げるつもりです」とその製作意図通りの作品になった。
まだ無声時代の1924年に松竹の蒲田撮影所の所長になった城戸四郎という大プロデューサーの下に、トーキー時代に入って1936年には大船撮影所に移転、松竹蒲田調、大船調とよばれる情緒たっぷりのメロドラマ、人生のように悲劇もあれば喜劇もあるが、女性の生き方、美しさがきわだつ、岡田茉莉子が自伝に述べている松竹調は、たとえドタバタ調でも、ロマンチック・コメディーを撮らせたら木下惠介監督の独壇場と言ってもいいぐらいだった。
岡田茉莉子と吉田輝雄のフレッシュなコンビがどこで、どんなふうにして出会い、愛を感じながらも接近したり離反したり、長い道中の果てに結ばれるかは見てのおたのしみということにしよう。ロマンチック・コメディーには男と女の喧嘩道中とも言うべきパターンがあってその定石どおり、口喧嘩をしながら富士山の見えるハイウェイのドライブの途中、何度も車を止めて降りてはまた乗って、運転席と客席にいたふたりが、ついにふたりならんでドライブするまでの微妙な変化というか、軌跡を見るだけでもほほえましく心躍る木下惠介タッチだ。
岡田茉莉子が看板娘の料亭は東京の銀座とはいえ下町風で、高級感より気軽にいろいろ人物が出たり入ったり、出会ったり別れたりする庶民的な場になっているところが、気取らない木下惠介監督流ならではの工夫なのだろう。
笑わせながらも鋭い人間観察と皮肉にみちた悲喜劇
『アパートの鍵貸します』は大都会の片隅に生きるしがない独身のサラリーマンの悲喜こもごもの人生を描いたコメディ・ドラマ(comedy drama)——コメディ(喜劇)でもあるとともに深刻なドラマ(悲劇)でもあるという。その底流にはチャップリンのヒューマン・コメディー(1928年の『サーカス』、1931年の『街の灯』、1936年の『モダン・タイムス』など)に連なるジャンル。アメリカ的プラグマチズム(社会的成功すなわち出世と金銭)にふりまわされながらも、愛に飢え、ニューヨークという大都会に生きる孤独なサラリーマンが主人公で、「ニューヨークという都市の心臓が脈打っているような映画」、その意味での「ニューヨーク映画の傑作」とヘルムート・カラゼク(『ビリー・ワイルダー自作自伝』、瀬川裕司訳、文藝春秋)は書いている。
主人公(ジャック・レモン)が働く高層ビルの保険会社は3万人もの社員をかかえているビルで、何百人もがタイプライターをたたいている巨大なオフィスの奥行きを出すために奥の方には大人の服装をさせた子供を配して遠近法を効果的に工夫したとのこと(アカデミー白黒美術監督賞を受賞したアレクサンドル・トローネルのデザインである)。
ジャック・レモンは会社が終わっても家に帰れないので、残業をしたり、バーのカウンターで飲んだくれたり、セントラルパークで寒さにふるえながら時間をつぶしたりして風邪を引いてしまったり……なぜ早く家に帰れないかというと、4人の上役に順ぐりに自分のアパートの鍵を貸して浮気をするための部屋を利用させているからなのである。もちろん、昇進させてやると出世欲につけこまれ、ほのめかされて(ときにはおどされて)、やむを得ずそんなラブホテルの営業みたいなことをひきうけているのだが、ビリー・ワイルダー監督は自ら「洗練された悪趣味」による鋭い人間観察と皮肉にみちた諷刺精神にもとづくものだというのだ。出世のために会社の重役たちにアパートの鍵を貸してデートの場を提供するなどといった汚い「商売」をひきうけた平社員の弱さ、いやしさ、愚かさと同時に、出世を夢見る社員の根性をくすぐり、そこにつけいって、昇進させることを条件にアパートの鍵を要求し、家庭は大事に守りながら浮気にはげむ、ブルジョワ根性まるだしの重役たちの醜悪さが、痛烈なお笑いとともに仮借無く告発される。「世に不道徳な物語」なのだとビリー・ワイルダー監督はシニカルに言うのである。だが、そこにも、もちろん、人間的なドラマがあるのだ。
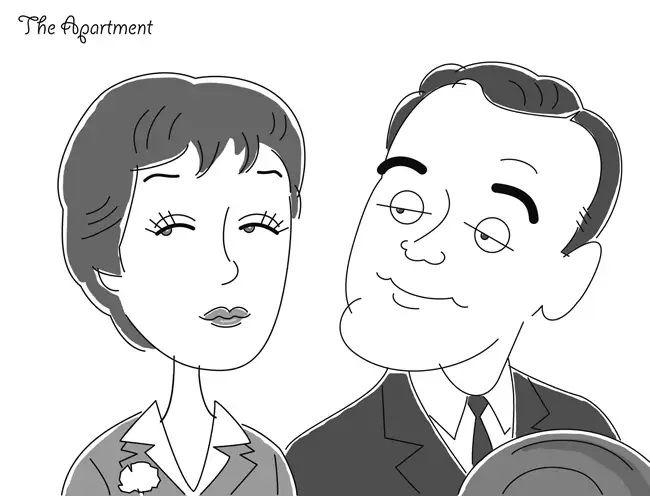
イラスト/池田英樹
ジャック・レモンのとぼけているようで、しみじみとした風情がさりげなくすばらしく、共感を呼ぶ。ビルのエレベーター・ガール(シャーリー・マクレーン)に彼は恋をしてしまうのだが、彼女は重役の愛人で、クリスマスイブに彼のアパートでデートしているのだ。その間、ジャック・レモンはバーのカウンターで飲んで時間をつぶしている(オリーブ入りのドライ・マティーニを飲んで、オリーブの種をていねいにカウンターに並べているので、何杯飲んだかがわかる)。そこで出会った女をめずらしく連れてアパートに帰ったら、シャーリー・マクレーンが自殺を図って倒れていて、事態は急変する。アパートの隣室の医師(ジャック・クルーシェン)がジャック・レモンを「この人でなしの色事師め!」とののしりながらもシャーリー・マクレーンの手当てをして命を救ってくれるが、ジャック・レモンは上役の部長に連絡を取り、アパートで寝たきりの彼女をあずかる形で面倒をみなければならなくなる。彼女がまた自殺を図ったりしないように剃刀を隠したり、窓をあけたりすると飛び降り自殺するのではないかと心配したり、食事用にスパゲティをゆでてテニスラケットで水切りをしたりする(ここは左手を使っているのがおもしろく、これはジャック・レモンが左利きだからでなく、チャップリンにならって、あえて左手を使って無器用な感じを器用に強調してみせたとのこと)。笑わせながらも涙ぐましい奮闘努力といったところ。
元気になって部長にひきとられたシャーリー・マクレーンは、大晦日の夜、レストランで、部長からジャック・レモンがもうアパートの鍵を貸してくれないんだという話を聞き、ジャック・レモンの彼女への愛を知ることになる。彼女は席を立ち、ジャック・レモンのアパートに向かって走る。涙がこみあげてくるほど感動的なシーンだ。アパートにたどり着き、部屋の前までくると、なかからバーンと銃声のような音がひびく。何事か…まさか自殺では? 彼女はあわててドアをたたく。
最後まで笑わせながらも、ささやかな人生のドラマを盛り上げるビリー・ワイルダー監督の巧妙な映画術である。

イラスト/野上照代
山田宏一
やまだこういち●映画評論家、翻訳家。ジャカルタ生まれ。東京外国語大学フランス語学科卒業。1964~1967年にパリ在住。その間「カイエ・デュ・シネマ」の同人となり、ジャン=リュック・ゴダール、フランソワ・トリュフォーらと交友する。

