映画評論の大家である山田宏一さんに、毎月、とっておきの映画を「2本立て」で紹介していただくコーナーです。今月は、若尾文子が女優として最も充実していた時期の名作『越前竹人形』を取り上げます。そして、フランスを代表する作曲家で、多くのヌーヴェル・ヴァーグの映画音楽を手がけたミシェル・ルグランのドキュメンタリー映画が劇場公開されることになりましたので、ミシェル・ルグランとゴダール監督との関係をメインにこの新作映画を解説していただきました。
紹介作品
ミシェル・ルグラン
世界を変えた映画音楽家
製作年度:2024年/上映時間:109分/監督・脚本:デヴィッド・ヘルツォーク・デシテス/脚本:ウィリー・デュハフオーグ/音楽: デヴィッド・ヘルツォーク・デシテス、ミシェル・ルグラン/撮影:ニコラス・ポーシャン、リヤド・カイラット、スタン・オリンガー/出演:ミシェル・ルグラン、アニエス・ヴァルダ、ジャック・ドゥミ、カトリーヌ・ドヌーヴ、バンジャマン・ルグラン、クロード・ルルーシュ、バーブラ・ストライサンド、クインシー・ジョーンズ、ナナ・ムスクーリなど
2025年9月19日(金)よりヒューマントラストシネマ有楽町ほか全国順次公開
公式サイト:https://unpfilm.com/legrand/
越前竹人形
製作年度:1963年/上映時間:102分/監督:吉村公三郎/原作:水上勉/脚色:笠原良三/撮影:宮川一夫/音楽:池野成/出演:若尾文子、山下洵一郎、中村玉緒、中村鴈治郎、殿山泰司、伊達三郎、浜村純、西村晃など
『若尾文子映画祭』もたけなわ、わが若尾文子セレクションもとりあえずこの1本でしめくくることにして吉村公三郎監督の忘れがたい『越前竹人形』を久しぶりにDVDで見て感動を新たにしたものの、個人的な思い入れもあってちょっと長めに書いてしまい、今回はこの日本映画1本のみにとどめることにしようと思っていたところ、特報のようにこれから公開される新作のフランス映画、それもとびきりの見ごたえある1作がとびこんできた。『ミシェル・ルグラン 世界を変えた映画音楽家』。つい2019年1月に87歳で亡くなった国際的なミュージシャン、作曲家、75年におよぶ音楽人生で手がけた映画音楽が200作品以上もあり、アカデミー賞の受賞も3回、その多彩な作曲活動とともに指揮者、歌手、ピアニスト、エンターテイナーとしての魅力も手に汗にぎる演奏と心ゆさぶる感動的なライブ感覚あふれる画面に横溢させた生々しい長篇ドキュメンタリー伝記映画である。
●ヌーヴェル・ヴァーグに愛された映画音楽家
映画ファンはヌーヴェル・ヴァーグとともにミシェル・ルグランの音楽の洗礼を受けることになる。ミシェル・ルグランの音楽と映画の結びつきが戦後の世界の映画を変革したヌーヴェル・ヴァーグ勃興期だったのだ。ヌーヴェル・ヴァーグのプロデューサーとして知られるピエール・ブロンベルジェの製作によるドキュメンタリー作家フランソワ・レシャンバック(ブロンベルジェの甥であった)のキャメラによるアメリカ紀行、それも現実を不意打ちすることによって人間や社会の真実(ヴェリテ)をとらえる映画(シネマ)という意味で「シネマ・ヴェリテ」とよばれた新しいドキュメンタリーの代表的な1本である1958年の『アメリカの裏窓』からはじまり(同じ1958年に若きミシェル・ルグランはアメリカに渡ってマイルス・デイヴィスやジョン・コルトレーンやアート・ファーマーといったそうそうたるジャズ・ミュージシャンをメンバーに率いて録音したアルバム「ルグランジャズ」を発表している)、ジャン=リュック・ゴダール、ジャック・ドゥミといったシネマ・ヴェリテの流れ(あるいは運動)と軌を一にするヌーヴェル・ヴァーグ(新しい波)の一派が次々にルグランに映画音楽を依頼することになるのである。
ヌーヴェル・ヴァーグの雄とも言うべきゴダールとルグランのコラボレーションはあまりにも独特で衝撃的で、なにしろ伴奏音楽が主旋律を奏でるだけで登場人物はそれに合わせて歌わないミュージカル『女は女である』(1961年)から、たてつづけに短篇『怠けの罪』(オムニバス映画『新・七つの大罪』第5話、1961年)『女と男のいる舗道』(1962年)、短篇『立派な詐欺師』(オムニバス映画『世界詐欺物語』第5話、1963年)、そして『はなればなれに』(1964年)とつづき(その前後にオムニバス映画『パリところどころ』第5話として撮る、『女は女である』の続篇的エピソードとも言える短篇『モンパルナスとルヴァロワ』もふくめて)、当初はとくに熱のこもったものだったと思われる。『女と男のいる舗道』のビリヤード室でアンナ・カリーナがひとり踊りまくるときの、そして『はなればなれ』のカフェでアンナ・カリーナがクロード・ブラッスールとサミー・フレーとともに肩を並べて踊るときの、ジュークボックスから流れるミシェル・ルグラン作曲のビートのきいたリズミカルなメロディーにはただ、ただ魅せられ、心躍った。ゴダールは『はなればなれに』のあと、さらにアンナ・カリーナがアメリカに行ってジーン・ケリーに会い、ミュージカルに共演して歌って踊りたいと申し込むけれども、ジーン・ケリーは「もうミュージカルの時代は終わってしまったんだ」と答え、そして、街に出てもうハリウッドの豪奢なミュージカルのセットもすべて壊されたり、長いあいだ放置されたまま廃墟と化してしまってるんだとノスタルジックに語り合いながら、アンナ・カリーナとともに歌って踊りはじめるという、ポストモダン・ミュージカルとも言うべき映画をミシェル・ルグランの音楽で構想していたはずで、のちにアンナ・カリーナにインタビューをするチャンスがあったので、あの企画はどうなったのかとたずねてみた。「そう、そう、企画というところまではいかなかったけれども、たしかにそんなアイデアをジャン=リュックと話し合ったことがあります」とアンナ・カリーナも思い出してくれた。「そのころ、ジャック・ドゥミがカトリーヌ・ドヌーヴ主演でせりふ全部が歌われる『シェルブールの雨傘』という美しい映画を作って、次は本格的なミュージカルをミシェル・ルグランと組んで撮る企画を立て、ジーン・ケリーの特別出演が決まっていた。『ロシュフォールの恋人たち』です。たぶん、その企画を知って、ジャン=リュックはわたしがジーン・ケリーに会いに行って歌って踊るという映画のアイデアをあきらめたのだと思います。ジャン=リュックはジャック・ドゥミを心から敬愛していましたから」とのことだった。

イラスト/池田英樹
『はなればなれに』はジャック・ドゥミ監督とミシェル・ルグランのコンビが大成功した『シェルブールの雨傘』と同じ1964年の作品で、ゴダール/ルグランの最後のコラボレーションになった。クレジットタイトルにも「ミシェル・ルグラン最後の(?)映画音楽」と出てきて、皮肉っぽく揶揄的に「最後の(?)」と疑問符入りでおどろかされた。映画『はなればなれに』のなかには『シェルブールの雨傘』の楽曲が愛と敬意をこめて引用されていて、この「最後の(?)映画音楽」の疑問符はむしろ惜別の思いがこめられたものだったのだろうと思われた。それから2年後、アンナ・カリーナが出演した最後のゴダール作品(長篇)、『メイド・イン・USA』(1966年)について、ゴダールはそれが何よりも『シェルブールの雨傘』に似せて作られた映画であり、「登場人物は歌っていないが、映画そのものが歌っているのだ」とミシェル・ルグランの音楽を未練がましくなつかしむかのように語るのである。『ミシェル・ルグラン 世界を変えた映画音楽家』を見ながら、そんなことまで思い出した。
●絶頂期の若尾文子が演じる宿命的な女の哀しみ
「私がちょうど30歳になるくらいの作品だったでしょうか」(「若尾文子 “宿命の女”なればこそ」)若尾文子・述/立花珠樹・著、ワイズ出版)と述懐する若尾文子の女盛りの、女としての容姿容貌の最も美しい年ごろ、肉体的にも精神的にも女優として最も充実した年ごろ、その意味での絶頂期のスター・若尾文子の代表作の1本が吉村公三郎監督の『越前竹人形』(1963年)である。
原作は水上勉の同名の小説。すぐれた大衆文学に与えられる直木賞の純文学変質がささやかれたほどの評判となった『雁の寺』以来、自己の鉱脈を発見したかのように『越後つついし親不知』『五番町夕霧楼』『越前竹人形』と宿命的な女の哀しみを詠じた官能的かつ抒情的な世界を開拓した異色の推理作家(松本清張に続く社会派推理小説の人気作家になる)、水上勉の小説はもしかしたらそれ以上に、目を見張る映画的鉱脈の発見につらなる原作だったのかもしれない。川島雄三監督、若尾文子主演の『雁の寺』(1962年)、吉村公三郎監督、若尾文子主演の『越前竹人形』(1963年)、田坂具隆監督、佐久間良子主演の『五番町夕霧楼』(1963年)、今井正監督、佐久間良子主演の『越後つついし親不知』(1964年)、それに「スリラー形式の運命劇」とまで絶賛された異色中の異色とも言える社会派ミステリー、内田吐夢監督、三國連太郎、左幸子、高倉健、伴淳三郎等々競演の『飢餓海峡』(1965年)……どれもみな力強い文芸大作のような趣きのある忘れがたい映画化だった。
映画化にあたって脚本を担当した舟橋和郎(川島雄三と共同、『雁の寺』)、笠原良三(『越前竹人形』)、鈴木尚之(『五番町夕霧楼』『飢餓海峡』)、八木保太郎(『越後つついし親不知』、)といったすぐれたシナリオライターたちの力もあったのだろう。映画的な時間の流れにぐいぐいひきづられ、薄幸のヒロインの痛ましい人生や逃れられない過去の運命の絆に複雑にからまれて翻弄される人間模様に目がくらみ、魅せられ、圧倒された。
越前(福井県)の雪深い山村に住む竹細工師の死から『越前竹人形』ははじまる。後継ぎの一人息子、喜助(山下洵一郎)が細々と家業の竹細工(といっても主として手籠、花籠のような日用品ばかり)を作りつづけるが、そこへ「芦原の玉枝」と名のる齢三十路前と思しき——若尾文子の述懐そのままにちょうど30歳になるくらいの——女性が墓参に訪れる。父、氏家喜左衛門の「お世話」になったという手短かな挨拶。冬ごもりの地方の地味な頭巾と羽織、雪沓をぬぐと汚れた靴下が目に入る。しかし、どことなく垢抜けた美しさがただよう。雪の降りしきるなか、静かに墓参を終えて去って行くが、21歳の喜助は女のことがいつまでも気になって、春になるのを待ち兼ねて芦原に出かけ、遊廓「花見屋」に玉枝を探し出す。玉枝は風邪でちょっと咳をしているのだが、これがのちに椿姫のように結核になって死ぬ暗示にもなっているのだろう。
玉枝の部屋で、喜助は初めて目にする花魁姿の巧緻な竹人形に驚愕し、衝撃をうける。客としてなじんだ亡き父が玉枝に贈った渾身の傑作だった。この衝撃の一瞬から若い喜助は父のように(あるいはむしろ、父に負けまいとして)愛する女のために竹人形づくりに精進することを生き甲斐にするのである。遊廓の玉枝の妹分(中村玉緒)から玉枝が近くなじみの客に身請けされそうだと聞くや、大金を工面して先に玉枝を落籍して山奥の寒村のわが家に迎えることになる。わずかな荷物と玉枝をのせた素朴な荷馬車が竹林に沿った長い田舎道をやってくる。喜助は狂喜して花嫁を迎え、寺の和尚(殿山泰司)の取持ちで、その夜ただちにささやかながら婚礼の式を挙げる。
こうして玉枝をわが家に迎えた喜助は、初夜から竹細工の仕事に没頭するが、それは初めて玉枝が喜助の家を訪れた雪の日の彼女の姿を写し取ったもので、父に負けぬ立派な竹人形をつくってみせると意気込む喜助のまなざしに玉枝は彼を抱きしめたいという衝動を抑えるしかない。生き甲斐を得て仕事に励む喜助だったが、夜の共寝を拒絶し続けて玉枝を困惑させるばかりだ。喜助は3歳で死に別れて顔も知らない母への憧憬を玉枝に重ね合わせていたのである——という異常な愛の物語なのである。
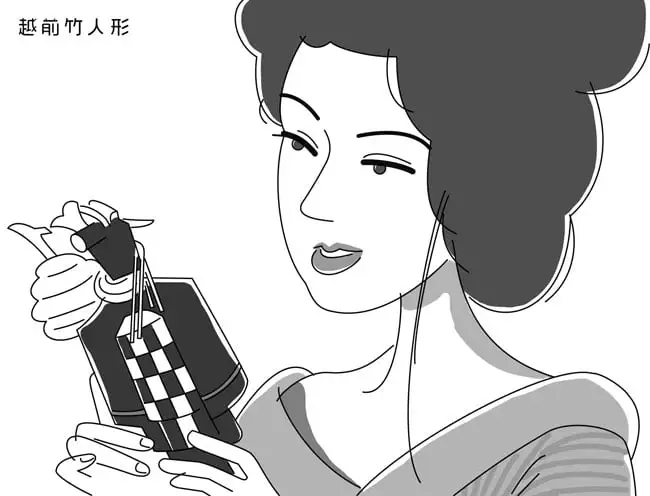
イラスト/池田英樹
私は映画『越前竹人形』を見たあと、吉村公三郎の書いたエッセイ集「あの人この人」(共同企画出版部)を読んで、吉村監督がこの映画を最後に「すんでのことで死ぬところだった」と書いているのを知った。「去年(1963年)の暮れの12月13日の晩に脳出血の発作で倒れた」というのである。「疲労の方は夏の仕事の『越前竹人形』いらいである。なにかにつけて左前の映画界のことで致し方ないかもしれないが、製作費と製作日数をできるだけ切りつめねばならぬことで、かなりの神経を使う。頭はなんぼ使ってもいいけれど、神経を使うことは健康に最もよろしくないんだそうだ。倒れたときも正月から製作にかかるはずの『傷だらけの山河』の準備で、心身を労していた。(結局この映画は山本薩夫氏がやったが、もちろんそれをみてはいない)発作の起こったのはちょうど小津安二郎監督の亡くなった翌日のことで、お通夜の晩だった」。
若尾文子は「吉村さんって、女性専門っていうと変だけど、女性映画を主に撮ってらした方ですね。何しろ、超ベテランの監督で、一番印象に残っているのは、絵コンテを前の日に全部書いてから現場にいらっしゃるんですね。普通は、絵コンテ通りに始めても、撮影の途中で、ちょっと違うってんで変えることがあるんですけど、吉村さんは絶対変えませんでした。前日に描いていらした通りに撮っておられたのを、私は覚えています」と言うのだが、このいかにも物に動じぬ超ベテランの大監督にも迷いの時はあったということなのだろう。助監督時代が長く、なかなか監督になれなかった。『母の想い出』というこんなエッセイがある。ちょっと長くなるけれども抜粋させていただこう。
「島津保次郎監督の『私の兄さん』(1934年)という映画の[助監督の]仕事の終わりぎわで徹夜がつづき、朝方、大森の奥の下宿へ帰って来たとき、机の上に電報がのっていた。
『ハハキトク スグカエレ』
私は1年近く家に帰っていなかった。私はその前年、はじめて[会社からチャンスを与えられて]短篇を1本撮っていたが、作品の出来は失敗で、また助監督に逆もどりしていた。両親は田舎住まいなので、この私の処女作を観ていない。私は自信を失い、前途が不安だった。給料も少なく貧乏していたが、両親に心配をかけるのが嫌だったから補助もたのまなかった。
母の入院している病院は彦根城の濠に沿っている。一時重態だったそうだが、私が着いたときは少し持ちなおして、わりあいに元気だった。
その夜は私はあまり広くない病院で母と枕を並べて寝た。母は「このごろ仕事の方はどうや」と、たずねる。
「うん……どうもうまくいかへん」
「ええ脚本を書かんと、監督になれへんのやそうやな。せいぜい勉強するのや。才能のないもんは、人一倍辛抱せなあかん」
あとにもさきにも、私の仕事について話したのはこれだけだった。母は私が自信をなくしているのを察していたらしい。
病状は急変し、3日目の朝、母は静かに息をひきとった。苦しみはなかった。ゆびがごつごつして荒れているので、手を組ませるのが容易でない。何か呆けたような気持で涙も出なかった。
冷たい遺体を毛布でつつみ、私が膝に抱いて父と一しょに、柏原村の家までハイヤーに乗った。母の体を抱いたのは生れてはじめてだったが、堅く重く、もう人の体の感じはしなかった。
「わしの方が先やとばかり思うてたが……」
父は糖尿病から肺結核となり、病状はかなり進んでいた。
東京へ帰ると、下宿の机のそばに母からの小包がとどいていた。この小包を駅へ出しに行ってから、母は猛烈な腹痛におそわれたのである。帰郷した私と入れ違いにこの小包がとどいていたのだ。小包は袷と羽織だった。栗のむしたのと、海苔の缶に入れたかき餅の揚げたのが出てきた。手紙も入っていた。私が筆不精なので、それをたしなめ、この小包が着いたらすぐに返事をよこすように書いてある。
私はおおかたは虫食いの栗を一つ一つかじりながら泣いた。冷たい雨が降っていた。私はこのことを後に[監督になって]『足摺岬』(1954年)という映画にとりいれている。
それから半年たった夏の日の夕方、父が亡くなった。暗い電燈の下にやせほそった父が寝ていた。枕もとに母の写真があり、父の顔を被った白い布の上にも、その写真にもなぜだか、たくさんの小さい虫が這っていた。
両親が亡くなってから4年目に、やっと私は正式の監督になることができ、その翌年の春、[母とは]字がちがうがやはり知子という名の娘と結婚した。」
これがたぶん『越前竹人形』の喜助が玉枝に重ね合わせた母のイメージなのかもしれないと思った。「あまり覚えていない。そんなに強烈な印象は残っていない」と若尾文子が言う(「若尾文子“宿命の女”なればこそ」、前掲)『越前竹人形』の山下洵一郎の演じる役がたしかにどこか稀薄な感じながら吉村公三郎監督の書く「想い出」の母親のイメージに似ているような気がしたのである。
抽象的で、あやうく気の抜けた幻想にしかすぎなくなりそうな(といっても若尾文子の演じる役にかぎってそんなことはあり得ないのだが!)ヒロインのはかなくもなまめかしい美しさが否応なく輝きはじめるのは、玉枝に母の愛の面影しか見ない純粋で透明な若い喜助の留守に悪魔のように現れた昔の遊廓のなじみの客(演じるのはあくどく巧妙な名優、西村晃である)に誘惑され、乱暴されて(「若尾文子 “宿命の女”なればこそ」の若尾文子ふうに言えば「昔のおなじみさんだからっていうんで、ちょいと気を許していると、あっという間に乱暴する」)、そして不幸にも妊娠してしまい、堕胎せざるを得なくなり、相談相手を求めて真夏の炎天下をひとり歩きまわる。白黒画面の絶望的な白く長い道。陣痛がはじまり、腹痛にこらえきれず、川べりの小さな渡し舟を見つけて倒れ込むように乗り込んだまま失神し、流産してしまった玉枝は、めざめたとき、神の助けのように老船頭(中村鴈治郎)が臨機応変の処理で流産した胎児を川に流してくれたことを知る。
憔悴しきった凄惨な姿で家に帰った玉江を喜助はもちろんやさしく迎えて介抱するが、衰弱した彼女の身体は回復することなく、結核に冒され、死を迎える。
すでに伝説化していた越前竹人形の制作も途絶え、物語は終わる。「恋い、慕い、求めながら、妻であるその肌にふれず……雪国に哀しく描かれる異常な純愛!」というのが映画の謳い文句であった。

イラスト/野上照代
山田宏一
やまだこういち●映画評論家、翻訳家。ジャカルタ生まれ。東京外国語大学フランス語学科卒業。1964~1967年にパリ在住。その間「カイエ・デュ・シネマ」の同人となり、ジャン=リュック・ゴダール、フランソワ・トリュフォーらと交友する。

