映画評論の大家である山田宏一さんに、毎月、とっておきの映画を「2本立て」で紹介していただくコーナーです。今回は特別に1本立てで、加藤泰監督、中村錦之助主演の『真田風雲録』を取り上げます。1963年に公開された時はまったくの不入りでしたが、安保闘争に情熱を傾けていた若者たちのあいだで熱狂的に受け入れられました。この異色作の成り立ちをひもときながら、監督の加藤泰の頑固ともいえる映画作りの真相と本作の魅力について詳細に語っていただきました。
紹介作品
真田風雲録
製作年度:1963年/上映時間:100分/監督:加藤泰/原作:福田善之/脚本:福田善之、小野竜之助、神波史男/撮影:古谷伸/音楽:林光/出演:中村錦之助、渡辺美佐子、ジェリー藤尾、ミッキー・カーチス、千秋実、佐藤慶、原田甲子郎など
福田善之さん死去/劇作家『真田風雲録』…という訃報が新聞に出て、加藤泰監督、中村錦之助主演による映画化を思い出し、なんとビデオ(DVD)も出ているというので、どうしてもまた見たくなった。
「『真田風雲録』など1960年代を代表する戯曲で知られる劇作家・演出家の福田善之(ふくだ・よしゆき)さんが8月21日、肺炎のため死去した。93歳だった。(……)真田十勇士の活劇に60年代安保闘争の学生たちを批評的に重ねた『真田風雲録』は1962年に初演、翌年映画化された。(……)」(「朝日新聞」8月24日朝刊)
私は舞台のほうは観ることができなかったけれども、加藤泰監督の映画『真田風雲録』(1963年)は公開から数年後にすでにカルト(崇拝)の対象になっていた異色の名作として熱狂的な雰囲気のなかで——小さな名画座だったか自主上映会だったか、愛好家だけが集まってちょっと変わったアクの強い個性的な映画を鑑賞するという環境で——気を引き締めて見た記憶がある。メチャクチャ面白かった。ミュージカル仕立ての異色の時代劇である。
●中村錦之助主演作の中で際立つ異色チャンバラ時代劇
天下分け目の関ヶ原——慶長5年(1600年)9月15日、関ヶ原で石田三成(豊臣秀吉に仕えたので、当然ながら豊臣方)の西軍と徳川家康の東軍とが天下を争った名高い合戦である。この世紀の戦いのさなかに戦災不良孤児たちが戦場泥棒をしながらたくましく成長、勇将・真田幸村に率いられ、まさに勇将の下に弱卒無しとはこのことか、「真田隊軍歌」(福田善之作詞、林光作曲)を高らかに誇らかに大合唱しながら行進するのだ。
〽人生たかが50年
夢まぼろしのごとくなり
かどうかは知っちゃいないけど
やりてえことをやりてえな
てんでカッコよく死にてえな。
私が何回か見た小さな名画座(だったか、サークルだったか)の上映回では和気あいあい、お客もいっしょに大合唱になったこともある。
60年安保闘争は1959〜60年、日米安全保障条約改定に反対して行なわれた国民的規模の運動。1960年5〜6月には連日デモ隊が国会を包囲したが、条約は改定された。1970年にも条約延長への反対運動が行なわれた。全学連(戦後結成された全日本学生自治会総連合)も1960年前後から分裂、学生運動は多様化する。
キネマ旬報「日本映画作品全集」の『真田風雲録』の項にも「60年代安保[闘争]で闘った青年たちの思想と感情と行動をマジメさと軽薄さの混沌のうちに描いた福田善之の戯曲の映画化」とある。あちこちであまりにも60年安保闘争の挫折をテーマにした映画化として語られすぎた加藤泰監督の『真田風雲録』であったが……。
戦国時代の武将、真田幸村の家臣で大阪冬の陣、夏の陣に、大阪方のために大活躍した10人の勇士がいて、その武勇伝は明治末から大正初期にかけて発行された講談本「立川文庫」によって創作されたものだという。忍術の猿飛佐助、霧隠才蔵、怪力の三好清海入道、三好伊三入道、鎖鎌の由利鎌之助、それに筧十造、海野六郎、望月六郎、穴山小助、根津甚八とそれぞれ得意技の武芸で人気を呼んだ。すべて架空の人物のようだが、小学館「日本国語大辞典」には猿飛佐助だけは「戦国時代の忍術者として伝えられている人物」としながらも、「甲賀流の書にその名が記されているが、実在したかどうかは不明。大正初期に大阪赤本の講談豆本でその武勇伝が書き広められ、真田十勇士の1人として世にもてはやされた。猿飛は「西遊記」の孫悟空にあやかったといわれている。大阪成象堂の武士道文庫に伝記がある」とあやふやに明記されている。
歌舞伎の名門から映画入りして、チャンバラ時代劇の若きスターになり、錦ちゃんの愛称で親しまれた中村錦之助の魅力的な忍者猿飛佐助だった。1960年代の中村錦之助はアイドル的な錦ちゃんから一皮も二皮も剥けて、筋金入りの意欲的な錦之助主演映画が次々につくられた。1961年には伊藤大輔監督で『反逆児』(原作は大佛次郎の戯曲「築山殿始末」)、62年には加藤泰監督で『瞼の母』(原作は股旅ものの第1人者として知られた長谷川伸の同名の戯曲)、田坂具隆監督で『ちいさこべ』2部作(原作・山本周五郎、脚本・鈴木尚之/野上竜雄/田坂具隆)、内田吐夢監督で『宮本武蔵・般若坂の決斗』(原作・吉川英治、5部作の1本)、63年には今井正監督で『武士道残酷物語』(原作・南条範夫「被虐の系譜」、脚本・鈴木尚之/依田義賢)、加藤泰監督で『真田風雲録』(原作・福田善之、脚本・福田善之/小野竜之助/神波史男)、山下耕作監督で『関の弥太ッぺ』(原作・長谷川伸、脚本・成沢昌茂)、64年にも田坂具隆監督で『鮫』(原作・真継伸彦、脚本・鈴木尚之/田坂具隆)、今井正監督で『仇討』(原作/脚本・橋本忍)……といった中村錦之助の名演が光る見ごたえある力作ぞろいである。『真田風雲録』はそんな力作群のなかでも異色のドタバタ調のチャンバラ時代喜劇だった。加藤泰とは何者か? 1970年には「遊侠一匹 加藤泰の世界」(山根貞男編、幻燈社)、95年には「加藤泰映画華」(権藤晋編、ワイズ出版)という加藤泰研究書が出版されているので、以下、この2冊から加藤泰と関係者の言葉を引用しつつ私なりに紹介させていただくと、そもそも加藤泰監督の劇映画の第1作からして、吉川英治原作による『剣難女難』(前篇・女心伝心の巻/後篇・剣光流星の巻、1951年)という「チャンバラ映画への初心とウンチクを、チャンバラにつぐチャンバラへ、唯一筋に、何の衒いもなく傾けて、脇目もふらず撮りあげたと言える」(と加藤泰監督自身、のちに率直に告白している)連続活劇的2部作だった。主演はまさにチャンバラ時代劇のために生まれたような細面の端整な顔立ちをした美男子、黒川弥太郎だった。
「中村錦之助氏との出合いとなった仕事」は1957年の『源氏九郎颯爽記 濡れ髪二刀流』(原作・柴田錬三郎、脚本・結束信二)。監督といっても、東映という映画会社の社員にすぎないから、もちろん「会社命令」で中村錦之助と組み合わされた監督の1本目である。「だが、僕にとっての此の仕事の意味は、自分がうちこんでいける登場人物を1人、見つけたことである。それは主人公の源氏九郎に許嫁の青年を討たれ、彼を敵と狙いながら、どうしようもなくひかれてゆく、織江という女(田代百合子が演じた)だったのである。人というものは、そのような状況に置かれて苦しむ時こそ、真実の光を放つように思えて仕方ないし、そのような女とのかかわりあいで見てこそ、源氏九郎というお化けみたいな主人公にも血が通ってくると僕には思えて仕方がない。作品の出来、不出来は別にして、僕はそのような思いをこめて、この映画を撮りあげた」(と加藤泰監督は熱っぽく告白する)。次いで続篇『源氏九郎颯爽記 白狐二刀流』(1958年)を加藤監督自らの脚本で映画化、錦之助との組合わせもうまくいって会社側にも認められたかと思いきや、「試写を見られた映画会社(東映)の大カントクが『何ですあのシャシンは。不真面目きわまる。折角のスター中村錦之助をワヤ(めちゃくちゃ)にさせるつもりですか』と激怒され、撮影所長以下に訴えられたというので、『いや、それでしたら、皆、僕が悪いのです。つまり、この映画のお話も、東映時代劇ではお馴染みの尊皇、攘夷、佐幕の浪人、藩士、武家娘、奉行所役人、豪商、公卿、公卿娘等々で運ばれるのですが、今回初めて自分の脚本で撮る事になった僕は、それらの人物達に、それまでの型や約束を破棄して、一体彼らの収入はどれ程で、どんな暮しで、どんなものを食って、何が嬉しくて、何が悲しくて、何が腹立たしいのかというようなことを、まず考えながらやってみたのです』とまたも言い訳したものの、果然、その結果は、その頃の東映時代劇の常識から見て、まことに不真面目きわまる人間達が、不真面目きわまる考えで、不真面目きわまる行為を働く映画が出来てしまったのである」と後悔先に立たずの開き直り。
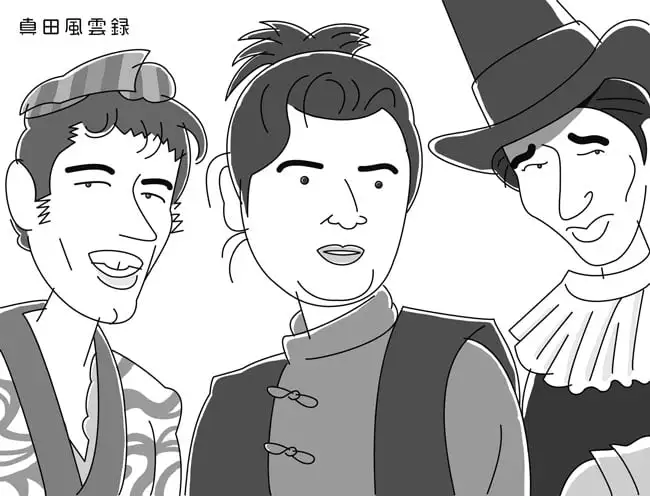
イラスト/池田英樹
●世間から弾き出された若者たちのドタバタな青春を描く
さらに1958年の『風と女と旅鴉』(脚本は成沢昌茂で、これは傑作と言っていい感動作だった)の撮影のときには、製作部から「君は中村錦之助にもメークアップをするなと言ったそうじゃないか」と責められて、静かに「ドラマの役が要求するメークアップをしようと言うことです。誰も彼も、男も女も、まるで壁のように顔料を塗って、ゲジゲジかミミズのように眉をかいて、雨よけの庇(ひさし)のような眉毛をつけて、枚方(ひらかた)の菊人形が仮装行列に来たようないでたちで芝居するのはやめようということです。従って、特に役がメークアップを要求しなければ素ッピンということに」とまたも開き直りの主張、「君は録音技師に、水音の烈しい谷川沿いの山道のロケーションでセリフの沢山ある長いショットをシンクロ(同時録音撮影)でやると言って聞かんそうじゃないか。そんな悪条件の無理なシンクロで、キレイな音がとれるものか」と責め立てられるに至って、「どうして何時までも、そんな原始的なことが問題になるのです。1930年に発声映画(トーキー)が実用の段階を迎えてからでも、すでにもう30年近くになるのですよ。僕らが今問題にするのは、そのドラマのショットがどういう音を要求するか。つまり……」と弁解しつつ抵抗するものの、さらには「君は錦之助にキッスをやらせるのかッ。その結果がドーイウコトニナルカ。すでに全国の錦ちゃんファンからは、錦之助のキッス反対の投書が殺到しとるのを知らんのかッ」とどなられる始末で、「轟々たる非難と心配の声をかきわけながら、やっと撮りあげたのが、この1篇である」と加藤泰監督はたぶん空威張りではなく胸を張って書いている。「それまでは、どちらかと言えば従順で、よく言うことを聞く方の新進監督であった僕が、どうして急に、そんな分からずやの頑固者になったのでしょう。訳はカンタンです。此の映画に出てくる奴が、皆、僕のうちこめる奴ばかりだったからです。まともな世間から弾(はじ)きだされた奴。卑怯な奴。ずるい奴。そのくせどこか底のぬけた気のいい奴。小悪党達。つまり、そんな奴らのお話の映画なら、僕は妙に自信が持てたのです。」
1962年の『瞼の母』(「大好きな」長谷川伸の原作から加藤監督自身が脚本を書いた)もいい作品だったが、15日間という限られた撮影で「2度とすまいと誓った早撮り」であったものの、新進監督倉田準二の協力のおかげで「僕は手を抜くことなく全力投球が出来た」という。そして1963年の、中村錦之助とは5本目の組み合わせになる『真田風雲録』で反逆児加藤泰監督の鬱憤(うっぷん)は積もりに積もって爆発したかのようである。いわく、「原作の福田[善之]氏は60年安保闘争の挫折を通じて書いているのですが、それを作品化する意図は作家の方にあるわけだけれど、果たして[そのような意図が]僕にあるかといえば、ないんです。ただ、この映画はこの映画のスタイルなりの手法があるわけだから、ぼくなりの見解からやってみようということになった」というわけである。「『真田風雲録』は60年安保の挫折を置き換えたわけだけど、加藤監督はどっちかというと批判的で、革新内のヘゲモニー(主導権)争いみたいなところにはもっていかないようにしようと言ってました。むしろ、佐助とお霧の関係、あるいは青春像として捉えようとしていましたね」とチーフ助監督の鈴木則文も語っているように、青春ドタバタ喜劇(とまではきめつけなくても、加藤泰監督ごのみの、「僕のうちこめる奴」の、「まともな世間から弾きだされた奴、卑怯な奴、ずるい奴、そのくせどこか底のぬけた気のいい奴、小悪党達、そんな奴らのお話の映画」)としての面白さのほうが今見てもきわだっているような気がする。ロカビリー歌手のジェリー藤尾やミッキー・カーチスの珍優ぶり、喧嘩早いが純情なかわうその六や鎖鎌代わりにギターを持った伴天連スタイルの由利鎌之助の悲しさやオトボケぶり。霧隠才蔵が女で(舞台でも演じた渡辺美佐子)、その名もお霧、浮浪児の頃から猿飛佐助に恋をして、恋仲になって、身ごもって、家庭を築くという小さな幸福を夢みるが…というエピソードも感動的だ。やがて真田隊は全滅、大将の真田幸村(千秋実)も敵の死体にけつまずいて、その槍に自ら突き刺さって「てんでカッコ悪く」戦死。猿飛佐助だけが強力な敵方の伊賀流忍者、服部半蔵(原田甲子郎)と死闘を交えるが決着がつかず、最後はひとり、兵(つわもの)どもが夢の跡さながらの古戦場・関ヶ原をいずこへとも知れず去っていくのである。
「どうしようもなく、ネバってしまった仕事」であったが、映画は壊滅的にコケて、「関西地区の東映の小屋(直営館)では6日間で引っ込められてしまった」という。「この映画は当たりませんでしたね。学生さんや映画サークルの人には大変受けましたが、当時の撮影所長から東映始まって以来の不入りだと言われたものです」とキャメラマンの古谷伸も残念そうに述懐している。
日本映画史に異才(と言うべきか)加藤泰監督登場のエピソードを語るだけで長々とくどい紹介になってしまったが、その後、東映任侠やくざ映画の頂点をきわめた1本『明治侠客伝・三代目襲名』(1965年)、『瞼の母』につづく中村錦之助主演による長谷川伸の世界の映画化の集大成とも言うべき股旅映画の傑作『沓掛時次郎 遊侠一匹』(1966年)を発表。中村錦之助は東映専属を離れてフリーになり、歌舞伎座公演、テレビ出演などをへて、1972年に萬屋錦之介と改名(萬屋は父・中村時蔵の母方の屋号)、萬屋一門の総帥として活躍することは周知のとおり。
といったところで、「2本立て」の2本目の外国映画はイギリスからハリウッド入りしたJ・リー=トンプソン監督のストーカー・スリラーの傑作『恐怖の岬』(1962年)を紹介するつもりだったが時間切れで締切りに間に合わなくなってしまった。失礼致します…。

イラスト/野上照代
山田宏一
やまだこういち●映画評論家、翻訳家。ジャカルタ生まれ。東京外国語大学フランス語学科卒業。1964~1967年にパリ在住。その間「カイエ・デュ・シネマ」の同人となり、ジャン=リュック・ゴダール、フランソワ・トリュフォーらと交友する。

