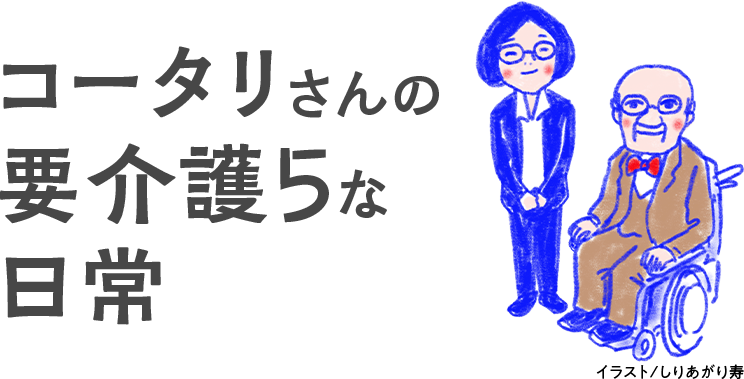<毎月第2・4火曜更新>2011年、突然のくも膜下出血により要介護5となった神足裕司さん(コータリさん)と、妻の明子さんが交互に綴る「要介護5」の日常。介護する側、される側、双方の視点から介護生活を語ります。
連載第56回「理想の家」
![]()
人は「今の自分」を基準にしか家を考えられない。
神足裕司(夫・介護される側)
家を建てた頃は子育てに配慮した模範解答の家だった。
「家は3度建てると、ようやく納得のいく家になる」
そんなもっともらしい言葉を、住宅展示場か何かで聞いた覚えがある。3度も家を建てられる人間は、よほど金と運と体力に恵まれているか。あるいは、よほど懲りない人だ。
ボクは36歳のころ、親の土地に家を建てさせてもらった。当時としては、かなり考えた家だったと思う。雑誌も読み、モデルハウスも回り、その当時は車をたくさん停められる家。
営業マンの話も半分だけ信じて「これ以上はない」と自分なりに納得して建てた。
が、その「納得」は、元気な体が前提だった。
体が思うように動かなくなってから、この家を見る目は一変した。階段は急だし、廊下は長いし、ドアノブはやたら遠いし、スイッチは、なぜこんな位置にあるのかと腹が立つ。家というのは、元気な人間のために、元気な人間が考えてつくるものなのだと、今さらながら思う。
介護のことなんて、ほとんど考えていなかった。せいぜい「いずれ義父母と同居するかもしれない」その程度の想定で、両親用に1部屋ずつ和室を設けた。
年寄りは畳がいい。和室は落ち着く。日本人の心だ。全部、思い込みだった。
実際に同居してみて、しばらく時が経ったこの数年。90歳代の親にとって和室はとにかく不便だ。
立ち上がれない。布団から起き上がれない。畳に足を取られて転びそうになる。
「年寄りには和室がいい」そう言ってきたのは、たいてい元気な中年だ。自分が年寄りになった姿を、想像できないまま。
年をとると「風情」より「安全」、「伝統」より「実用」その順番が、はっきり逆転する。
家を建てた頃、子どもたちはまだ小さかった。だから風呂は広めに。階段も少し余裕をもたせて。リビングと玄関は2枚の開き戸に。トイレも、まあまあ広めに。
当時は「いい父親の家」だったのだと思う。子育てに配慮した、模範解答の家。
皮肉なことに、車椅子生活になった今、その「子育て仕様」が助けになる場面がある。広めのトイレ。開き戸。無駄に広い風呂や玄関。
計算していなかったバリアフリー。たまたま当たった宝くじみたいなものだ。
いまは平屋が流行りだという。「ワンフロアで完結する暮らし」「老後も安心」どの住宅メーカーも、同じ言葉を並べる。
実際、我が家も2階は使っていない。義母は2階から1階へ。ボクも書斎だった1階の部屋で寝起きしている。2階は、ほぼ「思い出置き場」だ。
平屋の便利なところは、上り下りがないこと以上に、生活がごまかせないことだと思う。逃げ場がない。誰かが動けば、音でわかる。倒れれば、すぐ伝わる。
2階にいれば聞こえないことが、平屋では全部、聞こえてしまう。それは不自由でもあり、介護においては、正直でありがたい。
介護というのは、立派な設備より最新の住宅性能より「気づける距離」のほうが、ずっと重要だ。
もし次に家を建てることがあるなら、たぶん平屋を選ぶ。でも、また同じ失敗をする気もする。
なぜなら、人は「今の自分」を基準にしか家を考えられないからだ。若いときは、老いを想像しない。元気なときは、弱る自分を信じない。介護する側のときは、介護される側の気持ちがわからない。
「3度建てないとわからない家」というのは、設計の問題じゃない。人生を3回やり直さないと、わからないという意味なのだ。
ボクはいま「介護される側」として家を見ている。この視点は、元気な頃にはなかった。というより、あえて見ないようにしていた。
家は夢を語る場所ではなく、現実を引き受ける器なのだと、ようやくわかった。あの頃400万円くらいの上乗せをしてエレベーター付きの家を建てる気になっていただろうか。どこを削れば予算を数万円落とせるか考えていたのに。
今日もボクは1階の部屋で目を覚まし、ゆっくり体を起こし、車椅子に移り、この家の中を移動する。
考え抜いた家のつもりだった。けれど、歳月が経つとすみやすい条件は違ってくる。しかし、不思議なことに思いもよらない部分が、生きることをあきらめずにいられる家であった。
少なくとも、住宅展示場の営業マンよりは、この家のことを、今のボクのほうがよく知っているのだから、使いやすさもいたらないところもわかる。
介護が必要なために建てられた家は本当に幸せに見える家に感じるのだろうか。そんな気がしないのは何故だろう。

2枚扉で大変便利な玄関とリビングのドア。(写真・本人提供)
2月24日更新です。
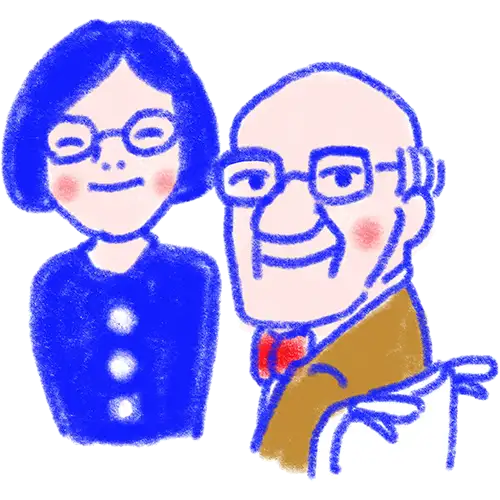
神足裕司
こうたり・ゆうじ●1957年広島県生まれ。大学時代からライター活動を始め、グルメレポート漫画『恨ミシュラン』(西原理恵子さんとの共著)がベストセラーに。クモ膜下出血から復帰後の著書に、『コータリン&サイバラの介護の絵本(文藝春秋)』など。
神足明子
こうたり・あきこ●1959年東京都生まれ。編集者として勤務していた出版社で神足さんと出会い、85年に結婚。1男1女をもうける。