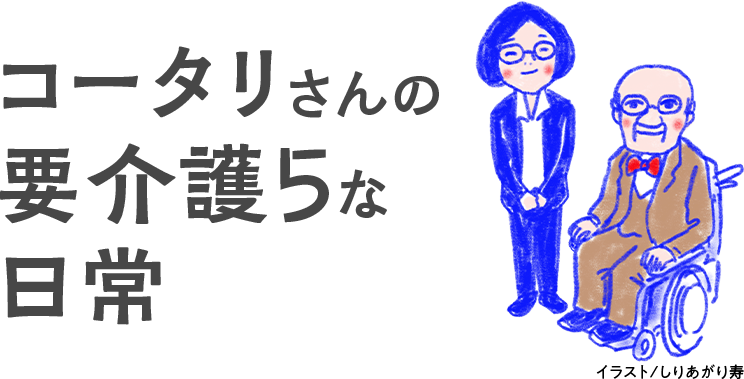<毎月第2・4火曜更新>2011年、突然のくも膜下出血により要介護5となった神足裕司さん(コータリさん)と、妻の明子さんが交互に綴る「要介護5」の日常。介護する側、される側、双方の視点から介護生活を語ります。
連載第41回「忘れられない編集者」
![]()
ボクは古いタイプの物書きなのかもしれない。
神足裕司(夫・介護される側)
クモ膜下出血の後遺症で要介護5の体になってからも色々な編集者にお世話になった。
先日「九十歳。何がめでたい」を日本に帰ってくる飛行機の中で見た。
5月にTBSで頂いた舞台挨拶付き試写会にも行ったので鑑賞するのは2回目だ。試写会には、もうすぐ九十歳になろうとしている義母も一緒だった。
この映画は作家の佐藤愛子先生が一度絶筆されてから新しく連載を始め、それが本になり、旭日小綬章受章を受章するまでの実話だ。時代に乗り遅れてしまった昔ながらの編集者と作家のやり取りがボクにとってはリアルで懐かしい。物書きの端くれだったボクもたくさんの編集者にお世話になった。

映画「九十歳。何がめでたい」(写真・本人提供)
編集というのは、雑誌や本を企画し、出来上がるまでの制作全体の管理をする仕事だ。編集者が執筆もするイメージが一般の方々にはあるかもしれないけれど、普通は作家やライターが文章を書き、編集者はまさしく「作品を編み上げる」仕事をする。大体が「こういう企画があるんですけど」と出版社の編集担当が持ってくることになる。いや書き手が「こんなことをしたい」って売り込んだりもすることもある。が、その企画が決まれば作家やライターが書き、編集者が時にはその原稿を構成したり文字数を合わせたり、事実関係の間違いを発見してくれたりして文章は成熟していく。そして作品として世の中に出る。
ボクがクモ膜下出血の後遺症で要介護5の体になってからも色々な編集者にお世話になった。本を何冊も出してもらったし、連載も頂いた。病気になる前のボクの担当は相当大変だったとは思うが、違った意味で病後のボクの担当もそれはそれは大変だろう。今のこの連載の編集者だって大変だ。締め切りはいつも間に合わないかギリギリ。誤字脱字も多いだろう。意味が通じないし、、、と思ってるかもしれない。編集者がいてボクはいる。
そして映画を見ながら一人の人物の顔が浮かんでならなかった。
古くからの友人であった。フリーの編集者で色々な出版社で仕事をしていた。彼も取材をして週刊誌などの記事を書いていたが「編集の仕事の方が向いているのになあ」と思っていた。
彼は、ボクが病気になってから思ってもみなかったくらい面倒を見てくれた。友人や知人が色々な方向でボクを助けてくれていたが、彼のサポートはある種特別だった。「そんなに仲良かったっけ?」と他の編集者に聞かれたぐらい、病後のボクを支えてくれた。
動けなくなってしまったボクがものを書けるように、あれやこれや面倒を見てくれた。時には「そこまでしてくれなくていいよ」というくらい動き回って先回りして、なるべく良い方向に向くように計らってくれた。彼の動きを見ていると昔の編集者を思い出す。その映画に出てくる編集者のような感じなのだ。何が好きか、どうやったら車椅子で行けるか、生活の一部まで共にするかのように過ごした。
先にも話したが、編集者は誤字脱字を校正者と一緒に直したりもする。彼とはよく揉めた。直しの入った原稿が「ボクの文章のテンポと違った句読点の打ち方をした」と怒ったことがあった。「そこに「、」を入れるのおかしいですよ、神足さん」
「いやボクはあえてそこに入れてるの」
馬鹿馬鹿しいことでも彼にはそんなことも言えた。
「神足さんは昔から「ここは後でこんな感じで書くからそれまで空けといて」とか編集者泣かせの書き手なんだから。そんな「、」であれこれ言いますか???」と言われたりもした。
言いたかったから仕方ない。書き手として譲れない「、」なんだと。
そんな彼も3年前の12月、脳溢血に襲われた。いつもはスケジュールを守る彼が連絡もなく原稿の締め切りに遅れた。おかしいと思った雑誌の編集者が家へ見に行ったら倒れていたという。救急車で病院へ運ばれた時、すぐに家にその編集者から我が家にも電話があった。
「彼の家族に連絡を取りたいんだけど神足さんなら知ってるかと思って」すぐにボクの代わりに妻が病院へ駆けつけた。朝が来ても安心できる電話はない。
肉親でなければ手術のサインもできないという。それからボクらは彼の親族探しに悪戦苦闘することになるのだけど、彼の担当編集者がやっぱりいい仕事をした。彼の大学の知人を探し当て高校の同級生を探した。高校の同級生なら実家を知っているだろうと。
その同級生から連絡先を聞くことができたんだという。結婚もしていない一人暮らしの彼のことは、何も知らなかったんだなあと愕然とした。確か弟さんと妹さんがいたはず。そのぐらいしか知らない。仕事の人なんだから当たり前だが、彼はボクのことを何でも知っている勢いだったにもかかわらずだ。
ボクも佐藤愛子先生には及ばないが、古いタイプの物書きなのかもしれないなあ、と映画を見て思った。
今の家を建てた時、まだ編集者が自宅に原稿を取りに来ることがある時代だった。引っ越してくる前のテラスハウスの一階は、居間と食卓が一緒になった広い部屋だったので、原稿を取りに来た編集者が、まだ小さかった子供がご飯を食べたりお風呂に入ったりバタバタの中で待っていてくれた。だから家を建てる時の妻の唯一の希望が「一階にボクの書斎部屋を作ってほしい」だった。家を建てた頃からバイク便ができ、インターネットが普及して編集者が原稿を取りに来ることはめっきり減った。Enterをピッと押せば編集部のパソコンに転送される。
そうそう、ボクは病気になって左側が麻痺してしまったので左手も使えない。そのためパソコンで原稿を書くことができなくなった。原稿用紙に書く。ただでさえも汚い字がわかりずらい文字になって苦労しているが、原稿を起こしてくれている。
そのボクが書いている原稿用紙を作ってくれたのも彼だ。
「神足さん、芥川龍之介が作ってたとこと同じところで作りましょうよ。神足裕司って名前も入れましょう。少しでもやる気になってくれますか?」
おかげで一生使っても使いきれないほどの原稿用紙が家にはある。注文の単位を違えたらしいけど。万年筆も神田で修理してきてくれた。ボクの好みを読み切っている。
古い古い編集者の忘れられない話である。

忘れられない編集者と一緒に(写真・本人提供)
![]()
裕司は倒れても書くことを許されましたが、サポートは必要でした。
神足明子(妻・介護する側)
「明子さんは過保護なんじゃないですか?」と言われるぐらい心配で何重にも予防線を張ってしまいます。
裕司の仕事を手伝うことになるとは思ってもいませんでした。
昔の私は同じような業界で働いてはいましたが、前回の裕司の原稿にもあったように、基本裕司は物書きで、私は書くことがメインでない仕事、どちらかといえば出版社では編集のような仕事をしていました。似てはいましたが、全く違う仕事です。
結婚する前、リスペクトはしていましたが「今どんな仕事をしているか」はよくわかっていませんでした。結婚するときに「仕事はやめる」と言ってみんなを驚かせましたが、きっぱりやめて家庭に入りました。
ますます裕司がどんな仕事をしているかよくわからなくなっていました。月曜日は東京のテレビ局、金曜に大阪のテレビ局へ行き、その後広島のテレビに出演して日曜に帰ってくる。そんな大まかなスケジュールしかわかっていませんでした。マネージャーのような方や、各会社の編集の方のほうが何十倍も裕司を把握していたと思います。
裕司が倒れ、それでも書くことを許されたとき、どうしてもサポートが必要でした。動けない・話せない裕司を取材に連れていくのです。いつの間にか「私が一緒」が当たり前の仕事の仕方になっていきました。
取材先ではもちろん本人も聞いているのですが、質問は私がすることが多いです。時間が許せばその場で裕司の聞きたいことを聞きますが、そうでない時は「後でご連絡させていただいていいですか?裕司が伺いたいことをまとめてお聞きしたいのです」そう言います。
すらすら取材先のことを頭の中でまとめて書くこともありますが、どうしてもうまくまとまらない時には取材時の写真をテーブルに並べたり、スライドショーのようにテレビへ映し出して状況を思い出すところからやり直すこともあります。写真を見ているうちに頭の中の記憶がパズルのようにつながっていくのでしょう。文字がスムーズに出てくるようになります。まるで裕司の脳が動き出すのを見ているような気がしてきます。
現場に連れていくことも、眠らないで原稿を書くように見張っているのも、脳がそのように動き出すことを見守っているのも。取材に行った時その内容を忘れないように録音したり録画したり。秘書である私の役目はわりと大変です。
前回出てきたかけがえのない編集者の方にも「明子さんは過保護なんじゃないですか?」と言われるぐらい心配で、何重にも予防線を張ってしまいます。録音しておいた方がいいんじゃないか?もう一回やり直した方がいいんじゃないか?
ほとんどが使わなくていいのですが、念のためです。「原稿が書けなかったら困るじゃない」そう思ってしまいます。
その編集者の彼と私はよく喧嘩しました。「そんなことしないてもいい」とよく彼には言われましたし、こんなこともありました。
「パパはこう言っています」「いや、神足さんにはこうして欲しいんです。ホントに伝えてくれましたか?」「伝えてますよ、でもそう言ってます」「ホントですか?おかしいなあ」
「神足さんがそういうはずない」という彼の考えと「だってそう伝えてと言われたんだもん」の私。なんだか恋人の取り合いをしているような、そんな気分にもなります。
仕事のことは彼の方が知っているんですから。新参者の私がやり方を変えておかしなことになったら大変なことなんだろうなあ、と何回も思いました。裕司と一緒に仕事をしたことなんてほとんどない私ですから、実際彼のいう話の方が正しいのでしょう。「わかりました、もう一回聞いてみます。それでいいか」そう仕切り直します。
彼が絡んでいない仕事でも「あれ読みました。よかったですよ」なんて言ってもらったら、私はホッとしたりもしたのです。その日は機嫌だってよくなるぐらい。
単行本が出来あがれば彼と二人で「乾杯だね」なんて一緒に喜んだりもしました。用事もないのに連絡をくれて「来週行きますよ」となんでもないのに来てくれて、そんなのがとても「ありがたいなあ」っていつも思っていました。
彼の誕生日にクリスマス会&忘年会&誕生日会をやるのがその年の最後の集まり。そして一週間もたつと、新年が来て新年のご挨拶と言ってはお酒を持ってやってくる。そんな当たり前が数年前からなくなりました。
彼が倒れてしまい一人暮らしなので施設に。春に行けば「今年の神足さんの花見はどうするんですか?」と心配してくれる。夏に行けば「誕生日会はどうするのか?」と。
もうすぐ彼の誕生日がやってくるのでお見舞いに行こうと裕司と話しています。今はこちらが行かなければ会うこともできない。彼はいつ行ってもパパの心配をしてくれまう。「仕事はうまくいってるのか?」「具合はどうなのか?」喋れないパパを気遣ってなるべく話してくれようとします。パパにとって大切な人なんだなあと二人をみていて思うのです。
病気を患ってしまった二人の空間にお互いを心配している空気が流れます。それを感じていつもジンときてしまいます。
いつか我が家でご飯が食べられたらいいなあと思います。車椅子二台を一緒に押せるようなものを作ってほしいです。二人を新宿御苑のお花見に連れて行ってあげたいなあ。

編集者の彼と(写真・本人提供)
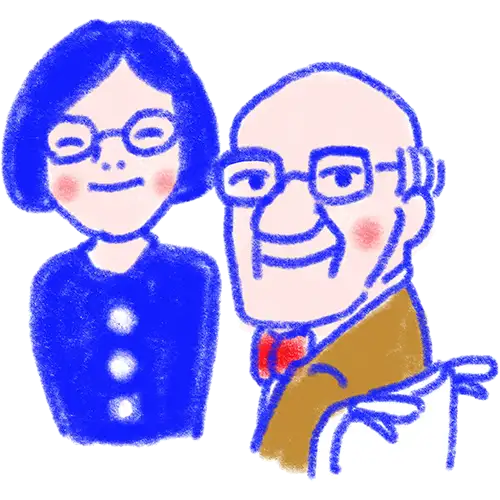
神足裕司
こうたり・ゆうじ●1957年広島県生まれ。大学時代からライター活動を始め、グルメレポート漫画『恨ミシュラン』(西原理恵子さんとの共著)がベストセラーに。クモ膜下出血から復帰後の著書に、『コータリン&サイバラの介護の絵本(文藝春秋)』など。
神足明子
こうたり・あきこ●1959年東京都生まれ。編集者として勤務していた出版社で神足さんと出会い、85年に結婚。1男1女をもうける。