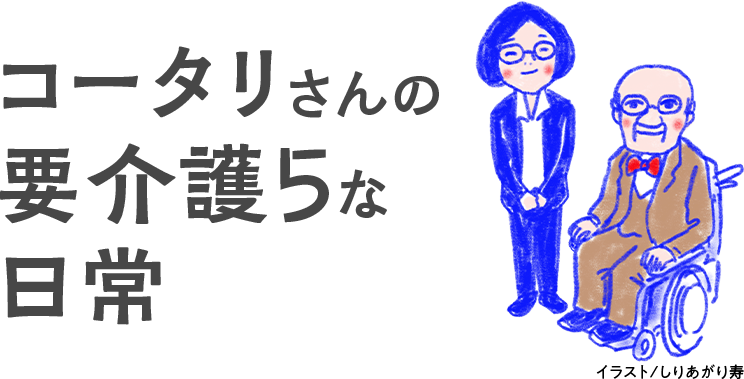<毎月第2・4火曜更新>2011年、突然のくも膜下出血により要介護5となった神足裕司さん(コータリさん)と、妻の明子さんが交互に綴る「要介護5」の日常。介護する側、される側、双方の視点から介護生活を語ります。
連載第42回「香港の福祉用具の展覧会」
![]()
日本の優れた福祉用具は世界でも活躍している。
神足裕司(夫・介護される側)
日本で行われている展覧会と一番違うところは「子どもがたくさん来ている」ことだ。
香港で楽齢科技博覧曁高峰会(GIES)が11月21日から24日にあった。楽齢科技博覧曁高峰会は日本で言えば国際福祉機器展(H.C.R.)みたいなものだ。
香港特別行政区政府と香港社会福祉協議会が共同で開催し、香港科技園区公司が行うプロジェクトで、香港で最も大規模な福祉系の展覧会と聞いた。

楽齢科技博覧曁高峰会(写真・本人提供)
楽齢科技博覧曁高峰会は2017年に開催されてから現在まで、色々な最新の商品や大学で研究中の品物、色々な国から福祉用具などが出展されている。
展覧会を見ていると「あれ?見たことがある」そんな商品が多々あった。
「これはこちら(香港)で制作しているものですか?」と聞いてみると「いえ、日本の商品ですよ」そんな商品もたくさんあった。
知人が、「あれ?これ日本で使ってるの!」なんて思って近づいてみると広東語で話しかけられる。日本語で聞き直してみると「あれ?日本の方なんですか?」と驚かれたと。一般客の日本人なんて少ないんだろう。
我が家でも使っている・お世話になっているメーカーのものも出展されていて話もはずんだが、担当の方が現地に26年も駐在していると聞いてさらに驚く。
車椅子のWHILLといい日本の優れた福祉用具も世界で活躍しているんだなあ、と嬉しくなる。
しかし、この香港で最大の福祉用具の展覧会、日本で行われているものと一番違うところは「子どもがたくさん来ている」ことだ。最大の違いである。
日本の福祉用具の展覧会では、ほとんど子どもの姿を見たことがない。香港の展覧会には本当に驚いた。あちらこちらに小学生の遠足らしきグループが先生に付き添われている。楽しそうに最新の車椅子や、お風呂に入るためのリフトや、リハビリのために開発された卓球のプログラムなんかを試している。
でも子供のことだ、車椅子に乗るのだってあっちにぶつかり、こっちで動けなくなっていたり、あんなに遠くまで行っちゃったの?そんな感じで、しかも楽しそうに色々体験している。ブースの会社の人も慣れたもので子どもの相手をしている。今回だけではなく、よく来ているんだろうなあという感じで大人側も対応している。
「この学校、香港ではお嬢様学校ですよ」なんて小耳に挟んだりしたが、その学校だけでなく、他の学校もたくさんきていた。車椅子を体験している友だちの横で「なんでこんなにクルクル回れるの?」なんて質問している子もいたという。「好奇心の塊」の目をしている。あまり先入観もないようだ。そんな時代を体験できることは良いことだと思う。この子たちの感想文をぜひ読んでみたいなあ。

展示品を体験する子どもたち(写真・本人提供)
次に感じた日本の展覧会との違いは、VRモノの商品がものすごく多いことだ。大学の研究発表やリハビリに使うゲームなど本当にたくさん見た。
VRに関していえば日本のボクの周りには研究している方も実際リハビリに使用している施設もあるにはあるが、香港は出展している数が比べ物にならないぐらい多い。ゲーム性の高いリハビリもの、認知機能を確かめるためのものと様々だ。VRが身近に流通しているんだなあと実感した。

VR系の展示品も目立った(写真・本人提供)
この展覧会は、一般の市民も福祉用具を間近で体験し、理解を深めるだけでなく、現地の高齢者や障害を持った人、色々な人やサービス産業が、福祉関連の科学技術を「よりよく使えるようになるためにある」と聞いたのだが、実際それが成り立っているような気がした。子どもたちがそれらの用具をこんなに小さいうちから触れて使ってみることは本当に有意義なことだと思う。
日本の福祉用具の展覧会にも一般企業の方々が(福祉に関係ないような企業も)研修に来ているのは知っていたが、ぜひ子どもたちも遠足で行ってほしい。
![]()
「病気を患ったパパを置いては死ねないなあ」と考えていました。
神足明子(妻・介護する側)
「私が全部やる」体制を見直す試みは裕司も積極的で「いいんじゃない」と思っています。
先日の香港で行われた展覧会もそうですが、今年は公私ともによく海外へ行く機会がありました。私同伴でなくとも海外へ行けるよう、色々な対策を考えました。もちろん一番慣れている私が一緒の方が、私も本人だってスムーズに決まっています。けれど、裕司本人だって私と離れて普通に仕事や、友人たちと出かけたりするのも、たまにはしたいんじゃないかな、と思ったりもします。
大体私は「こんなに過保護だったのか」と思うほど一緒にいると「どうかな?大丈夫かな?」なんて心配してしまうし、あれやこれや手を出してしまったりするのです。
「少しはいない方が、パパのためにもリハビリのためにいいんじゃないか?」なんて思ったりもします。
今までは「病気を患ったパパを置いては死ねないなあ、一日でも長く私が生きなきゃ」なんて真剣に考えていたのですが、だんだん歳をとってくると「どっちが先に病気や事故で亡くなるかもわからないなあ」なんて思うのです。急に私がいなくなったことを想像して、その練習に「私が全部やる」体制を見直さなきゃ、と思うこともしばしば。ここ数年の私の心境の変化です。
そこで、旅や仕事も色々手伝ってもらえるような、車椅子も押してくれる人をお願いしてみました。専属ではないので、必要な時に何人か交代で頼むのですが、まあ試行錯誤。長年一緒にいる私だって裕司の代弁を間違えてしまうこともしばしば。そこはなかなかうまくいかないようですが、後から聞いてみると、裕司もしっかりしなきゃと思うのか積極的な感じもします。「いいんじゃない?!」私は密かに思っています。もちろんその方にはトイレ関係や身体的なことはお願いできないので、ヘルパーさんにも依頼しないといけません。大掛かりなことになってしまいますが、そのフォーメーションでもなんとかやれることがわかって私も一安心です。
その方法で海外にも仕事に行けるし、普段のお仕事もできないことはないと分かっただけでもホッとしました。仲のいい友人に「そりゃ、アッコがいなくたってちゃんと回るって言ったでしょ?大丈夫だって」と前から言われていたのですが、とにかく心配性の私が手放せなかっただけなのかもしれません。そんな感じで今年は色々なフォーメーションで国内や海外へ出かけていった裕司でした。
仕事あり、プライベートあり。行く所々で裕司が「ここへ来るのは最後になるかもしれない」なんて毎回言うので「いつも言ってるけどそんなことないでしょ?」と返されてしまうのですが、よく行く場所ならいざしらず自分にとってマイナーな所では「そうなのかもしれないなあ」なんで横で聞いていることもあります。
もしそうならその場所で何をしたいのか、何を見たいのか、と思うのですが、いつも裕司は「以前行ったところへ行きたい」とか「食べたい」と言うことが多いということ。仕事柄「ここで海の中の写真が撮りたい」とか「星の写真が撮りたい」というような新しい「やりたいこと」は増えましたが結局「旅のマーキング」(最近我が家でできた新語)をしたいんだな、と思うのです。
そういえば、よく行動を共にしている「動けない高齢者に旅のプレゼント」を行っている方の話を聞いていても「どこに行きたいですか?何が見たいですか?」と聞いてみると、「昔住んでいた家のあったところを見てみたい」とか「以前行ったパリの公園にあるベンチをみたい」とか過去に行ったことのある場所やレストランをみたいというのが圧倒的に多いそう。もちろん行ったことのない「一度行ってみたかった」という新しい場所もリクエストには多いのですが、過去に訪れた地へもう一度行ってみたいという「思い出の確認(旅のマーキング)」がしたいようだ、とのことです。
裕司は結婚した頃、香港が大好きでした。ショートトリップでもイギリスの雰囲気を味わうことができた点。それなのに中国やインド、様々な国の文化が混在していて中国本国とは全く違う、その雰囲気が好きでした。
大好きだった九龍側のホテルでは、クリスマス時期になるとトランジットでも数泊滞在する、というほどでした。そこから船でセントラル側へ渡って、これまた好きな中国茶の店とイギリスのスーパーへ。旧式のワゴンで飲茶を食べて、レパルスベイの方まで二階建てバスでいく。「そのコースを行ってみたいな」そんな話をしていましたが、一つも実現できず。仕事ですから。「最後かもしれない」と言っていた香港ですが「もう一回行く」と言い出す始末。リベンジです。
道路の真ん中まで張り出す電飾の看板なんかはめっきり減ってしまって、昔とは少し変わってしまった香港ですが、まだまだ裕司によっての「いい思い出の地」は健在だったようです。
何か心の中が動いてやりたいことがむくむくっと湧いてきたようです。
旅にはそんな効果もあるんですね。

香港の様子(写真・本人提供)
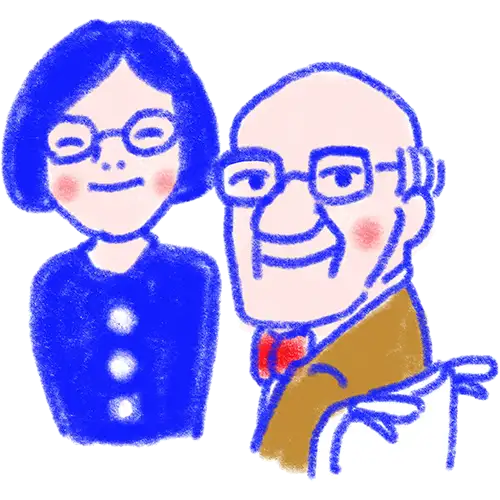
神足裕司
こうたり・ゆうじ●1957年広島県生まれ。大学時代からライター活動を始め、グルメレポート漫画『恨ミシュラン』(西原理恵子さんとの共著)がベストセラーに。クモ膜下出血から復帰後の著書に、『コータリン&サイバラの介護の絵本(文藝春秋)』など。
神足明子
こうたり・あきこ●1959年東京都生まれ。編集者として勤務していた出版社で神足さんと出会い、85年に結婚。1男1女をもうける。