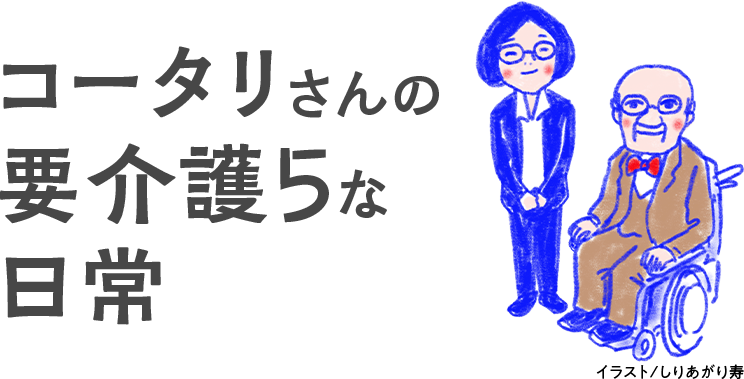<毎月第2・4火曜更新>2011年、突然のくも膜下出血により要介護5となった神足裕司さん(コータリさん)と、妻の明子さんが交互に綴る「要介護5」の日常。介護する側、される側、双方の視点から介護生活を語ります。
連載第45回「我が家の介護事情」
![]()
我が家で「自由に体が動く人」は妻だけだ。
神足裕司(夫・介護される側)
両親の介護だけでなく叔父、叔母の問題も周りで結構聞く話だそう。
我が家にとって介護の問題は、ここ10数年ぐらい大きくのしかかっている。特にこの1年は過渡期を迎えているのだ。
現在は、90歳の義両親とボク67歳、妻65歳。我が家で元気に動けるのは妻だけだ。元気に動ける妻だって実は闘病中だったりする。「自由に体が動く人」という意味だ。
ご存知の通りボクは12年前くも膜下出血に見舞われ、53歳の時に半身不随や言語障害、記憶障害、視野狭窄、本当に色々な障害を持ってしまった。いまだに寝返りも打てない。
最初の数年は介護初体験の娘や息子、それにキーパーソンの妻を中心に試行錯誤、在宅で介護してもらってきた。妻は50歳になったばかりで若かった。同居の義母も若かった。ベッド上のボクにおやつを持ってきてくれたり、お茶を持ってきてくれたり。
「私がいるから。何かあったらヘルパーさんに電話するから平気よ」義母はそう言って、ボクにとって「介護者の一役」だって担ってくれたぐらいだ。
妻が1日いなくたってボクらでそこそこ留守番もできていた。
そこへ6年前ぐらいに、単身赴任していた義父が大腿骨骨折、予後も悪く歩けない状態で帰ってきた。我が家の1階にある客間だった部屋に「もう歩くのは無理かもね」という状態で。
最悪なことに癌の手術をして余命宣告もされていた。
「家に帰すのは無理だよ」そう言われたが「最後ぐらい家で過ごして、いよいよになったら病院へ行けばいいわよ」と太っ腹な妻が提案した。まだ子どもたちも家にいたし、人手があった。いや、子どもたちを人手として期待していたわけではない。妻の精神衛生上の問題だ。愚痴を言える相手がいた。
ボクは1階にもう1部屋あった仕事部屋のデスクを片付け、そこに介護ベッドを置いて生活していた。妻はその床に布団を敷いて寝ていた。
寝返りを打てないボクは少なくとも3時間に1回体位交換が必要だったので、妻はそこに寝ることとなったのだ。(現在はAI搭載のベッドで管理されているのでベッドが自動で体位交換をやってくれる)

仕事部屋のデスクと介護ベッド(写真・本人提供)
その時は義母が元気だったので、2階にある自分の部屋で十分生活できていた。
その後5年かけて歩けなかったはずの義父は歩けるようになり、庭の手入れや家の壊れたところを日曜大工で直したり、家の中では元気に動き回れるほどに回復していた。典型的な昭和1桁生まれの頑固義父だ。家の中での尊厳が作用したようにも思える。「家にいて生活することが体にとってこんなにいいことなんだなあ」と実験のように間近でみた。
義母は義父が作った中小企業の1つを任され経営していたので、年齢の割に進んだ考えの持ち主だった。義父が単身赴任で長年いない生活に慣れきっていたから頑固な父に対しても「自分のことは自分でやる!」という姿勢をとってきた。新しい生活の形態ができるまでは大変だったが、子どもたちも独立し、なんとか老人4人体制の我が家が出来上がった。
それがだ。昨年義父が骨折して入院した。それをきっかけに歯止めがきかなくなったように我が家はバランスを崩した。
すぐに帰ってくるだろうと思っていたが、義父がいなくなって間もなく義母の様子がおかしくなった。今まで義父の面倒をそれなりにみてきた緊張感がなくなったせいだろうか。認知症が始まった。急速に。まだ普通に生活できているが、もう結婚して独立した孫が帰ってこないと夜中に心配して玄関を開けてみている。妻は何回起きて義母を寝室へ送ることか。
入院には至らない程度ではあったが、そのうち義母も骨折して2階の部屋での生活はできなくなってしまった。今では義父の部屋だった1階で寝ている。義父は帰ってくるタイミングを失ってしまっている状態だ。帰ってきても2階で生活できるメンバーがいない。
「リビングにベッド置く?」
「爺さん(義父)の部屋だったとこは広いんだから片付けて2人部屋にしたら?」
我が家の老人ホーム化が始まるのか。
そしてまたまた昨年は妻の叔父が亡くなり、子供がいない叔母(88歳)の介護が妻のはんちゅうに入って来た。流石に妻もお手上げじゃないか?
我が家が特殊なのかと思っていたら、周りで結構聞く話だそう。叔父、叔母問題。結婚していなかったり、子供がいなかったり。
知り合いは付き合いもない叔父が独居で亡くなり、役所から電話がかかって来たそうだ。財産や借金があるかもわからない叔父だったが、役所の人も慣れたもので「財産放棄の手続きをしてくれれば関わらなくてもいい」というような話だったとのこと。
そんな差し迫った話ではなくても「親族で話し合って叔母さんを地方の老人ホームへ入れた。叔母さんの年金で生活できるように」とか「なぜか私が2時間もかけて叔母さんを見に行っている。2ヶ月に1回ぐらいだけど」とかね。そんな話をたくさん聞く。両親だけでなく、叔母さんや叔父さんまでかあ。若者の、いや初老を含めて、ますますそんなことは多くなっていくんだろう。
叔母はまだ元気で1人で生活できている模様。妻は重い腰を上げて老人ホームやその他施設を探し始めた。色々な問題がのしかかってくる。
妻が今1番ボクに話すワードは「これってこの金額に見合ってる?」だ。
入居金に月々かかる金額、食事や遊興費。「そんな豪華なところは無理よ」「けどねえ」
「年金でどうにかなるところにしたらいい」とアドバイスをもらった。義父母は働いていたし年金もそこそこあるが、ボクは年金じゃ入れるところがないんだよね。
それが我が家の最近の話題である。
![]()
裕司がなんと「優等生な介護される人」だったのか
神足明子(妻・介護する側)
「優しくしよう」そう思っているのに、なんでそうできないのか。いつも自己嫌悪になってしまいます。
もうすぐ14年になろうとしている介護生活。よく「介護生活は終わりがわからないから辛いのよ」と聞いていました。
介護が始まって14年もたとうとしているけど、まだまだ先は長く続きそうで、私が先にどうにかなってしまったら、、、なんて考えることも出てきました。
ここ一年ぐらいの我が家の介護生活を思うと「今までは本当の介護生活だったのかなあ」と思ってしまいます。両親の介護が本格的になってきたのです。最近は自宅にいる認知症がはじまった母と毎日喧嘩しています。
今まで裕司を介護してきたのとは全くと言っていいほど感覚が違います。裕司がなんと「優等生な介護される人」だったのかと。
まあ仕方ないのです。裕司は動けないのでベッドから落ちることもなければ知らないうちに歩いてどこかへ行ってしまうこともありません。しゃべれないので喧嘩してぶつかることもありませんでした。逆に「どう考えているんだろう?」「痛くはないか?」など「こちらが考えなければ」と常に思っています。何も言わないのですから。
動けない人を介護する苦労はあります。力が入らない人を持ち上げたり、動かしたりするのはそれはそれで大変です。けれど普通は介護される人も自由に動いたり、反論したりできることが多いのです。当たり前ですが。しかも両親なので上下があるとすれば親が上の立場であることが多いのでしょう。どちらが大変か?
母が今日も薬を飲んだか飲んでないか、ヘルパーさんと話し合っています。飲んだのならその袋は?日付が入っているはず。「ないのよ。飲んだかわからないのよ」ゴミ箱まで探すのですが、どこにいったのかわかりません。「だからヘルパーさんが来るまで薬は触っちゃダメだって」ついつい母に言ってしまいます。
話し合って、今度は母の薬を裕司の部屋へ隠しておくことにしました。母の目が触れない場所に。ヘルパーさんがそこまで取りに来て飲ませることに。すると夜中に薬を探して「ねえ、薬がないのよ」と起こしに来ます。私、どうしよう。
お鍋も何回焦がしたことでしょう。「お鍋を火にかけたら近くにいないとダメだって」
そんなことに怒っても。だって敵は認知症なんだから。わかってはいるんです。
我が家のガス台は温度が上がったら消えるものに変えました。電気湯沸かし器をテーブルの上に置いたりしましたが、それを火にかけてみたり。「プラスチックが燃えて火事になるところでした」とヘルパーさん。
あっという間にそれもダメになり、ガス台はスイッチが入らないよう細工しました。「火がつかないのよ」「おかしいねえ、壊れたのかな」何回も聞きに来ます。
自宅への帰り道、夜ゴミの回収場所を通ると「あれ?これうちのゴミだよね」と明らかにわかる袋が放置されています。プラスチックゴミの日なんてまだ先なのに。家に持ち帰り「プラスチックゴミ、今日じゃないよ」「え?捨ててないわよ」
そう?ゴミ置き場にあったけどね、、、ゴミが歩いていったんだね、、、と心の中で言葉を吐き捨てプンプン。毎日同じことの繰り返しです。「あれ、また違う日に出してる」母に伝えても仕方ない、とそのまま回収して終わることがほとんどです。でもなにかの拍子に「違うって」と言葉が出てしまいます。言ってはいけない、と思っているのに。
真面目に取り合っても仕方ない。言っても分からないんだから仕方ない。わかってはいるんです。「優しくしよう」そう思っているのに、なんでそうできないのか。いつも自己嫌悪になってしまいます。
あんなにおしゃれだった母が変な組み合わせの洋服を着て寒い寒いと言っています。そんな母を「みていたくないな」という気持ちもあるのかと思います。
父は骨折で入院したのに、コロナに感染したり心臓の調子が悪かったりするうちに、母がこんな調子になり、帰ってくるタイミングを失って施設のお世話になっています。
今も施設でコロナが発生し、面会はできませんが「細いタイプのマジックを持ってきて」「単行本を注文して持ってきて」「雑誌を持ってきて」と3日をあけずオーダーが入ります。面会もできないのだからわざわざ行かなくても、Amazonで注文して郵送したらいいんじゃないか、いい考えだ!と思っていましたが、何故かダメだそうです。残念。
昨日の私のスケジュール。朝ごはんは裕司と母の3人で平和にいただく。お洗濯など家事全般をすませ私の病院の受診。母がヘルパーさんとお風呂の日だというので用意をして、着替えの件で母と一悶着。
その後裕司と母に昼ごはんを食べさせて父の施設にお届け物。ドライブスルーのように受付へ荷物を預ける。
その足で約40キロ離れた叔母の家へ。叔母宅での第一目的は最寄りの銀行へキャッシュカードを作りに行くこと。ギリギリ15時に間に合った。ほっと一息ついたところで「身分証明書がバッグに入っていない」と叔母。「え〜〜」
事情を話すと、15時が過ぎシャッターが閉まっている入口の、通用口を通って取りに帰っていいということに。叔母が取りに行くがなかなか帰ってこない。「どこかに置いて分からなくなったの。マイナンバーカードも保険証もちゃんと一つのポーチに片付けたのよ。それがないの」と自分はちゃんと管理しているが見つからないと主張。
「はいはい、じゃあ今日はダメね。また私がこれるときに」「困ったわ、キャッシュカードないと不便なのよ」そう言ったって、わざわざこのために来た私。次に来れるのは10日後。
「10日後なんて、なんとかならないの??」いやいや無理ですよお。パパの仕事だって詰まってます。
叔母は最近「いつ来れるんだ」「次はいつ?」と寂しさを連呼します。叔母の家で居間にあるスマートフォンへnanacoのアプリをいれ、証券会社に残高証明の電話をして、夕方遅めの時間に夕食の材料を買って帰宅。
帰宅してみるとリビングにも部屋にも母の姿が見えない。「あれ?どこだろう?」
裕司の部屋へ行ってみると、母は裕司の車椅子に座り、何やらお茶を一緒に飲んでいる様子。(と言っても裕司は一人でベッドでは飲めないのですが)
「ねえ、パパ(裕司)。お腹すいちゃったわよねえ」と母。
「はいはい、わかりました。遅くなってごめんね、夕飯にしようね」小さな子どもが私を待っていたような感覚です。
ご飯の後にようやく裕司の原稿書きの本番の仕事が待っています。こんなバタバタの一日です。
でも友人には「明子がいなくなってお母様は平気なの?私なら家に残して外にはいけない」そう叱られてしまいます。裕司の介護初期の頃にも言われました。動けない裕司を置いて出かけられるのか?と。本当に熱心な介護をしていると私のいい加減さ?がハラハラするそうです。
かたや違う友人には「なんで老人ホームにすぐに預けないの?ちゃちゃっとやっちゃえばいいじゃん。何に悩んでるの?お金?まさか弟さんが何か言うの?誰かに相談してる?」
いや誰にも相談してないけど、その友人が言うようにちゃっちゃと老人ホームにも入れる決断なんてできないんです。
「なんで優しくできないんだろうと思ってるくらいなら預けたほうがお母さんも幸せだよ」そう言われると落ち込みます。
なんで老人ホームに入れる決断がつかないのか、自分でもよくわかりません。もう一方の友人に言われたように、ちゃんと介護ができていないなら、預けたほうがよっぽど良いんだとは思います。
私のアバウトな性格が今の介護生活ができている要素の一つなんだとも感じています。

両親と裕司でいちご狩りに、母と裕司(写真・本人提供)
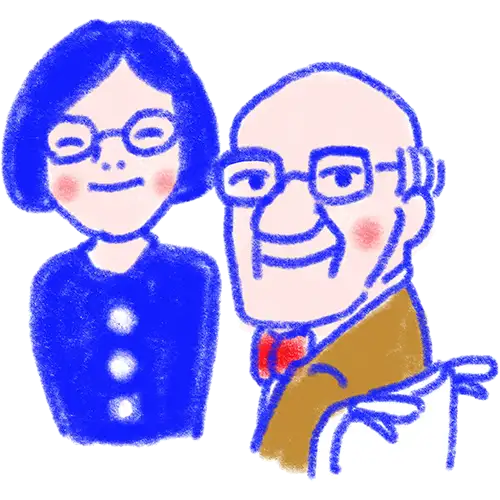
神足裕司
こうたり・ゆうじ●1957年広島県生まれ。大学時代からライター活動を始め、グルメレポート漫画『恨ミシュラン』(西原理恵子さんとの共著)がベストセラーに。クモ膜下出血から復帰後の著書に、『コータリン&サイバラの介護の絵本(文藝春秋)』など。
神足明子
こうたり・あきこ●1959年東京都生まれ。編集者として勤務していた出版社で神足さんと出会い、85年に結婚。1男1女をもうける。