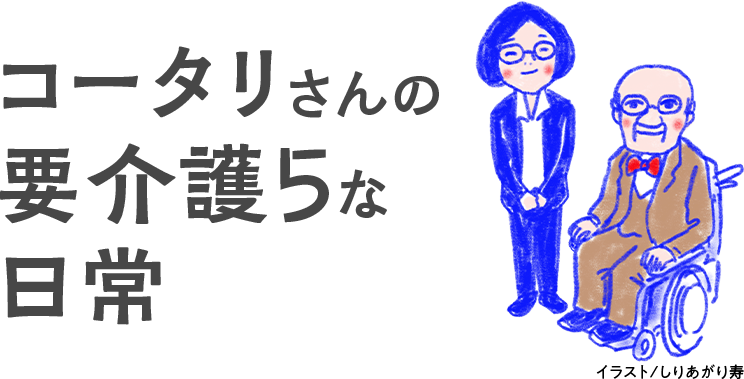<毎月第2・4火曜更新>2011年、突然のくも膜下出血により要介護5となった神足裕司さん(コータリさん)と、妻の明子さんが交互に綴る「要介護5」の日常。介護する側、される側、双方の視点から介護生活を語ります。
連載第49回「新しい場所」
![]()
新しい場所には少しだけ構えてしまう。
神足裕司(夫・介護される側)
新しいことを始めるときに大切なのは、まず「相手を知る」こと。
新しい場所に向かうときは、いつだって少しだけ構えてしまう。ましてや、それが仕事となればなおさらだ。期待がまったくないわけじゃない。でも、その何倍もの責任感と、まだ見ぬ土地への戸惑いが、どうしても頭をよぎる。
今回の行き先は石川県。東京大学でも活動している登嶋健太くんが中心となって動き出した新しいプロジェクトに同行することになった。いままでやってきたことが、ほんの少しでも役に立つなら…横で記録を撮れれば、と思っている。
羽田から飛行機で小松空港まで、わずか1時間ちょっと。窓の外に広がる日本海は、梅雨空の下でどこか鈍く沈んでいた。海の色に気づいたとき、自然と心も引き締まった。
空港を出て、車に乗り込み、能登半島を目指す。途中、道路脇にはブルーシートが目立ち、崖崩れの跡がそのままになった山が続く。昨年1月の地震から1年半が過ぎようとしているが、その爪痕はまだ、はっきりとこの地に刻まれていた。
珠洲市に入ると、倒壊した家々が目につき始めた。ひしゃげた電柱、ひび割れた道路。テレビや新聞で何度も目にした光景だったはずなのに、実際にこの空気の中に立つと、映像で感じていた以上の重さが、肌にのしかかってくる。崩れた瓦礫の隙間からは、誰かの日常がこぼれ落ちたままだ。
新しいことを始めるときに大切なのは、まず「相手を知る」ことだといわれる。今回の「相手」は、単なる仕事のパートナーや地元の関係者だけじゃない。この土地そのものだ。ここに暮らし、ここで傷つき、そして、また歩き始めようとしている人たち。その歴史や文化、そして今抱えている痛みや不安――全部を知らなければ、本当の意味での「始まり」なんて訪れない気がする。
車を走らせながら、地震の爪痕が残る町を見て回る。壊れた家と、その庭に咲く紫陽花。傾いた電柱と、その向こうに広がる青い海。悲しみと、美しさが入り混じった、なんとも不思議な光景が続いていた。
その日の夕方、住宅が点々と並ぶ通りに差しかかったとき、空き地が目立つ場所にひっそりと「宝湯別館」という昔ながらの温泉宿が建っていた。少しくたびれた看板が、それでもしっかりとこの地に根を張っていることを物語っていた。
宿の向かい側には、崩壊した家がまだそのまま残されていた。瓦礫が積み重なり、柱が斜めに倒れ、かつての暮らしの痕跡がむき出しのままだ。周囲の空き地も、地震の傷跡をそのまま晒している。
そんな中、作業着姿の男性が車から降り、宝湯別館へと向かって行った。続けて、別の男性が徒歩でやってきた。どうやらこの温泉は復興のために現地で働く人たちの憩いの場所にもなっているらしい。
温泉宿の暖簾が夕暮れの風に揺れていた。崩れた家と、復興に関わる人たちの小さな拠り所。その対比が、胸に残った。
車の助手席の窓を開け、写真を撮りに行ったみんなの帰りを待っていると、何か作物を作っているのか、草むしりをしている高齢の女性の姿が見えた。まわりは崩壊したままになっている家、すでに取り壊しが終わったのだろう空き地になった場所。でも、自分はここを離れず、野菜の世話をしながら、変わらずここで生きているんだろう。
崩れた家と、紫陽花と、そこに立つ高齢の女性の姿が、忘れられそうにない。きっと、ここにいる人たちは、痛みの中にも生活を続け、少しずつ、また前を向こうとしているのだ。

倒壊した家屋と紫陽花(写真・本人提供)
登嶋健太くんが始めようとしていることも、この場所、この人たちと、どう向き合うかが問われる。ただ新しいプロジェクトを持ち込めばいいわけじゃない。まずは、知ること。そして、寄り添うこと。そこからしか、本当の意味での「始まり」は生まれないのだろう。
たった2日間ではあったが、その土地を見て周り、石川の素敵な場所も、地震で傷ついた痛ましい場所も、この目で見て、耳で聞いて、肌で感じた。能登半島地震の復興に関わるこの仕事に、これまでの経験や活動が少しでも活かせるなら、それは何よりのことだ。
帰り際にもう1度、宝湯別館の前を通った。明かりが、薄暗くなり始めた通りにぽつんと灯っていた。崩れた家の向こうから「日本海がこんなに近いところに見えるんだな」と海に飲み込まれた時のことを想像して怖くもなった。
この場所、この人たちと向き合いながら、自分にできることを1つずつ、積み重ねていきたい。そんなことを思いながら、車に揺られた。
能登の海は、梅雨の中休み。夕焼けで鈍く、それでも確かに光をたたえてみえた。

広がる空き地と佇む神足さん、登嶋さん(写真・本人提供)
![]()
「復興」なんて簡単な言葉じゃ言い表せない。
神足明子(妻・介護する側)
被災地で感じた“わからなさ”と支えることの意味
能登半島の地震からもう随分経つような気がしていたし、最近めっきりニュースでは取り上げられなくなった気もしていました。けれど行ってみれば、まるで昨日の出来事のようにあちこちに傷跡が残っていて、人の生活はまだ取り戻せていません。「復興」なんて簡単な言葉じゃ言い表せない日常も見えました。
車椅子での移動は、どこへ行っても一筋縄にはいかないけれど、今回ばかりはそれ以上に「車椅子の方はどうしているんだろう」と本当の意味で不安になりました。現地の人たちの生活はどう成立しているんだろう、と。
被災のひどかった地は、歩道も車道もまだまだガタガタのままで、すんなりなんて車椅子では進めない。避難所に目をやれば、家の周りに突貫工事でつけた簡易的なスロープがみえます。
「避難所の中で車椅子の方も生活しているのかな。和室では、不便だろうけど」
「どうやって寄り添えばいいのか」という問いにぶつかりました。

スロープが取り付けられた避難所(写真・本人提供)
裕司は言葉に時間がかかります。けれど、今回の視察では「こっちの道、段差がすごい」「どうやって生活してるんだろ」など「言葉が思わず溢れた」という感じで出てきます。
いたるところで起きている災害。「被災地はどうなってるんだろうなあ」と口にします。当たり前のようにすでに復旧、復興していると思っていたのに。現状は違うのかもしれません。
ある現地の女性は「ボランティアさんは来てくれるけど、数日で帰っちゃう。ずっといてくれる人がおらん」と笑っていたけれど、その声の奥には、少し泣きそうな響きがあったような気がします。「私たちだって本当に頑張っている。まだ、私たちになんかしろなんて無理だわ」と、お怒りの言葉も聞きました。
「介護する側」としてとても気になったのは、やはり避難所から歩いてすぐの所への移動でも、結局「裕司は車で待たなければいけない」という場面が何度もありました。要するに、車椅子では動けない、通れない場所になってしまっているのです。
けれど、そういう不便さを目の当たりにすることで、ようやく私もほんの少しだけ、ここで暮らす人の困りごとに触れられた気がしました。
それと同時に「支援をする難しさ」を感じたりもしました。
目の前にいる人が困っている。でも何に困っているのかが、すぐにはわからない。それを一緒に考えてみること。想像してみること。
その上で私たちが持っているもので、少しでも心が満たされてくれたら、と切実に思いました。
今回、石川県からお呼びがかかり、VRで世界旅行をお届けする事業に採択され、被災地に出向きました。「登嶋健太さんを代表とする裕司たちのVR旅行のシステムが少しでも癒しになってくれたら良いのになあ」と心から感じました。
今回、裕司と石川県へ行って「支えること」について、改めて考えさせられました。
介護も支援も、すぐに結果が見えるものじゃない。むしろ「何ができるかわからない」という状態に、耐える時間の方が長いのです。
でも、その中で人と人が少しずつ近づいていく。信頼も希望も、そうやって育っていくのだと思いました。
裕司が帰りの車の中でぽつりと「また来よう」と言っていました。
それが答えなんだろう。
あの地に、何度でも足を運んで“わからなさ”に向き合い続け、寄り添っていくこと。自分たちのできる形の支援をしていくこと。
始まったばかりのことです。勉強しながら、長く続けていきたいと考えました。

ガタガタの歩道に佇む神足さん(写真・本人提供)
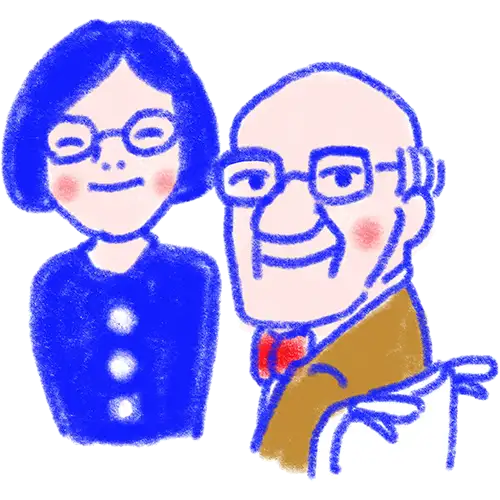
神足裕司
こうたり・ゆうじ●1957年広島県生まれ。大学時代からライター活動を始め、グルメレポート漫画『恨ミシュラン』(西原理恵子さんとの共著)がベストセラーに。クモ膜下出血から復帰後の著書に、『コータリン&サイバラの介護の絵本(文藝春秋)』など。
神足明子
こうたり・あきこ●1959年東京都生まれ。編集者として勤務していた出版社で神足さんと出会い、85年に結婚。1男1女をもうける。