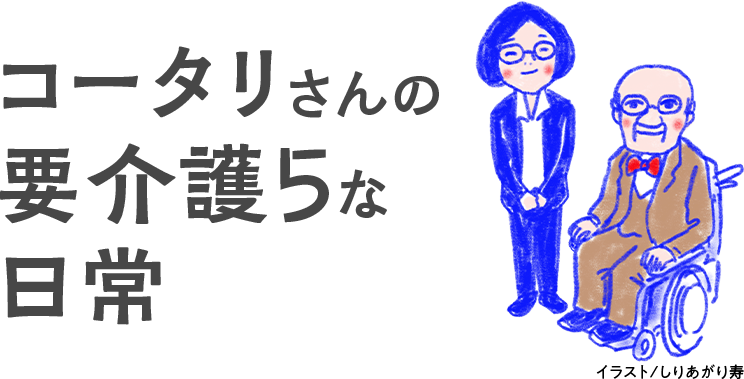<毎月第2・4火曜更新>2011年、突然のくも膜下出血により要介護5となった神足裕司さん(コータリさん)と、妻の明子さんが交互に綴る「要介護5」の日常。介護する側、される側、双方の視点から介護生活を語ります。
連載第51回「家族とはなにか」
![]()
病院での手続きなど「姪」という立場には決定権がない。
神足裕司(夫・介護される側)
子のいない叔父や叔母を姪が世話をする、そういうことを制度や社会はまだ十分に想定していない気がする。
この夏の暑さは、人の体と心を試すかのようだった。
朝から電話をかけても出ない叔母を心配して、妻が駆けつけたのは、ただの胸騒ぎからだった。玄関の鍵もあいていたそうだ。
「おかしい!?」家の中に入ると、寝室で叔母はぐったりと横たわっていた。
救急車を呼び、病院へ。熱中症だった。命は取りとめたが、もし発見が少しでも遅れていたらと思うと、今でもぞっとする。
叔母は昨年、長年連れ添った夫を亡くした。子どもはいない。
身寄りといえば、年老いた兄――つまり妻の父と、妻、そしてその弟だけだ。
実際に妻は叔父が亡くなってからあれこれ面倒を見てきた。叔母もまた妻を頼りきっている。病院のベッドに横たわる叔母は、弱々しい声で「心配かけてごめんね」と言った。叔母は涙をこらえきれず、妻のその手を握りしめた。
妻と叔母は、特別な関係にある。結婚前の叔母は実家で同居していて、幼い妻にとって「もう一人のお母さん」だった。夏休みに一緒にアイスを食べたこと、そうした日常が妻の心には今も残っている。だからこそ、叔母に頼られるのは自然なことのように思えるのだろう。
けれども、実際の制度や病院での手続きになると「姪」という立場には決定権がない。そこに大きな「もどかしさ」がある。
病院からは「退院後の生活をどうしますか」と迫られる。自宅に戻すのか、リハビリ病院に転院するのか。真夏の一人暮らしに戻すのは危険すぎる。でも姪である妻には「最終判断権」がない。
年老いた父(叔母の兄)も入院中。あっちもこっちもお年頃の状態だ。妻は「わたしが一番近くで世話をしているのに、どうしてはっきりものが言えないんだろう」と苦しくなる。その言葉を聞くたび、ボクも胸が痛む。
何か助けはないものだろうか。そんな状況でも支えになるもの。病院には医療ソーシャルワーカーがいて、退院後のプランを一緒に考えてくれる。叔母が住む横浜市には地域包括支援センターがあり、独居高齢者のための見守りサービスや、身元保証、死後事務の相談までできる。制度や地域の支えが、親族の「立場の壁」を少しずつ補ってくれるのだ。介護認定の手続きなどなかなか大変な時を過ごしている。
叔母にとって、妻は最後の「安心できる拠り所」なのだろう。だからこそ頼るし、だからこそ甘える。妻にとっても、子どもの頃からの思い出が繋がっているからこそ、突き放すことはできない。これは血のつながり以上の「生活のつながり」なのかもしれない。
親戚の中で、こういう関係が生まれることは決して珍しくない。だけど、それを制度や社会はまだ十分に想定していない気がする。
ボクは思う。親の介護だけでなく、子のいない叔父や叔母をどう支えていくのか。それはこれからの時代の大きなテーマだ。少子化で「姪や甥」も少なくなる。誰かが倒れたとき、誰が駆けつけるのか。今回、妻が叔母を救ったように、血縁の濃淡より「そばにいる人間」が一番の命綱になるのかもしれない。
病院の帰り道、妻はぽつりと言った。「もし叔母がまた家に戻って同じことになったら、今度は助けられないかもしれない」。その声には、疲れと覚悟が混じっている。ボクはただ、横でうなずくしかできなかった。でも、そうやって心を痛める人がいる限り、叔母はきっと大丈夫だと信じたい。
この暑さはまだ続く。エアコンのスイッチ一つが命を左右する夏に、僕らは「家族とはなにか」を突きつけられている。血縁、制度、そして思い出。そのどれか一つでは支えきれない。けれど重なり合えば、人は生き延びることができる。叔母と妻の物語は、その証のように思える。
妻の肩には少なくとも介護が必要な人間が4人もいる。ずっしり重い。その1人が自分なことが心苦しい。
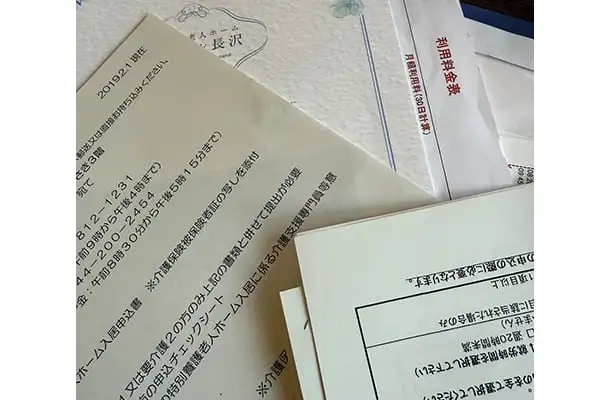
叔母のために取り寄せた資料(写真・本人提供)
![]()
介護は重荷だけれど縁でもあります。
神足明子(妻・介護する側)
叔母の介護が加わると抱える要介護者は4人に。
叔母の入院が続いています。病室で横たわるその姿を見るたび、胸の奥が締めつけられるのです。
この人は、私にとって「第二の母」になりつつあります。やっぱり「私が面倒みないとだな」と思います。
母が忙しくて手が回らなかったとき、料理を教えてくれたり、相談に乗ってくれたりしたのが叔母。
その叔母は今、夫を亡くし、子どももおらず、独りきりで病と向き合っています。退院後、どうやって暮らしていくのか。だれが支えるのか。「答えはひとつしかない」そう考え始めました。「第二の母」を今度は私が介護する番。そう思うと、胸の奥に重い覚悟がずしりと落ちてくるのです。
しかし現実は厳しい。すでに私の暮らしには3人の要介護者がいるのです。
同居している実母は認知症が進んで、日ごとに目が離せなくなっています。火を消し忘れたり、同じ話を何度も繰り返したり。私がいないと子供のように不安がります。母のそばにいる時間は、身体よりも心を削られます。
父は別の病院に入院中で、通院や面会の負担があり、そして夫の裕司は病を経て、日々の生活や仕事は常に一緒です。
そこに叔母の介護が加わる。数えてみれば4人。四方から引っ張られているようで、自分の体が裂けてしまいそうになります。
夜、布団の中で思います。「このままの体で、私はどこまで持つのだろう」と。65を過ぎ、体力も落ち、あちこち怪我をしたり腰も痛い。若い頃のように力で押し切ることはできません。
「施設に預ける」という選択肢もあります。でもそれは万能の解決策ではなく、預けたからといって安心できるわけではありません。結局は見舞いに通い、気を配り、最後まで心を砕き続けます。どんな形でも、叔母を支えるのは私なのです。
叔母の手を握ると「あっこちゃん、困ったわねぇ、私どうなるのかしら」と弱々しく話します。
そのぬくもりに、子どもの頃からの記憶が重なります。「ありがとう」と言葉にはしなくても、目の奥に感謝の色が浮かぶ。その瞬間、私は思うのです。「やっぱり最後まで、この人を見届けよう」と。
もちろん、不安は消えません。4人の要介護者を抱える現実は、時に私を押し潰しそうになります。「もし私自身が倒れたらどうなるのか」考えると怖い。けれど、それでも逃げられないのが「縁」なのだと思います。「できるのかな?甘い考えかな?」常に不安になります。
母、父、叔母、そして裕司。みなそれぞれ、私の人生を形作ってきた大切な人たち。叔母は「第二の母」として、母の隙間を埋めてくれました。今度は私がその人を支える番です。父と母には、娘として最後に寄り添いたい。裕司とこれからも共に歩んでいきたい。
介護は重荷です。けれど同時に、縁でもあります。叔母を介護することは、ただの義務ではなく「私に与えられた宿題」であるように思えるのです。
不安がなくなることはないでしょう。でも、一歩ずつやっていくしかない。荷物がどれほど重くても、できるとこまでやっていくしかないな。

入院中の叔母(写真・本人提供)
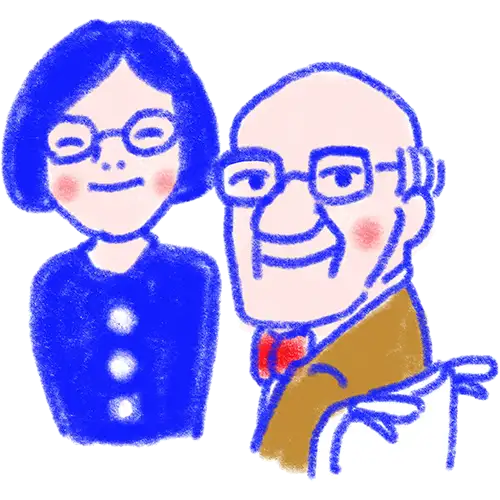
神足裕司
こうたり・ゆうじ●1957年広島県生まれ。大学時代からライター活動を始め、グルメレポート漫画『恨ミシュラン』(西原理恵子さんとの共著)がベストセラーに。クモ膜下出血から復帰後の著書に、『コータリン&サイバラの介護の絵本(文藝春秋)』など。
神足明子
こうたり・あきこ●1959年東京都生まれ。編集者として勤務していた出版社で神足さんと出会い、85年に結婚。1男1女をもうける。