小さな駅で降りる
中編
- 作品:
-
小さな駅で降りる
2000年4月(全1回) テレビ東京 - 脚本:
- 山田太一
- 演出:
- 松原信吾
- 音楽:
- 久石譲、上田聡
- 出演:
- 中村雅俊、堤真一、根岸季衣、奥貫薫、前田亜季、石丸謙二郎、岩松了、柄本明、佐藤慶、山崎努、牧瀬里穂、樋口可南子ほか
叩き上げのスーパーの社長との対話。
食品会社だから仕事先にスーパーがある。
ある時、里見は部下の沢口、それに別の部署の若い女性(奥貫薫)の二人を連れて町のスーパーに行く。社長に会う。
この社長を演じているのが山崎努。当然といえば当然だが、貫禄ある素晴らしい演技を見せる。演技というか、もう完全にスーパーの社長になり切っている。訪ねてきた中村雅俊、堤真一、奥貫薫の三人が緊張しているのは無理はない。
社長といっても大企業の社長とはまったく違う。背広でネクタイなどという堅苦しい格好ではなく、普段着のブルゾン。いかにも叩き上げで、現場を大事にしていることがうかがわれる。
これはあとでわかることだが、彼はもともとは町の魚屋だったという。昭和四十四年にこれからはスーパーの時代だという世の流れを見て、魚屋をスーパーに変えた。これが一号店で、現在は、とても大手にはかなわないが、それでも十七店舗になっている。
食品会社の三人を前にして彼はいう。「大手にまじってなんとかやっていけているのは、オレが毎朝、十七店すべてまわって、この商品はここに置け、これはこっちと指定しているからだ」と語る。
決して自慢しているわけではない。弱小企業の苦労を語っている。苦労人だけにつねに現場を大事にしている。彼は、仕事中の女子社員が三人の客に茶をいれようとすると「いい、俺がやる」と自分で茶をいれて三人に出す。人柄がこの一点でわかる。
合理化への批判と悲しみ。
里見がまず、これまでこの店の営業を担当していた柄本明演じるベテラン社員が会社を辞めたと報告すると、社長は気の毒そうにいう。
「昨日、来たよ。泣いていたよ」。
食品会社の営業部員(卸し)と町のスーパー(小売り)のおやじとのあいだにいい関係が出来ていたのだろう。その相手がリストラに遭った。気の毒と思うと同時に、食品会社が若い二代目の社長になって合理化を進めているのを苦々しく思っているのだろう。三人に苦言を呈するようにいう。
「なんか火が付いたように人減らししているんだって」「合理化を進めて、昔の小売りと卸しのいい関係なんかなくなったな」。
おそらくリストラに遭った社員の時代には町の小さなスーパーとも、情のある付き合い方をしていたのだろう。一緒に酒を飲むこともあっただろう。売り場で手伝いもした。そういういわば家族的な付き合いがあった。そうした小売り(スーパー)と卸し(食品会社)の親密な関係が、次第に古臭いと否定されてゆく。
町のスーパーの社長はそれを悲しんでいる。批判している。
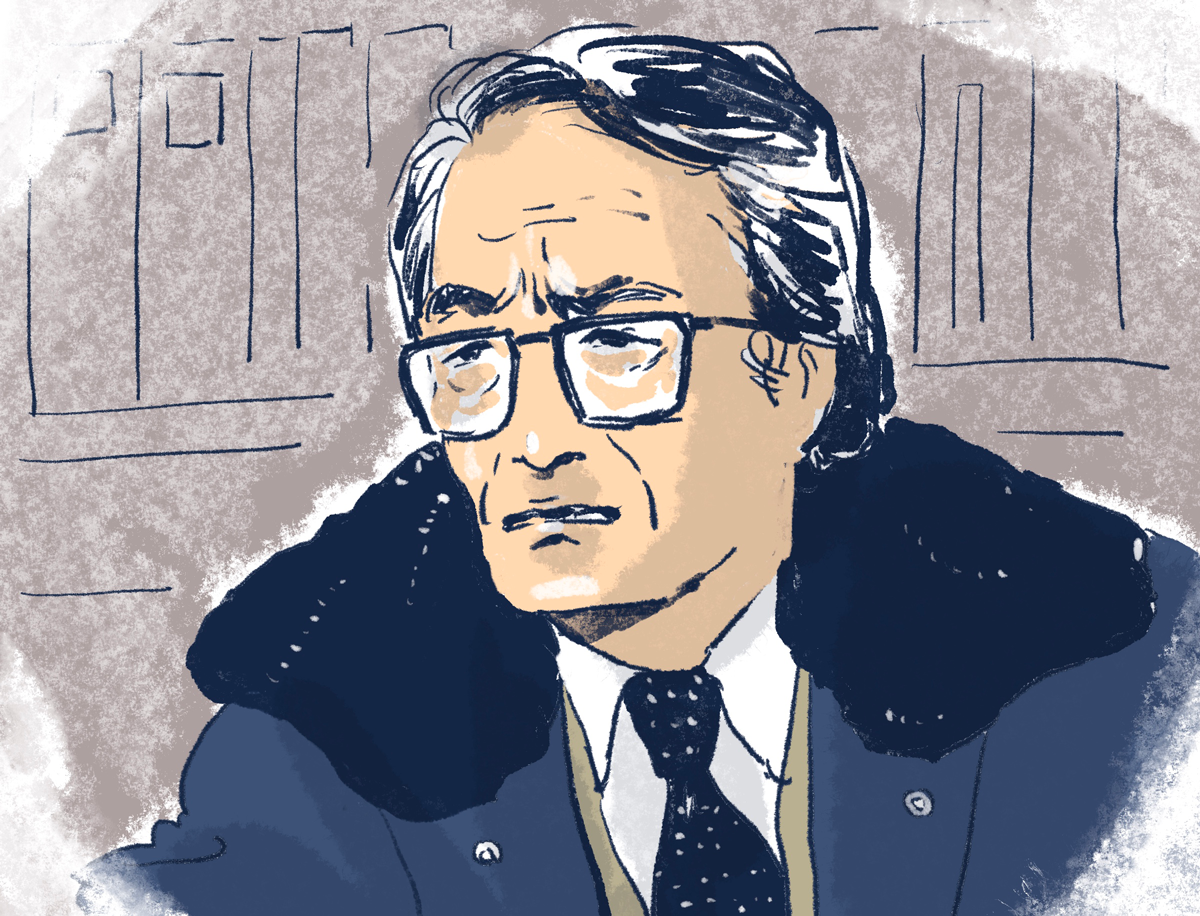
イラスト/オカヤイヅミ
昔気質の社長に惹かれる主人公たち。
堤真一演じる新しい世代の社員が意見を求められ、いまの時代、昔風のやり方は合理的でないし、透明でもないと批判すると、昔気質の社長はここぞと自論を強調する。
商売は人間相手だろ。人間は合理的でもないし、透明でもない。コンピュータのいう通りには動かない。理屈どおりにはゆかない。「だいいち合理的な商売なんてつまらないじゃないか」。
小さな魚屋から始めて、なんとか十七店舗まで育てあげた。その自信、自負がある。しかし、それが次第に時代に合わなくなっているのも事実。
三人の食品会社の社員は、それでも社長のいうことに心動かされたのだろう、そのあとスーパーの倉庫で、段ボールの整理をする。
一種のサービス残業で、まったく合理的な行動ではないのだが、三人は社長の昔気質の言葉を聞いて、そうせざるを得なかった。
現代の合理化を求める会社のあり方に、三人は疑問を抱いているのかもしれない。だから社長の言い分に少し心動かされて段ボールの整理をはじめた。
ここで山崎努演じる社長が昼とは違って和服姿であらわれ、三人を見て「有難う、有難う、パートのおばちゃんたちがどれほど喜ぶか。ご苦労、もう帰っていいよ」と声を掛けるのも、この社長の気さくな人柄を感じさせる。
彼がなぜ和服を着ていたかというと、「これから民謡の発表会、市民ホール」と笑顔で説明し、〽ソーラン ソーランと歌い出すのが愉快。このあたりの山崎努は絶妙。三人がつられて「ソーラン ソーラン」と手拍子を打つのは、自然に出たものか、あるいは社長への追従か。追従としたら会社人間のつらさが出ている。
家庭を顧みない父が聞いた娘の言葉。
毎晩、帰りが遅い里見は妻とも中学生の娘とも会話がなくなっている。その間に妻と反抗期にいる娘の関係がうまくなくなってきていると察した里見は、ある日曜日、娘を車に乗せて湘南あたりの海辺に行き、娘の話を聞こうとする。
そこで娘は意外なことをいう。うちは家族ではないみたい。ばらばらになっている。「むかつく」。
仕事優先で、家庭のことを顧みなかった父親としては、黙って娘のいうことを聞いているしかない。
個人的なことになるが、私は、娘を演じている前田亜季のファン。
はじめて見たのは、柳美里原作、篠原哲雄監督のテレビドラマ(のちにビデオ化)『女学生の友』(01年)。
十五歳の高校一年生の女の子(前田亜季)と、大手食品会社を定年退職した初老の男(山崎努)の心の触れ合いを描いている。
孤独な二人が、いつか惹かれ合い、何度か会うようになる。何度目かに会って別れるとき、前田亜季が自分の祖父といってもいい年齢の山崎努を振り返って「わたしたち友だちだよね」というところは胸が熱くなった。
そのあと、山下敦弘監督の『リンダ リンダ リンダ』(05年)の、女学生のバンドのドラマーや、浅田次郎原作、鈴井貴之監督の『銀色の雨』(09年)の、米子の町で小さなネイルの店を開く女性などが忘れ難い。
※以下、後編に続く(1月17日公開)。
川本三郎(かわもと・さぶろう)
1944年、東京・代々木生まれ。東京大学法学部卒業後、朝日新聞記者を経て、映画や文芸、都市論などを中心とした評論活動に入る。主な著書に『大正幻影』(91年・サントリー学芸賞)、『荷風と東京「断腸亭日乗」私註』(97年・読売文学賞)、03年『林芙美子の昭和』(03年・毎日出版文化賞)、『白秋望景』(伊藤整文学賞)がある。その他、『マイ・バック・ページ ある60年代の物語』、近著に『映画の木洩れ日』(キネマ旬報社)がある。





