大丈夫です、友よ
後編
- 作品:
-
大丈夫です、友よ
1998年11月(全1回)フジテレビ - 脚本:
- 山田太一
- 演出:
- 深町幸男
- 音楽:
- 福井峻
- 出演:
- 市原悦子、藤竜也、深津絵里、柳葉敏郎、井川比佐志、坊屋三郎、前田まゆみ、西川亘、内藤達也ほか
熟年カップルのような浩司と良子。
洋子と有沢が津屋崎の漁港を歩いている頃、浩司と良子はハウステンボスで観光を楽しんでいる。観光船で運河を行く。中世ヨーロッパの街並みを眺める。そしてホテルに部屋を取る。旧婚旅行をしている熟年カップルのように見える。
ホテルの部屋は別々だが、隣どうし。節度を守ろうとしている。
良子はこんな豪華なホテルに泊まるのははじめてなのだろう。「キャーって驚いてる。くやしいけん、平気な顔しようとしとる」と素直にいうのが可愛い。
浩司は、西洋風に夕食のときには正装するのだから、とホテル内のブティックで良子のためにまたドレスを買ってくる。
夜、二人は食事をするためそれぞれ正装して、おしゃれなレストランに入る。浩司は慣れているだろうが、良子ははじめてなので落ち着かない。おのぼりさんの様子。
出されるワインを飲むのもはじめてのようで、あまりおいしそうには飲まない。見かねた浩司が良子のために焼酎と、そしてナイフとフォークに慣れない良子のために箸をボーイに頼む。焼酎と箸で良子はひと安心。このあたりの市原悦子の様子もいかにも「おばん」らしくていい。
ハウステンボスでのすれ違い。
一方、洋子と有沢は社長の引き出しにハウステンボスの宿泊券があったことから、そこで何か手がかりをつかめるかもしれないとハウステンボスに行く。
そこの喫茶店ではじめて有沢は熱心に洋子の会社に顔を出したのは、本当は洋子に会いたかったからだと打ち明ける。口べたな有沢としては精一杯の告白である。それを聞いた洋子はうれしそう。自分もはじめて有沢に会ったとき「胸がキュンとした」という。
夜、食事を終えた浩司と良子は庭から打ち上げられた花火を見る。そのとき偶然、二人のうしろを有沢と洋子の二人が通り過ぎるが、この時点では互いにそれと気づいていないのが面白い。
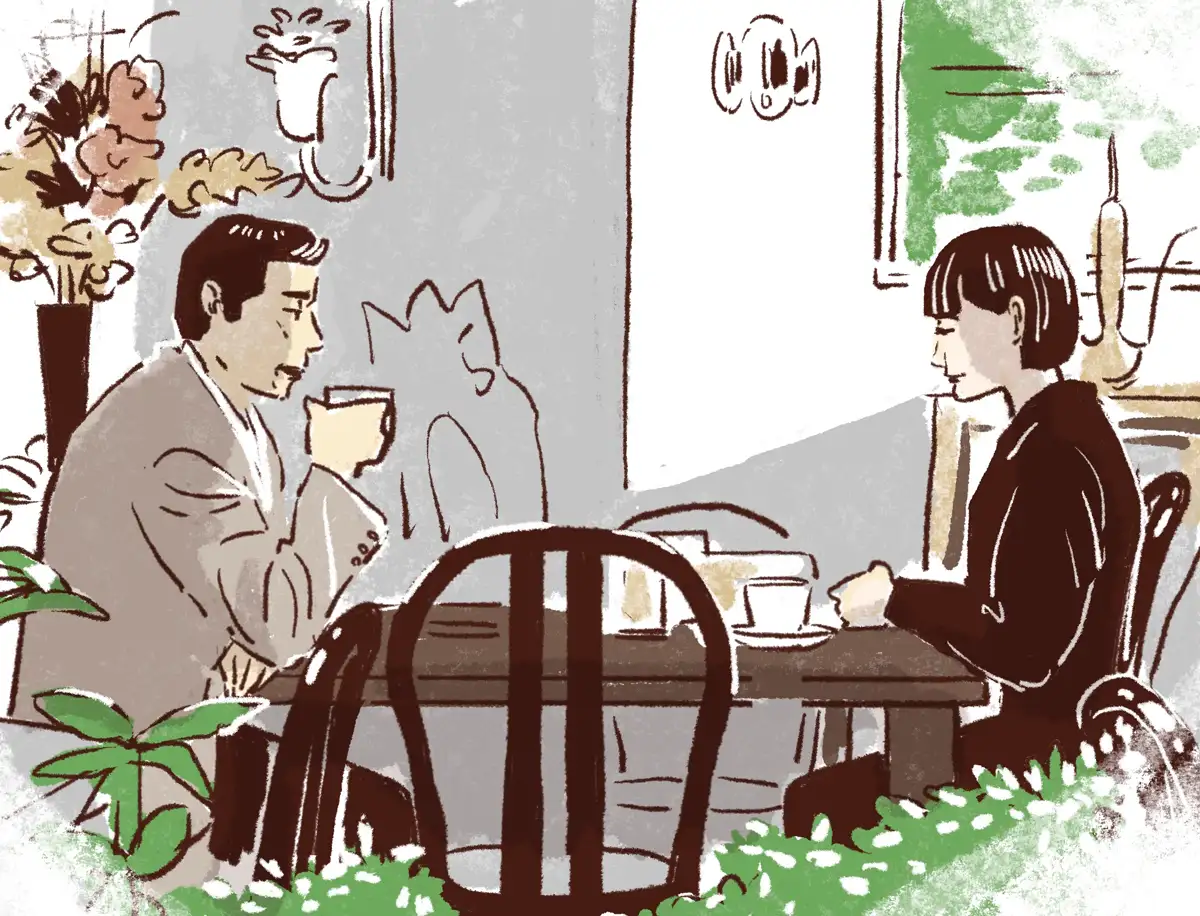
イラスト/オカヤイヅミ
素直な女心が響く洋子のセリフ。
洋子と有沢もハウステンボスのなかのホテルに泊まることになる。その前に夜のカフェで洋子が有沢にこんなふうな話をする。
「この三ヶ月、(あなたを)観察して的(まと)を絞ろうと思いました」
「的って?」
「この人と結婚しようって」
驚く有沢に洋子はさらに追い打ちをかけるように続ける。
「ただ、結婚をする気のない人とセックスする気はありません。もう二十五ですし、そういう風に考えていますから。もし今夜、私に手を出したら、それは結婚したいということだと判断します」
そのあとがさらにいい。
「そして、私は手を出してくれていいと思っています」
女性のほうが積極的になっている。彼女に押され気味の有沢が、
「ずいぶんいろいろ計画的なんだね」
と呟くと、洋子はさらに付け加える。
「普通だと思います。口に出さないだけで女は誰だってこれくらい計画しています」
山田太一は本当にセリフがうまいと感嘆する。普通なら計算高い嫌な人間に見えてしまう女性が、素直に正直に女心を語っていて、演じる深津絵里が可愛く思える。
このあと二人がホテルで結ばれるのはいうまでもない。洋子はここで着物に着替える。自宅から持ってきたという。これも「計画」のうちなのだろう。
良子の九州弁、セリフの説得力。
セリフがうまいといえば、この『大丈夫です、友よ』には、心に残るセリフが多い。
良子が神社で浩司に、チューリップの歌の替え歌を覚えているかと聞く。浩司は覚えていないので、「よく覚えるな」と驚く。すると、生まれ育った津屋崎にいまも住んでいる良子はいう。「狭いところにおるけん、こまいこと覚えとるとよ」。なるほどと思う。
あるいは、良子が浩司とハウステンボスに向かう特急列車に乗ったときに、うしろめたさもあって、良子がひとり呟く言葉。
「だいたいこの年の女がたった一日、よそで泊まるとき、こないいい訳しとるのも腹が立つ」。中年の主婦の思いがこもっている。
市原悦子のセリフがすべて九州弁なのもいい。このドラマは俳優の演技もみんないい。とくに市原悦子と深津絵里は光る。セリフがいいと俳優の演技もよくなるのだろう。
浩司を思いとどまらせる“おばん”の良子。
その夜、洋子と有沢はベッドを共にするが、良子と浩司のほうは分別をわきまえて別々の部屋で寝て一線は越えない。だから、あとで、女房のことを心配してホテルに駆けつけた昭夫の前でも、恥じることはない。誤解はとけて一緒にビールを飲むことになる。
その朝、目が覚めた良子は部屋に浩司の姿がないことに気がついて、もしやと悪い予感がして、海のほうに浩司を探しに行く。このときは、良子はドレスではなく、もとのジャージーの上着にスラックス、スニーカーという「おばん」の格好に戻っているのが好ましい。このあたりの演出も行き届いている。
良子は海を見ている浩司を探し出す。このあとの二人のやりとりも心に残るものがある。
「目が覚めたらあんたが死んどってゆさぶって泣くなんて役割ごめんやからね」。
浩司はここではじめて、取引先の大手の会社が倒産して自分のところにも影響が出た。どうせ女房も子どももいない。糸が切れてしまった。気力がなくなってしまった。しかし気がかわった。
「夕べ、良子ちゃんが楽しそうにしているのを見て、まだ生きる喜びがあるんだと思った」
「楽しそうじゃなか、ほんまに楽しかった」
二人はそうやって笑い合う。良子はこうもいう。「昨日からのことウチには刺激が強すぎて気が高ぶっとる」。あくまでも素直だ。
楽しかった過去と繫がる現在。
浩司は、良子の地道な生活者ならでは明るさ、素直さ、元気に触れて生きる勇気をとり戻した。同級生というものは有り難い。何十年ぶりかで会ったのに、親しくしている。昨日のことは、二人のあいだでいい思い出となって残るだろう。
このあと、良子は朝の散歩に出た洋子と有沢に会い、洋子に有沢を紹介される。そして浩司と昭夫を加えた五人で祝福のビールを飲み、幸福のうちにドラマは終わってゆく。
最後、オランダの民族衣裳をつけた男女が踊るのを見ながら、良子は、中学校の頃を思い出したのだろう。画面はセピア色の中学校時代の集合写真にかわり、そこに懐かしい校歌が流れる。写真には子どもの頃の良子、浩司、昭夫のまだあどけない顔が映っている。子ども時代と現在が確実につながっている。幸せな終りである。
※次回は『いちばん綺麗なとき』(9月11日公開)を予定。
川本三郎(かわもと・さぶろう)
1944年、東京・代々木生まれ。東京大学法学部卒業後、朝日新聞記者を経て、映画や文芸、都市論などを中心とした評論活動に入る。主な著書に『大正幻影』(91年・サントリー学芸賞)、『荷風と東京「断腸亭日乗」私註』(97年・読売文学賞)、03年『林芙美子の昭和』(03年・毎日出版文化賞)、12年『白秋望景』(伊藤整文学賞)がある。その他、『マイ・バック・ページ ある60年代の物語』、近著に『映画の木洩れ日』(キネマ旬報社)がある。





